|
その38 【東京国際映画祭】 今年の東京国際映画祭では、5本のフィリピン映画が上映された。 アジアの未来部門で『ある肖像画』『殺人の権利』、ワールド・フォーカス部門で『アンダーグラウンド』、CROSSCUT ASIA部門で『キリスト』『カカバカバ・カ・バ?』の5本。 その5本のうち、『カカバカバ・カ・バ?』だけは、1997年の「フィリピン映画 百花繚乱!」で上映された際に観ているのでパス。2015年にマイク・デ・レオン監督の3作品のデジタルリストア版のDVDがリリースされているので、その関係で上映されることになったのだろう。せっかくの上映なので観に行ってもいいのだけれど、平日の日中と平日の夕方18時からの上映というのは、勤め人としてはちょっとハードルが高い。仕事を抜け出して無理してまでという気にはなれなかった。 もっとも、他の作品にしても、夕方の18時とか18時10分からの上映だったりするので、仕事を抜け出さないことには観ることができないのだけれど。もう少し、上映開始時間を遅らせてくれると助かるのだけれどなあ。 それと今回、ブリランテ・メンドーサ監督をゲストに迎えての「ブリランテ・メンドーサ監督の演出論」という講演があり、ぜひとも聴きに行きたかったのだけれど、『アンダーグラウンド』『殺人の権利』とみごとにスケジュールが重なって行くことができなかった。 この講演に興味を持つ人は、フィリピン映画を観たい人とかなりの確率で重複するだろうに、そういう配慮はまったくなかったらしい。実に残念だ。 【アンダーグラウンド(Pailalim)】2017年 監督:ダニエル・R・パラシオ 出演:ジョエム・バスコン、マーラ・ロペス  ※パラシオ監督と主演男優ジョエム・バスコンのサイン 10月26日18時10分からと、10月29日10時25分からの2回の上映があったのだけれど、僕が観たのは26日の方。17時30分になるなり会社を飛び出して間に合うかどうか、実に微妙なところなのだけれど、なんとか上映開始5分前に指定席に辿り着くことができた。 上映会場は、TOHOシネマズ六本木ヒルズのSCREEN2。座席数351という、TOHOシネマズ六本木ヒルズで2番目に大きい会場である。フィリピン映画の上映に、そんな広い会場を用意する必要なんかないだろうにと思っていたのだけれど、実際にはかなりの席が埋まっていた。年々、フィリピン映画の上映に足を運ぶ人が増えてきているようだ。 もっとも、こうして上映されるのはインデペンデント映画ばかりで、大衆娯楽映画としてのフィリピン映画はまったく紹介されないままではあるのだけれどね。 さて、『アンダーグラウンド』。 実話をベースにした作品である。 貧しさゆえに、都市部の墓地に住み込み、そこで暮らす人々がいた。バンギス(ジョエム・バスコン/Joem Bascon)とバービー(マーラ・ロペス/Mara Lopez)の夫婦も、娘とともに墓地に住みついていた。 だが、そこに住みつくことは非合法であり、時には強制的な取り締まりによって墓地を追い出されたりすることになる。追い出されても他に行く場所のない彼らは、門番にいくばくかのワイロを渡し、あるいは若い女性はその身体を提供し、再び墓地に戻ってくる。 バンギスは、墓を掘り起こし、遺体とともに埋葬された装飾品を盗むことで生活の糧を得ていた。だが、娘が重い病気にかかり、医者に診てもらうための金が必要となる。やむなく、埋葬されたばかりの遺体を盗み出して横流ししようとするのだが…。 手持ちカメラを多用した映像がひたすらリアルで、非常に迫力があった。これは、明らかにメンドーサ監督の影響であろう。 Q&Aでも話が出ていたが、時には脚本がなく、役者がその場でキャラクターになりきって演技をしたというのだが、それもメンドーサ監督のアドバイスによるものなのだという。 そういう意味では、メンドーサの亜流というべき作品なのかもしれないが、映像の迫力はメンドーサ以上であったように思われる。 とにかく、力強い映像、迫力たっぷりの映像、高密度の映像に、場内の観客はすっかり打ちのめされてしまって言葉もないといったありさまで、エンドクレジットが終わったところでの拍手にもいまいち力が入っていない。それほど、圧倒的な映画だったのだ。 そして、主役を演じたジョエム・バスコンとマーラ・ロペスも素晴らしかった。特に父親になりきったジョエム・バスコンの存在感が圧倒的だった。 このジョエム・バスコン、出演映画の本数は非常に多く、僕の観ている作品も何本かあるのだけれど、主役としての出演はあまりないようで、まったく記憶になかった。おそらくは、実力派の脇役といった起用が多い役者なのだろう。 そして、その妻を演じるマーラ・ロペスはというと、マリア・イザベラ・ロペスの娘なのである。父親は日本人で、本人も日本語を話すことができるらしい。ぜひ、ゲストとして来日してほしかったのだけれど、残念ながら今回の来日はかなわなかった。 監督のダニエル・R・パラシオ(Daniel R. Palacio)は、ブリランテ・メンドーサ監督が主宰するワークショップに参加し、本作が長編1作目となる。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【アンダーグラウンド:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★ダニエル・R・パラシオ(監督) ★ジョエム・バスコン(バンギス役) 司会:これからQ&Aを始めさせていただきます。司会の島、通訳の鈴木です。よろしくお願いします。今日は、かなり興味深い話が聞けそうですね。 それでは、ひとりひとりご紹介していきましょう。今日のゲストは2人です。まず脚本・監督のダニエル・R・パラシオさん。そしてもうひとりご紹介してしまいましょう。主演いたしましたジョエム・バスコンさんです。まず、ひとりひとりご挨拶を。パラシオさんからお願いします。 監督:皆さん、楽しんでいただけたでしょうか。お招きいただきまして、ありがとうございます。 バスコン:皆さん、本当に今日はありがとうございます。この作品を楽しんでいただけたらと思います。また、東京国際映画祭にもお礼を申し上げたいと思います。 質問:最初に事実に基づく話とありましたが、どこの部分が事実で、そうでない部分がどこなのか気になったので教えてください。あと、見ている時に、ドキュメンタリーなのかなと思うくらいすごくリアルで、街全体もセットなのか本当にそのまま街を使われているのか、俳優たちも出ている人たちみんな俳優なのか、そうじゃなくて病院のシーンも俳優ではない人に協力してもらってやったのか、というあたりもあわせてお願いします。 監督:とてもいい質問ですね。プロデューサーのブリランテ・メンドーサと私はこの映画のことを「ドキュドラマ」と呼んでいますが、まさにドキュメンタリータッチであって、生々しさを見せたいという気持ちがありました。私たちの手法としては、できるだけ観客がすぐにこの世界を感じられるというか、体験できるようにしたいということで、そういう「ドキュドラマ」という方法を採用しました。 映画は90%が事実です。実際、ロケも本物の墓地で撮っていますので、プロダクションデザイナーはほとんど仕事がなく、とても楽だったのではないでしょうか(笑) 質問で、病院のシーンということをおっしゃっていましたが、私の恩師であるメンドゥーサ監督からも色々とアドバイスをもらって、彼のやりかたでもあるのですが、あのシーンは脚本がないんですね。脚本がなくて、キャラクターがこういう人物なんだと説明をして、あとでジョエムさんからもそのへんの手法、演出法については話があると思うのですが、病院の実際の看護師さんに、普通に患者が来た時と同じように扱ってくれと頼んで撮影をしています。彼らは普通にやっているとおりに動いてくれたわけです。 バスコン:実際、とても大変でした。はじめにリハーサル的なミーティングをしました。実在する人物、この映画のモデルになった人たちがいるわけですね。そこで私たちは、実際に2〜3日、彼らと一緒に墓地で過ごして、そこで体験したことからキャラクターを自分のものにしていきました。ですから、我々はそうしたリサーチをもとに、実際にキャラクターがこういう人物だということを把握した上で、今度は状況を伝えられ、その状況の中でいかにそのキャラクターが行動するかとかを考えて、そのキャラクターなりの行動なり動作なりをするわけです。 これはメンドーサ監督が考案した「ファウンド・アクティング」というメソッドなのですが、なにしろ脚本がない状態で、状況を与えられたことにリアクションをする、環境を与えられて演技するということなんです。 質問:最後にもうひとついいでしょうか。監督がいまこの作品を撮ろうと思った理由、経緯、きっかけというものはどういうものなのでしょうか? 監督:私は、墓地に暮らしている人たちというごく少数の人たちの話だけではなく、すべての見はなされた、どちらかというとアウトカースト的な、あるいは社会に無視されている人たちを取り上げたいと思いました。家族内でもそういうことは起こり得ますし、具体的にこの墓地の人たちということではなくて、橋の下で暮らしている人たち、ダンボールの家に住んでいる人たち、そういう人たちがフィリピンにはたくさんいます。私たちフィルムメーカーがこういう人たちのことを題材にしなかったら、いったい他に誰がとりあげるのかという思いで、いまこの題材を取り上げました。 質問:おふたかたからは、最初にエンジョイしていただけましたでしょうか?と言われたんですけど、打ちのめされてエンジョイどころではなかったという感じです。あの、手持ちカメラを多用した映像がたいへん迫力いっぱいで、このあたり、メンドーサ監督と共通しているなと思いましたし、俳優のおふたり、バスコンさんとマーラ・ロペスさんも迫力たっぷりで、それにも圧倒されました。 質問ですが、フィリピンのインデペンデント映画って、時としてむちゃくちゃ短期間で映画を撮影してしまうことがあるのですけど、この作品の場合はだいたいどのくらいの日数をかけて撮られたのでしょうか? 監督:11日間で撮影しました。しかし、最初の脚本の段階では3時間くらいある長いものでした。実際、かなり膨大な量を撮影して編集をしなければなりませんでした。どう編集するかブレインストーミングを繰り返して、とにかくカットしていかないといけないのですけど、いつまでたっても終わらず、ぜんぜん休めない、眠れない、終わりなき苦戦が続きました。でも、まさにこの映画のテーマにも不眠不休みたいなところがありまして、彼らの実際の生活というものは、休むどころかちょっと寝ると2秒でもう起こされるというような状況なので、我々もそれを経験したということになるわけです。 (これは、僕からの質問でした。) 質問:(英語で)なによりも第一に、このような素晴らしい映画を生み出されたことに対し、パラシオ監督とバスコン氏にお祝いを述べさせてください。おめでとうございます。東京国際映画祭でこのような作品に出会えて、たいへん感動しています。 ところでバスコンさんにお聞きしたいのですが、この役を演じる上でのインスピレーションというものはどういうところから受けたのでしょうか。というのも、私はあなたから、とてもとても深い父親の情愛というものを感じました。それから監督にうかがいたいのですが、カトリック教会の中での撮影では特にトラブルとか問題とかはなかったのでしょうか。 バスコン:ありがとうございます。私は、現実の世界では父親にはなっておりません。いまだ独身なんです。キャラクターについてリサーチしたとき、娘をもつというのはどういうことなのか、父親になるというのはどういうことなのか、父親らしく動くには、父親らしく感じるには、そういうことを実際に尋ねました。映画撮影中は、本当に自分が父親だと完全に思い込んでいましたので、父親になりきっていたのだと思います。 教会については、撮影中に問題があったかどうかというと、正直に答えると私にはわかりません。私たちはゲリラスタイルで撮影していたので、私たちはそこにいる人たちに知らせることなくカトリック教会の中に入っていって撮影をしました。だから、まわりの人たちはいつもと同じように行動していましたし、ごくごく自然なシーンが撮れたのだと思います。 監督:教会のシーンですが、撮影するということは教会の方には知らせていないわけですから、彼らが気づかないうちに撮ってしまいました。きっと、この映画を見たら、カトリック教会としては多少居心地が悪いような気持になると思います。でも、それでなんらかの行動をとっていただければと思います。 司会:それからさっき父親らしいという話があったんですけど、映画の時とジョエムさん、顔が違うような気がするんですけど。 バスコン:映画を撮影するとき、お父さんらしく見えるように、いっぱい食べて体重を増やしましたから。 質問:映画の中に「アクションライン」という組織が出てきて、墓地に住む人たちを追い出していたのですが、あれはどういう人たちで、実際にあのような組織がフィリピンにいくつも存在しているのでしょうか? 監督:あの「アクションライン」という人たちは、国に雇われている公的機関の人たちです。墓地に住むということは違法なので、彼らはああやって襲撃して、貴重品や物を奪っていきます。そうすれば、墓地に住まなくなるわけですから。 司会:それから皆さんも気になっていると思います。僕も気になっているのですが、あれは本当のお墓で、お墓に許可をとって撮影をしているのでしょうか? 監督:実際にこのできごとが起きたのと同じ墓地で撮影をしています。許可をとるのはぜんぜん難しくなくて、お金を払いさえすればいいんです。 この墓地は私の映画以外にも3本の映画の撮影で使われていて、ひとつはローカルスパイダーマン(エリック・マッティ監督の『スパイダーボーイ ゴキブリンの逆襲』のことだろうか?)で、あとはホラー映画です。 司会:あれは個人のお墓ですか、それとも公共のお墓? 監督:公共の墓地です。 司会:次の映画が決まっているという話をちらっと聞きました。 監督:まだ企画してリサーチをしている段階ですが、フィリピンの中の日本というテーマを考えています。誰もが知っているように戦争があり、日本とフィリピンとの間にはネガティブなできごともたくさんありました。しかし、そこには素晴らしいできごとだってありましたし、美しいできごとだってありましたし、愛情すらありました。私は、そういうところを掘り下げていって、日本とフィリピンの美しい関係というものをもっと見いだしていきたい。いま、そういう映画を企画しています。 Q&Aセッションが終わったところで、ロビーにて監督とバスコン氏が出てくるのを待っていると、同じ映画を観ていたらしい見知らぬ男性から「いやあ、すごかったですね。今年観た映画のベストですよ」と話しかけられる。観たばかりの映画の興奮を、誰かと共有せずにはいられなかったのだろう。 そして、ようやく出てきたバスコン氏をつかまえて、映画のポスターを印刷したポストカードにサインを入れてもらう。フィリピンのマスコミから、一緒のところを写真に撮らせてくれと頼まれたので、どこかに載ったのかもしれない。 続いて監督にもサインをもらう。 毎度毎度、こういう場面で「英語が達者だったら、いろいろと話したいのに」と思うのだけれど、それが叶わないのが実に残念。かと思うと、タガログ語でしきりに話しかけている女性がいたりして、世の中にはいろいろな人がいるものだなあ。 【殺人の権利(Tu pug imatuy)】2017年 監督:アーネル・バルバローナ 出演:マロナ・スラタン、ジョン・モンソン  ※バルバローナ監督のサイン 『アンダーグラウンド』の監督、主演俳優のサインをもらって、そのままロビーに残っていると、色黒で小柄な男性が近づいてきて、英語で話しかけてきた。 「ぜひとも、この映画を観てください」 手渡された小さなリーフレットを見ると、今回の東京国際映画祭で上映されるフィリピン映画5作を英語で紹介した小冊子で、そのうちの1本、次に観る予定の『殺人の権利』のところを彼は指さしているのである。 「次に観る予定ですよ。この映画のスタッフなんですか?」 「監督です」 「ええっ!!」 どうやら、僕が『アンダーグラウンド』の監督や主演俳優に話しかけながらサインをもらっている様子を見て、この日本人はフィリピン映画に興味を持っているらしいとあたりをつけて声をかけてきたものらしい。 なんと、期せずして『殺人の権利』のアーネル・バルバローナ監督と遭遇してしまったのである。 さっそく、用意してきたポストカードを取り出してサインを入れてもらう。なんてラッキーなんだ。 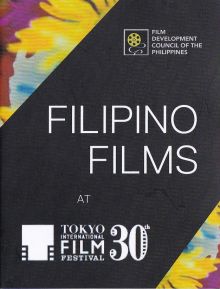 ※フィリピン映画開発協議会発行の東京国際映画祭向けの小冊子 『殺人の権利』が21時05分からなのでちょっと時間が空いてしまい、映画祭のポスターなどを眺めてブラブラしてから劇場の前に戻ると、入口の外でサインをもらう列ができていた。どうやら、台湾映画『アリフ、ザ・プリン(セ)ス』を観た後のサインであるらしい。 そこで何人もの知り合いに遭遇したのだが、そこで会った友人によると、「ブリランテ・メンドーサ監督の演出論」は、なかなか面白い内容だったとのこと。そうはいっても、フィリピン映画の上映時間とかぶってしまったからなあ。映画祭事務局は、そういうところまで気を使ってタイムスケジュールを組んでほしいよなあ、ホント。 しばし友人たちと立ち話をして、友人たちの多くは台湾映画『怪怪怪怪物!』を観に行き、僕だけはフィリピン映画『殺人の権利』を観に行く。 会場は256席のSCREEN9。なんと満席である。なにしろ、あやうくチケットを取り損ねるところだったのだ。毎度毎度思うのだけれど、いったいどういう人がフィリピン映画を観に来ているのだろう? ちょっと不思議でならない。 さて、『殺人の権利』。 ミンダナオを舞台にした作品で、これまた実話をベースにした作品である。 先住民族マノボ族の若い夫婦、ダーウィンとオブナイ。子どもたちと平和に暮らすふたりは、突如として現れた政府軍の兵士にとらえられてしまう。新人民軍によって仲間を殺害された兵士たちは、ふたりが新人民軍の居場所を知っていると疑い、案内をさせようと捕らえたのだった。だが、マノボ族を見下す兵士たちは、ふたりの服をはぎ取り、裸のままジャングルの中を引きずりまわし、ひたすら屈辱を与える。 やむなく、ふたりは新人民軍が原住民のために開設した小さな学校まで兵士たちを案内するのだが…。 前半はひたすら政府軍の兵士によるハラスメントが続き、観ていてはらわたが煮えくりかえってくるような怒りを覚える。冒頭の家族の描写が平和で幸せそのものだっただけに、本当に兵士たちが憎くて憎くて仕方がなくなってくる。このあたり、監督の力量がただものでないことをうかがわせると同時に、妻を演じた女性(マロナ・スラタン/Malona Sulatan)の存在感が大きい。 この女性はプロの俳優ではない。本当のマノボ族の女性なのである。役者じゃない女性に、ここまで要求するのか!というような場面が続くのだけれど(裸のままジャングルの中を歩かされたり、泥の中に顔を押しつけられたり)、それでも毅然とした力が目に宿り続ける。どのように貶められようとも、人間の尊厳を失わないこの女性の存在こそが、監督がこの映画に託したものではないだろうか。 素人でありながら、このような過酷な役にチャレンジしたこの女性に、心から拍手を送りたい。 なお、映画を観ながら、この女性が誰かに似ているとずっと思っていたのだけれど、途中でハタと気がついた。宮崎あおいに似ているのだ。あどけなさと、毅然とした力強さが同居する宮崎あおいのオーラが、この女性にも感じられるのだ。 ちなみに、彼女だけではなく、他の出演者もほぼ全員がプロの俳優ではない。政府軍の兵士のひとりを舞台俳優が演じている以外は、ほとんどが素人なのだ(夫婦の娘を演じているのは監督のお嬢さんで、政府軍の兵士のほとんどは映画のスタッフとのこと)。 世の中には、プロの俳優を必要としない映画、プロじゃない方が効果をあげる映画というものも存在するのかもしれない。 ミンダナオでは相変わらず紛争が続いているということは知ってはいたが、それはイスラム系のテロ組織と政府軍の戦いであると思っていた。新人民軍と政府軍との戦いというものは、マルコス政権時代の話だと思っていた。 ところが、この映画のもととなった事件が起きたのは2014年のことなのだという。映画の最後に、実際に政府軍の兵士につかまって、裸にむかれてジャングルを引き回されたという女性のインタビュー映像が挟み込まれるのだが、そこに出た2014年という字幕に、正直びっくりしてしまった。いまだにこんなことが続いているなんて! ちなみに、ミンダナオにおけるこうした悲惨な状況を題材にした映画を観たのは、これが2本目である。 1本目はマリルー・ディアス=アバヤ監督の『光、新たに(Bagong Buwan)』という2001年の作品である。それからずっとこうした状況が変わっていないだなんて。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【殺人の権利:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★アーネル・バルバローナ(監督) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 司会:ただいまご覧頂きました『殺人の権利』、監督がいらっしゃってますので、お迎えしていろいろお話しをうかがってみようと思います。 皆さん、それでは拍手でお迎えください。アーネル・“アルビ”・バルバローナ監督です。 (民族衣装を着た監督が、大きな袋を持って登場する) ようこそいらっしゃいました。まずはひとこといただけますでしょうか。 監督:皆さん、今日は私の映画を観ていただいて、しかもこの時間まで残っていただけたことに感謝申し上げます。私は皆さんの声を、自分の地元ミンダナオに持って帰れるということを非常に嬉しく思っております。 司会:監督はミンダナオからいらっしゃったということでよろしいでしょうか。 監督:はい。私はミンダナオで生まれて、ミンダナオで育ちました。 司会:この映画ですけど、これは実際にこのような事件があり、そのことから映画を着想されたということなんでしょうか。 監督:当初、自分の民族に関するドキュメンタリーを考えていたのですが、この映画の最後の方に出てくる実際の人物が遭遇した事件から触発されて、2014年の彼女の事件が、私たちにとってより効果的なショーケースになると考えて映画化することにしました。 司会:今日、実はですね、民族楽器までお持ちいただいて、あとでお楽しみがあるそうでございます。それでは、皆さんからの質問を受けていきたいと思います。 質問:大変印象深い映画をありがとうございました。政府軍のやりくちに、ものすごく腹が立ちました。 で、背景に関する知識が不足しているもので、最初、NPAと政府軍との戦いということで、マルコス政権下の話かな、昔の話かなと思っていたら、最後の方で2014年と出てびっくりしたのですけど、いまだにあのようなことが行われているということでしょうか。それと、政府軍をあのように描くことに対して、なんらかの圧力のようなものというのはないものでしょうか。 監督:実際にこれは2014年に起きた話で、こういう形でのいわゆるハラスメント、特に原住民に対してというものがいまだに行われておりました。ミンダナオでは長年にわたって内戦が続いており、私はそういうことを外の人に対して伝えたいと思っておりました。いまのところ、特に圧力というものは受けておりません。 (本当はもっと長々と答えているのだけれど、通訳の人が完全にはしょって訳すので、これだけしか書き起こすことができなかった。なお、例によって例の如く、この最初の質問は僕からのものでした。) 司会:これはマニラで行われているシナグマニラという映画祭でグランプリをはじめ賞をいくつかおとりになって、その意味では堂々と上映できているということなんでしょうかね。 監督:政府としては、市民に対して基本的な社会福祉事業を提供しなければならない立場であると思います。しかし、地方に行くと、なかなかそこまで手がまわらず、最低限の社会福祉事業すらおこなわれていないという状況があります。こういうことがおこなわれているんですよという批判的な意見を提示することで、なにかしら平和的な解決につながっていけばいいなという想いもあって、この映画の撮影をしました。 (これも、質問と回答とがチグハグなのだけれど、明らかに通訳がおかしいせいでしょう。) 質問:(英語で)このような重要な題材を扱った素晴らしい映画を撮っていただきまして、ありがとうございます。こうした民族の苦闘というものは、フィリピンだけではなく、インドや沖縄など世界中で繰り広げられているというのが現実だと思っています。 監督への質問ですが、この映画を観ていると、NPA(新人民軍)と現地の人たちとの間に、ある種のシンパシーというんでしょうか、協力体制のようなものがあるように見受けられましたが、そのことをもう少し具体的に説明していただけませんでしょうか。 監督:そうですね、実際のところ、現地の人と新人民軍との間に、ある程度の協力体制というようなものがあるとは言えるでしょう。反政府軍に対して、現地の人は近い位置にあるといえると思います。またその一方で、部族間での争いも行われていて、それもひとつの現実なのかなと思っています。 質問:もうひとつお聞きしたいのですが、映画の中に小さな学校が出てきます。その中で部族民に対して新人民軍の先生が教えているわけですが、その内容は彼らの歴史の一部ということで、おそらくはすでに知っていることではないかと思うのですが、それでもやはりそういう形で授業が行われているものなのでしょうか。(英語での質問だったのだけれど、通訳の訳した日本語がほとんど意味不明で、何を質問しているのかよく分からなかった。おそらく、質問していることは、この日本語とはまったく違うことだったと思う。) 監督:ミンダナオも長い歴史を持っているのですが、内戦が続く中、外から見ると政府がある程度指示を出してこういう学校を運営しているのかと思われがちですが、実際にはそうではない非営利団体のような組織がこういう学校を支えて、先住民にも教育をしていかなければいけないということでやっているのが現状かと思います。 質問:自然がすごくダイナミックできれいだなと思ったのですが、あれはすべてフィリピン国内で撮影したのでしょうか。 監督:実際に地元の人が暮らしているコミュニティで、実際に地元の人を使って撮影しています。 質問:内戦の地域とかと、接したりしてないんですか? 監督:私が住んでいる町のすぐ近く、バスで3時間ほど移動して、そこからさらに2〜3時間歩いたくらいの場所で撮影しました。 司会:役者さんは原住民の方々と、軍隊の方はプロの役者さんなのでしょうか? 監督:原住民を演じているのは、本当に現地の人たちです。父親と母親も、本物の現地の人です。ただ、娘を演じているのは私の娘です。軍人については、軍曹を演じているのは私も一緒に何回か仕事をしたことのある演劇をメインにやっている俳優で、大佐役はこの作品がデビュー作となる新人俳優で、残りは私の撮影クルーが演じています。 司会:はい、ありがとうございました。それでは、今日お持ちいただいたのは、それは楽器なんですね。映画の中で鳴っている楽器とうかがっています。ちょっとそのご説明と、ちょっと弾いてくださるということで、よろしくお願いします。 監督:この弦楽器はフィリピンの民族楽器でクブロンといいます。もともとはインドのシタールが変化したものと言われています。音としては、日本の琴が近いのではないでしょうか。 実際、映画の中の音楽は自分で手がけていまして、弦楽器とキーボードを使って映画の中の音楽を作りました。 (ここで監督による歌いながらの民族楽器の演奏があり、それをもってQ&Aは終了となった。) ※あらためてQ&Aの録音を聞き直してみると、明らかに通訳の方はゲストが喋っていることのごくごく一部しか訳していないし、しかもゲストがしゃべっていることのいちばん肝心な部分が抜けていたり、あるいは意味が伝わるように訳していなかったりということが大半を占めているようでした。 本当は、自分が録音を聞き直して、ゲストが喋っていることを訳すことができればいいのですが、自分にはとてもとてもそのような能力はないので、どのようにテープ起こしをすればいいのか、正直、かなり悩みました。 結局、ゲストが喋っているうちの聞き取れる部分は自分で訳して、それを通訳の訳で補足し、あるいは自分で推測し、聞き取れない部分(これが大半なんだけど)については、ゲストが喋っている通りかどうか分からないけれど通訳の訳を採用したり、あるいはばっさり切り落とすというようなことをしています。 結果、正しいかどうか、自分でも判然としない採録となってしまっています。おそらくは、監督が喋っているいことの3分の1ぐらいになってしまっていると思います。 この採録を読む場合、そのようなことを常に念頭においておいていただければと思います。 なお、YouTubeに別の日に行われたQ&Aの動画がアップされています。 監督の楽器演奏の様子もこちらで見ることができます。 別の通訳なので、こちらの方がよほどちゃんとした日本語になっています。 すでに監督のサインはもらっているので、Q&Aが終わったところで速攻で帰ろうとすると、なんと2列並んだ下りのエスカレーターの隣りに監督がいるではありませんか。 思わずエスカレーターごしに手を伸ばして力強く握手をしてしまう。 「この映画を作ったのは、ミンダナオの人に対して、とってもいいことですよ」と、拙い英語で伝えると、「僕もこの映画をミンダナオの人たちのために作りました。だから、タガログ語じゃないんですよ」。 そう、兵士たちが使っている言語はタガログ語だったかもしれないが、その他の場面で使われていた言語はタガログ語ではなかったのだ。 「マノボ語ですか?」と聞くと、監督がうなずく。 そのまま外に出たところで、ミンダナオの民族衣装を身につけた監督の写真を撮らせていただくと、横にいた女性を引き寄せて一緒にカメラにおさまってくれた。おそらく、奥さんなのだろう。  【ある肖像画(Ang Larawan)】2017年 監督:ロイ・アルセナス 出演:ジョアンナ・アムピル、レイチェル・アレハンドロ  ※セレステ・レガスピさんと監督のサイン この映画は10月30日13時50分からと31日20時40分からの2回上映があり、勤め人としては夜間に上映される31日を選ぶしかなかったのだけれど、30日に行かなかったことを大いに悔やむこととなった。なぜかというと、30日の上映では主演女優のレイチェル・アレハンドロさんが舞台にあがり、共演のセレステ・レガスピさんとのデュエットを披露してくれたというのに、31日の上映ではそのレイチェル・アレハンドロさんの姿がなかったのだ。いかんともしがたい事情があったのだろうけれど、2日続けての登壇がなかったのは実に残念。 ま、それはさており、当日のレポートを始めよう。 上映開始が20時40分で、映画が120分あり、その上映終了後にゲストを迎えてのQ&Aがあるという、例によって例の如くの「終電は大丈夫かあ!?」というタイムスケジュールである。なにしろ、Q&Aのあとで、ゲストが出てくるのを待ってサインを貰ったりするので、いっつも終電ギリギリになってしまうのだ。 ところが、会場に向かうエスカレーターに乗ってふと後ろを観ると、これから観る映画のプロデューサーと監督がそこにいるではありませんか! なぜ分かったかというと、このプロデューサーというのがフィリピンの大物女優であるため、絶対にサインをもらうぞと思ってきっちり顔写真のチェックをしておいたからなのです。 さっそく、「おそれいりますが、セレステ・レガスピさんですか?」と呼び止めてサインを貰ってしまう。 突然、見知らぬ日本人から名前を呼ばれたレガスピさんから「あなたは何者?」みたいなリアクションをもらってしまったのだけれど、そりゃそうだよね。だって、日本人で彼女の名前を把握している人間なんて、そうそういるわけがないもん。 でも、彼女は本当にすごい人なのです。今回こそプロデューサーとして招聘されているのだけれど、本来は女優であり歌手であり、しかも、リノ・ブロッカ、イシュマエル・ベルナール、マリオ・オハラといったフィリピンを代表する伝説的な監督の作品に出た方なのです。 ついでに、監督のサインも貰う(笑) そりゃ、ぜんぜん知らない監督のサインよりも、往年の大女優のサインの方が優先だよね。  さて、『ある肖像画』。 フィリピン映画には珍しく、本格的なミュージカル映画である。『シャシャ・ザトゥーナ(ZsaZsa Zaturnnah Ze Moveeh)』『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ(I Do Bidoo Bidoo)』のように、音楽をたっぷりと取り入れた映画がないわけじゃないけれど、それでもあれはミュージカル映画というわけではなかった。あくまでも、映画のひとつの要素として歌の画面が取り入れられていたにすぎない。インド映画をミュージカル映画とは呼ばないのと同じだ。 しかし、『ある肖像画』は、歌によってセリフがかわされるという、本格的なミュージカルだったのだ。 しかも、ミュージカルということでただただ楽しい映画を予想していたら、楽しいだけではなく、人間の尊厳、アイデンティティ、人生といったことをいろいろと考えさせられる映画でもあった。なかなか、奥深い映画だったのだ。 かつて、毎週金曜日になるとパーティが開かれ、セレブたちが集った館。それがいまでは電気代、水道代にも困るほど凋落してしまっている。有名な画家だった年老いた父は、ある事故以降、部屋にこもったまま出てこようともしない。カンディダ(ジョアンナ・アンピル/Joanna Ampil)とパウラ(レイチェル・アレハンドロ/Rachel Alejandro)のふたりの娘がなんとか屋敷を維持しているのだが、家を出た兄と姉の仕送りも滞りがちで、ことあるごとに屋敷を売り払ってしまえと妹たちに迫ってくる始末。 ところが、父が最後に描いた1枚の肖像画が素晴らしいと世間で話題になり、なにかとその肖像画を目的に人々が屋敷に押しかけてくる。 その絵を売れば大金が入り、生活が楽になるのは分かっているが、父からふたりの娘への贈り物として描かれたその絵を売りたくはない。 だけど、いちいち値切らないと日々の買い物すらできない生活からは抜け出したい。 ストーリーは極めてシンプルで、そんな状況にある姉妹を中心に、様々な人物が屋敷にやってくるのをミュージカル形式で描いていくだけである。 が、それでいて深いのだ。 最後は、自分は自分らしく生きればいいのだという力強いメッセージで締めくくられる。ある意味、世界中に散らばって働いているフィリピン人に対する応援歌のようにすら思えてしまう。 もともとは、古くから舞台で演じられていたミュージカルである。 プロデューサーであり、主要な脇役として登場するセレステ・レガスピ(Celeste Legaspi)も、かつてこの舞台に立ってを演じたことがあるという。 主演のレイチェル・アレハンドロも、舞台で同じパウラを演じたことのある歌手だ。 それを3年がかりで映画にしたのだという。 舞台となるのは太平洋戦争開戦前夜である1941年のマニラ。スペイン風の屋敷は、マニラのイントラムロスという城壁に囲まれた城塞都市の中にあり、主人公たちがかつて楽しんでいた生活もすべてスペイン文化の影響を受けたものである。古き良きフィリピンの光景なのだろう。すでにアメリカの統治下となっていたフィリピンではあるが、スペイン統治による文化が色濃く残っていた時代でもある。 もっとも、この直後に日本軍の空爆によってイントラムロスは焼け落ちることとなるのだが。永遠に失われてしまったその光景、古き良き優雅なる日々への、限りなきノスタルジー。 とにかく、その1941年の風俗を再現する美術が素晴らしい。 もうひとつの主役ともいうべき屋敷は、実際にバタンガス(ルソン島南部にある州で、マニラから長距離バスで2時間ぐらいかかったように記憶している。そう、僕は2度ほどこのバタンガスに行ったことがあるのだ)にある屋敷で撮影したとのことだが、屋敷の外部はイントラムロスに残っている建物などで撮影されたらしい。 屋敷内の調度品、登場人物たちが着ている衣装など、当時の雰囲気を見事に再現している。 そしてもうひとつ素晴らしいのが、登場人物のひとりひとりが皆生き生きと描かれているということ。脇役のひとりひとりまでが、ちゃんと輝いているのだ。 酒場のピアノ弾きをしている下宿人のところに、2人の踊り子がほろ酔いで遊びにきて、そこに古い知り合いの議員夫妻が娘と遊び人風のカップルを連れてやってくる場面が特に素晴らしい。2人の踊り子がピアノの演奏で楽しく唄い踊っているところに、唐突に議員の妻(演じているのはプロデューサーでもあるセレステ・レガスピ)が登場したとたんに場面が一気に明るくなる。これが大女優のオーラというものだろう。そしてさらにカップルの女性を演じているツァツァ・パディーリア(Zsa Zsa Padilla)が踊り出し、もう楽しいったらありゃしない。 警察官役で有名な歌手のオジー・アルカシッド(Ogie Alcasid)が出ているのは分かったけれど、他にも有名な人が山のように出てきている気配が濃厚。あっ、『インビジブル(Imbisibol)』の上映で来日した時にサインをもらったベルナルド・ベルナルド(Bernardo Bernardo)さんも出ているじゃん。 監督はこれが長編3作目となるロイ・アルセナス(Loy Arcenas)。ニューヨークの演劇界でキャリアを築き、2011年にフィリピンに帰国して「たまたま映画界に足を踏み入れることになった」という人物らしい。 上映終了後に4人のゲストを迎えてのQ&Aがあったのだが、1人が喋るとそれが終わらないうちに他の1人が喋り出し、続けて別の1人が喋り出し、また最初の1人が喋り出すという通訳泣かせのトークがものすごく楽しかった。みんな、この映画について喋りたくて喋りたくて仕方がないみたいだった。 もちろん、僕も質問をしたのだけれど、質問の前振りにセレステ・レガスピさんに讃辞を贈ったところ、それに対する返事があれこれあって、なかなか本題の質問に入れずに思わず笑ってしまう。ま、質問よりも、レガスピさんに讃辞を贈ることの方がメインの目的だったからいいんだけどね。 そして、Q&Aの最後には、来場してくれた観客に感謝をこめてレガスピさんが歌を唄ってくれたのだった(主演のレイチェル・アレハンドロさんがこの日のQ&Aにいらっしゃらなかったのは、重ね重ね残念だ)。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【ある肖像画:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★ロイ・アルセナス(監督)、 ☆セレステ・レガスピ=ギャラルド(エグゼクティブ・プロデューサー) ☆ガーリー・ロディス(エグゼクティブ・プロデューサー) ★アレンバーグ・アン(プロデューサー) 〈司会〉 ★新谷里映(映画ライター) 監督:本日は、この作品を観るためにご来場いただきまして、まことにありがとうございます。この作品は、ミュージカルの舞台を映画化するという、ひとつのプロジェクトとして始まりました。私はこの作品を、国内そして世界中にいるフィリピンの方たちへのラブレターだと思って作りました。 セレステ:こんばんは、皆さん。『ある肖像画』が、ここ東京国際映画祭においてワールドプレミア上映されたことを、私たちはたいへん喜ばしく、光栄に思っています。そして、この会場にいらして、私たちの映画を観てくださった皆さん、本当にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。 ガーリー:20年前、私たちはニック・ホアキン(原作者)の『ある肖像画』をミュージカルとして上演することを夢見ていました。そして、私たちがミュージカルとして仕上げた当時、観客の評判がたいへんよかったので、今度はいつの日か映画にしたいと夢見るようになりました。そして20年たった今、皆さんがこんな遅い時間まで私たちと一緒にここで過ごして、映画を心から楽しんで、この作品を認めてくれたということを、私たちは大変嬉しく思っています。ハッピー・ハロウィーン。今宵、この会場にいらっしゃってくださって、本当に本当に本当にありがとうござます。 アレンバーグ:こんにちは。20年前、私はまだ高校生でした。オリジナルのミュージカルを舞台で観た時は、単なるファンにすぎませんでした。ファンとして写真にサインをもらったりしていました。そして20年たって、こうやって実際にこの映画の仕事にかかわることができているというのは、本当にしあわせなことだと思っています。 司会:ありがとうございます。皆様の質問を受けつける前に私からひとつおうかがいしたいのですが、いま20年前の舞台から映画化へというお話しがありました。監督からも、プロジェクトのひとつだというお話しがありました。なぜこの題材でこんなにも長い間プロジェクトを続けていられたのか、この題材となったものへの皆さんが惹かれている魅力というものをお聞かせいただけますでしょうか。 監督:実のところ、私がこのプロジェクトに参加したのは4年前のことなんです。セレステとガーリーから、こういうミュージカルを映画化するというプロジェクトがあるのだけれど、監督として参加してくれないかと声をかけられました。私は、オリジナルのミュージカルにある、ニック・ホアキンの原作、ローランド・ティニオの詩、ライアン・カヤバイアブの音楽、いずれもフィリピンでは最高のものだと思っていましたので、ことわる理由はなにひとつありませんでした。作品に出演する俳優も、フィリピンでは最高の方たちにきまっていますので、もちろん私は引き受けると答えました。 質問:素晴らしい作品をありがとうございました。マニラで過ごしていた楽しかった日々のことを思い出しました。フィリピンでミュージカルというと、サルスエラという、20世紀初頭に映画が入ってくる前に流行っていた芸能形式があると思うのですが、このミュージカルはサルスエラみたいなものをある程度意識していらっしゃるのでしょうか。あるいは、それとはまったく関係なく現代風のミュージカルなのでしょうか? セレステ:さきほどから繰り返し20年前というフレーズが出てきていますが、そのことについて、おそらく、私が説明できるかと思います。 1997年、私たちはニック・ホアキンに、英語で書かれていた彼の劇を、フィリピンの言葉に書き直す許可を求めました。次いで、ローランド・ティニオにフィリピン語での詩を書いてもらいました。それが20年前のことです。そしてフィリピン文化センターで、3時間もののミュージカルとして上演することができました。舞台はたいへん高く評価していただきました。そのプロジェクトが私たちにとっていかに素晴らしかったか、私たちは決して忘れることができません。それは私たちにとって、代表作ともいうべきプロジェクトとなりました。 そして5年前、ガーリーと私は、このミュージカルの映画化について話し合いました。その時点では、それは単なる夢物語にすぎませんでした。なにしろ、私たちにはまったく資金というものがありませんでしたから。映画化にはとてもお金がかかるということを知っていましたから、どこから手をつければいいのかすら分かりませんでした。しかし、資金集めに乗り出すと、思ってもみなかったことに、たいへん多くの人が手を貸してくれて、おかげでこの映画ができあがったというわけです。 さて、音楽についての質問ですね。コンガとかタンゴ、クンディマンというのは、たいていラブソングでしたけど、私たちにとっては伝統的な音楽でした。しかし、1941年というのは、フィリピンにとってスペインの時代からアメリカの時代へと移行する端境期にあたっていました。古い時代と新しい時代とがせめぎ合った時期でした。新しい時代というのは、アメリカの時代です。だから私たちが手にしていたコンガ、歌、音楽といったものは、フィリピン独自のものというよりは、アメリカの影響を色濃く受けたものでした。それゆえ、私たちが使った音楽というのは、アメリカの影響を受けたものといえます。しかし、すべてのバラード、すべてのスローな歌は、フィリピンの古い伝統的な音楽であるクンディマンをベースとしています。 フィリピンというのは本当に音楽の途切れることのない国です。実際、ほとんどのフィリピン人は歌うのが大好きです。国のどこに行こうともそこには常に音楽があります。それは、サウンドシステムから流れてくる音楽だけではなく、常に歌っている私たち自身の歌声だったりします。本当に私たちは歌うことを愛しているのです。 ※クンディマン(Kundiman)というのは、フィリピンの伝統的なラブソングのこと。 質問:結末に関してですが、姉妹とお父さんの3人が亡くなったという話でした。私は原作を読んでいないので分からないのですが、同じ原作で1965年に作られた映画だと、最後はみんな死んでなくてハッピーエンドになっているので、最後にみんな死んで亡くなるというのは、今回のオリジナルというか、意図があってやったものなのでしょうか。もし意図があるとしたら、それはどういう意図でそうしたのでしょうか。 セレステ&監督:劇の中で実際に起きるのは、世界大戦が起きて、全員が死んでしまうということでした。質問者が観たという1965年のオリジナルフィルムというのは、英語版のことだと思います。 私たちは、より現実的な結末としました。実際に戦争によって、イントラムロスにあった家はことごとく焼け落ち、あの家族が戦争を生き延びることができたとは思えません。私たちは、そういう現実に即した物語としました。 それがローランド・ティニオにとっての、このミュージカルの終わらせ方でした。彼は、実際に戦争を描き、戦争によってすべてが破壊された様子を描きました。 ※実際には、映画で描かれた物語の後日譚として、空襲によってイントラムロスは焼け落ち、館も失われたと語られているだけで、主人公たちが亡くなる場面が描かれているわけではない。 質問:大変素晴らしい映画をありがとうございました。楽しい中に、いろいろ考えさせられる部分もありました。出演者が、皆さんひとりひとりがたいそう活き活きとしていたのが素晴らしかったと思います。その中でも特にここにいらっしゃるセレステ・レガスピさんが出たところで、バッと楽しい雰囲気が出てきて、素晴らしい女優さんだと思いました。レガスピさんは、リノ・ブロッカ監督とか、イシュマエル・ベルナール監督であるとか、マリオ・オハラ監督といった、フィリピンを代表する素晴らしい監督の作品に出ていらっしゃる方なので、そういう方がここにいらしていることをたいへん光栄に思います。 セレステ:ありがとうございます。本当にありがとうございます。 質問:それで質問ですけど… ガーリー:セレステは20年前の舞台でオリジナルのカンディダを演じていました。 質問:で、質問ですけど… セレステ&ガーリー:そして、レイチェルは1990年代の舞台でもパウラを演じていました。 (ここで、セレステさんとガーリーさんが同時に喋るので、よく聞き取れなかったのだけれど、「ニューヨークで上演した時からマニラで上演した時まで」というような言葉が入っているようだったけれど、この舞台はニューヨークでも上演されていたのだろうか? もっとも、もともと英語で書かれて、英語で演じられていた舞台なので、英語圏で上演されていても不思議はないのだけれど。とにかく、2人がよく喋るので、なかなか質問に辿り着けない。) 質問:(ようやく)質問ですけど、この映画は、美術、衣裳にものすごい力が入っていたと思うんですね、当時の雰囲気を再現するために。そのことでかなり苦労されたのではないかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。それと、舞台になった建物ですけれども、あれは実際にある建物なのでしょうか。それともセットなのでしょうか? (ここで監督とセレステさんが同時にどんどん喋ってしまうので、通訳も訳しきれず、僕自身も聞き取れないので、以下はむちゃくちゃ略された回答となります。発言者のところが「回答」となっているのは、複数の発言が渾然一体となったものとご理解ください。) 回答:衣裳は当時のオリジナルのものを再現しています。オリジナルを再現するのにたいそう苦労しましたが、実はボタンをとめるためのスナップが付いていなかったのを、安全ピンでとめていたりしました。 監督:実際、私の祖母があのような衣裳を着ていたのを覚えています。1960年ぐらいまでフィリピンで実際に着られていたファッションを再現しています。 回答:建物は実際にバタンガスにある建物です。屋内の撮影はその建物でおこないました。ただし、建物の外観は私たちが再現しています。また、1階部分はイントラムロスにある建物で撮影をして、2階部分はバタンガスにある建物で撮影をしています。つまり、映画で見る建物の外観は2つの建物から作り上げられているわけです。 (ここから監督、セレステさん、ガーリーさんの3人が、お互いの発言を補足しあうようにどんどん話し出すような展開になり、さらに通訳不能状態に陥ってしまう。) 回答:最後のラ・ナバル祭り(the La Naval Fiesta)の行進の場面では、私たちは第二次世界大戦前、1941年にあった最後のラ・ナバルの行進をそのまま再現しようと試みました。飾りの花も鳩も天使も、ぜんぶまったく同じように再現しようとしたのですが、当時の300年前のものは借りられませんでした。なんとか借りることができたのは、75年前のものです。 セレステ:最後の編集の段階になって、ロイは行進の場面を短くカットしようとしました。だけど、私たちは「お願いだからもっと長くしてえ!」と頼み込みました。だって、600人ものエキストラを雇って、600人分の衣裳を用意したんですよ。 ※「ラ・ナバルの行進」とは、10月におこなわれるラ・ナバル祭りの時に、天使像や花などで飾り立てた山車を引いて、大勢で街をまわる行進のこと。 ※例によって、この質問は僕からのものでした。 質問:本当にフィリピンチャーミングな魅力のつまった、音楽と映像のいっぱい入った映画をありがとうございました。この映画のもうひとつの主人公であろう絵については、結局はボヤッとしか見えなかったのですけど、若者のうしろに老人がいて、そのうしろにたぶん街が燃えているというような絵だったのですが、私としてはやはり1941年の4年後、1945年の2月に永遠に失われてしまったイントラムロスを象徴するような絵だったのではないかと思いました。この映画全体がイントラムロスに対するオマージュとなっているので、私にはそのように思えました。皆さんの意見をお聞かせください。 監督:たいへんよい指摘で、興味深く意見を聞かせていただきました。私たちは最初から、この絵を皆さんに見せないと決めていました。観客のひとりひとりがこの絵に見いだすものは、それぞれで異なるものなので、観客のイマジネーションに委ねるのがベストであろうと考えました。そして、その絵そのものは神秘的であるべき、皆さんにとって謎であるべきだとも思っています。また、それは簡単にはとけないような謎であってほしいとも思っています。 セレステ:今夜この場にお越し下さいましたすべての皆さんにお礼を申し上げます。そしてまた、あまたある素晴らしい映画の中から、この作品を選んでくださいました東京国際映画祭にもお礼を申し上げます。もしお許しいただけますなら、ここで感謝の気持ちとして皆さんに歌を歌いたいのですが、よろしいでしょうか。 Q&Aが終了し、観客が劇場を出る際、セレステさんが出口近くに立って観客を見送ってくれる。思わず握手すると、「マラミン・サラマッポ(大変ありがとうございます)」と丁寧に礼を言われ、「とんでもないです。こちらこそマラミン・サラマッポです」と身振りをまじえて応答する。 いつもなら、このあと、ロビーでサインを貰うところだけれど、今回は上映開始前にきっちりサインを貰ってあったので、さっさと劇場をあとにすることができたのでした。 【キリスト(KRISTO)】2017年 監督:HF・ヤンバオ 出演:クリストファー・キング  ※ヤンバオ監督のサイン 闘鶏場で賭けの仲介をしているボーイ(クリストファー・キング/Kristoffer King)。彼には妻と4人の子どもがいて、家族を養うために必死に働いている。 そのボーイのある1日、長女の卒業式があり、ボスからの呼び出しがあり、闘鶏場でのトラブルがありといった、特別でもあり、ごく日常でもある1日を描いていく。 ネットでこの作品の情報を探していると「最近のフィリピンのインデペンデント映画の新人監督は、どうしてみんなネクスト・ブリランテ・メンドーサになろうとばかりしているのだ」という辛辣な評価が見つかったが、まさにそんな感じの作品だった。 特にストーリーらしいストーリーがあるわけじゃあない。ただ、闘鶏場という特殊な世界での日常をリアルに描いていくばかり。 同じブリランテ・メンドーサの影響が濃厚な作品であっても、ダニエル・R・パラシオ監督の『アンダーグラウンド』は、圧倒的な映像の力、役者の力で観客をねじ伏せていた。だが、本作にはそういったパワーはなく、とりとめもない展開が続くだけの映画という印象になってしまう。 はっきりいって、自分にとってはあまり魅力の感じられない作品だった。 そもそも、闘鶏場での賭けのシステムが、見ていてぜんぜん分からなかった。馴染みのない世界なので、もう少し説明がほしかった。 主人公のキャラクターもいまいちはっきりしない。最初は家族のために真面目に必死に働いている父親というキャラクターだと思っていたのに、娘の卒業式の夜に家族で食事に行くための金をギャンブルにつぎ込んですっからかんになってしまったりする。家族のために、いろいろなことを我慢している男じゃなかったのかよ。なんか、何を考えているのかよく分からないぞ。 妻の方だって、最初のうちは家族思いの夫のことを心からいたわっている様子だったのに、金をギャンブルですってしまうと「あんたはいっつもそうだ」と口汚くののしって殴りかかる。いっつもそうなら、普段からもっとそれらしい態度で接していればこっちだって「なるほど、そういう夫婦なのね」と分かりやすいのに。 しっかりした脚本がなくて、役者が想定していたキャラクターと途中から違ってきてしまったのでは、などと邪推したくなってしまう。 そして、とってつけたような唐突な(ある意味、とっても陳腐な)エンディングに溜息が出てしまう。 本作は、ブリランテ・メンドーサ監督が立ち上げたインデペンデント映画を対象とするシナグ・マニラ映画祭において5部門で賞を取っているが、取ったのは主演男優、助演、編集、プロダクションデザイン、音響の5部門で、映画そのものが高く評価されたというわけではなさそうだ。にもかかわらず、ブリランテ・メンドーサ監督の推薦によって、今回の東京国際映画祭で上映されることになったのである。(ちなみに26日に観た『殺人の権利』は、監督賞を含む6部門で受賞している)。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【キリスト:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★HF・ヤンバオ(監督) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 司会:皆さん、こんばんは。ようこそおいでくださいました。東京国際映画祭、フィリピン映画『キリスト』でございました。こちら、クロスカットアジアの部門からブリランテ・メンドーサ監督の推薦ということで上映いたしました。監督がいらっしゃってますので、さっそく舞台にお迎えしていろいろお話しを聞いてみたいと思います。 監督とエグゼグティブプロデューサーを勤められましたHFヤンバオ(HF Yambao)さんです。ようこそおこしくださいました。今日が2回目の上映ということになります。 監督;再びお招きいただきまして、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。 司会:滞在中、どこかに行かれましたか。 監督:はい。先週の月曜日にいくつか観光地をまわることができました。ハロウィンを経験することもできました。 司会:それから、スタッフの方がおひとり会場にお見えになっております。マーケットエージェンシーを勤められましたシャンディ・バコロドさんです。(場内にいるスタッフが紹介され、観客の拍手で迎えられる。) 司会:最初に闘鶏についてお聞きします。闘牛とか闘犬というのは日本でも知られていますが、闘鶏というのはあまり馴染みがありません。この映画にあるように、ギャンブルとして一般的におこなわれているものなのでしょうか。 監督:はい。闘鶏の文化というのは、フィリピンでは古くから根付いています。どのような地方に行っても、小さな村であっても、都市部であっても、必ず闘鶏のゲームがおこなわれています。 司会:負けた方は、あれは、死ということですか? 監督:はい。通常、戦いは片方の死で決着がつきます。ゲームはごく短時間でおこなわれ、たいていは2分の間に決着がつきます。もし2分を過ぎても両方が生きているような場合には、引き分けということになります。 司会:それでは皆様からのご質問を受けたいと思います。 質問:撮り方なんですけど、そうとう近づいて撮ってらっしゃいますけど、どういう撮り方をしているのでしょうか。 監督:撮影期間は5日間でした。実際に私たちは撮影期間が非常に限られているいうこともありまして、人がたくさん出てくる場面、例えば市場のように人がたくさんいるところ、あるいは卒業式の場面もそうなんですけど、あのような場面は実際にイベントがおこなわれている場所で、リアルタイムに撮影しています。さいわいなことに、俳優さんたちはテレビとかで顔が知られているような俳優さんではありませんでしたので、実際にそういう卒業式とか、市場の中に入っていっても、誰も気がつかずにイベントをそのまま続行してくれるので、私たちはそれを撮ることができました。その時に撮り終えないと、同じことを撮ることはできないので、カメラ3台を使ってリアルタイムでの撮影をしています。 質問:たいへん興味深く映画を観させていただきました。最近のフィリピンの若手のインデペンデント映画の監督には、ブリランテ・メンドーサ監督の影響を受けている方が多いように思われます。先日、こちらで観ました『アンダーグラウンド』という映画も、撮り方であるとか、いろいろ影響を受けていたということでした。この作品もなんらかの影響があるような感じがします。監督も実際にメンドーサ監督のもとでスタッフをされていたので、こういったところが影響を受けているなとか、そういったところがあれば教えていただけますか。 監督:『アンダーグラウンド』の監督はブリランテ・メンドーサ監督の生徒ですが、おっしゃるように、私は実際にはメンドーサ監督の生徒ではありませんでした。しかし、私は2年ほど彼のもとで彼の作品にかかわって作業をしておりましたので、そういった意味ではさまざまな影響を受けております。実際、フィルムメーカーとしてメンドーサ監督は私にとっての師匠となりますので、そういった意味では非常に影響を受けております。特に作品の見せ方ですとか、非常にリアルな撮り方をしているところなどは、ものすごく影響を受けていると思います。 (例によって、これは僕の質問でした。) 質問:(英語で)フィリピンからまいりました。フィリピンにはもっともっとずっと美しいものがたくさんあるのに、そういう中でどうして闘鶏というものを撮ろうと思ったのでしょうか。 監督:闘鶏を取り上げた理由は主にふたつあります。まず第一に、私が最初にオファーを受けたときにはすでに脚本ができあがっていたということがあります。最初にこの映画にかかわらないかということで声をかけられたのですが、撮影の1週間ぐらい前になって、ただかかわるというのではなくて監督として参加してもらえないかと言われました。私はこの映画の中の少女のように、自分の父が闘鶏の仕事をしていたというような環境で育ったわけではありません。ですが、よくよく思い出してみれば、祖父も叔父も、そして私の父も、闘鶏場に足を運んでいたという記憶は、子どもの頃のものですが確かにありました。ですので、まったくそういうことを知らずに育ったというわけではありません。それから、フィリピンにはもっと他に美しいものがたくさんあるのに、どうしてこの闘鶏をとりあげたのかということについてですが、私はこの題材そのものをポジティブにとらえております。確かに、登場人物が貧乏であったり、闘鶏には死がかかわったりしています。でも、私が注目したのはそういうことよりも、そこにある家族の姿なんです。母親や父親が子どもによりよい未来を与えるために、闘鶏場や市場で夜遅くまで一生懸命に働いていて、そして子どもの方ではそういう親の愛を感じて一生懸命に勉強して、娘さんが2番の成績で卒業する。これは非常に祝福すべきことだと思っておりますので、私はこの題材をポジティブなものとして捉えております。 質問:タイトルに関連してお伺いしたいのですが、「キリスト」と日本語であったのでイエス・キリストのことかなと思っていたら、冒頭でそのキリスト教の儀式、ホーリーウィークの頃のものでしょうけれど、それがあったのでその話かと思っておりました。ところが、あとからそうではなくて闘鶏の話ときて、なるほどと思ったのですけれど、最後に冒頭の場面に戻ってきてなにかしらオチがつくのかと思ったら、そういうわけでもありませんでした。たぶん最初のところのエピソードとその後の闘鶏の話とつながりがあると思うのですが、私がフィリピンの文化的とか宗教的な背景をそこまで深く分かっていないので、つながりがいまひとつ見えませんでした。そこのところを、少し補足していただければと思うのですが。 監督:まさにこの映画で描きたいと思っていたことを指摘していただきまして、本当にありがとうございます。まず第一に、闘鶏で賭けをしている人が両手を広げる動作をする場面があるのですが、その時の形というのがまさに十字架の上のイエス・キリストと同じなので、その動作をキリストと呼んでいます。そして第二に、フィリピン人が人生において何か問題に突き当たった時にする3つのことがあります。映画はホーリーウィークの場面から始まりますが、そのひとつは、神に祈るということです。問題に突き当たった時に、フィリピン人は神に救いを求めます。神に祈りをささげることによって、問題からなんとか解放してほしいと願うのです。そして次に、一生懸命に自分が頑張ることでなんとかしようとします。映画に出てきた両親も本当に一生懸命働いています。そして3つめですが、リスクのある行動に賭けます。人生においてはさまざまな問題が発生してきますが、その時になんらかの形で自分がリスクをとって生きていくというのも、フィリピン人のひとつの生き方なのです。今回はギャンブルでお金を賭けるわけですけど、人は時として、目的を達成するためには命すら賭けなければならないといこともあります。そして、もしすべてがうまくいかなかったとしたら、人はいちばん最初の神に祈るというところに戻ってくるわけです。私はこの映画の中で、そうしたぐるりとひとまわりするような形を、表現したつもりです。 質問:(英語で)挑戦的な映画を観させていただきまして、ありがとうございます。今回は監督を引き受けた時点ですでに脚本ができあがっていたということですけれど、具体的にどういうプロセスでこの映画の「ストーリーの発見(Found Story)」がおこなわれていったのでしょうか。 監督:今回の映画の脚本を書いたライターの方は、私の他の映画でも脚本を書いているライターで、ブリランテ・メンドーサ監督の『罠(Taklub)』の脚本を書いた方でもあります。自分たちが脚本を書く時、あるいはライターさんが脚本を書く時というのは、たとえば自分が観たものであったりとか、想像したものであったり、あるいは本当に現実にあったことから触発されて書くというのが通常の脚本の書き方だと思います。頭の中に描かれたもの、想像したものがあって、それについてたとえばこういう場所に行ったら観れるんじゃないかとか、あるいはこういう人と話したらそれに関連する話が聞けるんじゃないかとか、そういう取材をして書くというのがひとつのやり方だと思います。しかし、「実際にあったこと」と「ストーリーの発見」とで何が違うかというと、まず私たちはあまり細かい描写というものを書いたりはしません。通常はそういう場合に、私たちはさまざまな「物語」を集めます。そして、「物語」を集めて、その中の重要なイベントがなにかということに注目します。この『キリスト』の場合、どうして闘鶏の話になったかというと、プロデューサーから闘鶏の話を映画にしたいというリクエストが最初にあったからです。プロデューサーというのは、父も兄弟もみんなずっと闘鶏にかかわっていたという人なのですが、その人たちはみんなアメリカに移住してしまい、マニラに残っているのはひとりだけでした。そこで、闘鶏を題材にした映画を作りたいというプロデューサーの依頼のもとに、ひとり残っていた方に話を聞きに行き、実際にその人たちがいたという闘鶏場にも足を運びました。でも、私たちはその方の「物語」を書いたのではなくて、闘鶏場にいる様々な人たち、たとえば賭け金を集めてくる人とか、食べものを売って働いている女性の方とか、そうした闘鶏場で働いている様々な人たちの「物語」を私たちは集めました。そこから私たちの「物語」というものができてきました。それは実際の私たちの経験でもありますし、観ていただく方にとっても、実際に闘鶏場で起こっている毎日の生活というものを経験するということになるのだと思います。 司会:そろそろ時間が来てしまったようです。活発なご質問、ありがとうございました。監督の今後の活躍をお祈りしまして、お開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。 フィリピン映画上映後のQ&Aでは、必ず真っ先に手をあげて質問をする自分なのだけれど、今回は特に聞きたいこともなく、珍しく手をあげなかった。 ところが、他に誰も手をあげる人がいないので、仕方なくおずおずと手をあげて質問をしてしまう。だって、わざわざ日本まで来てくれた監督に対して、まったく質問が出なかったりしたら申し訳ないじゃありませんか。 さいわい、僕の質問が呼び水となったのか、他の人の質問がそのあとに続いてくれたので、それなりにQ&Aも盛り上がってくれた。 でも、それらの質問に対する監督の大変に冗舌な回答を聞いていると、監督の強い想いに作品のレベルが追いついていないのではという気がした。理屈ばかりが先行して、実際の力量がそなわっていないのではと思ってしまったのだ。まあ、脚本ができあがっている状態で監督の話を持ちかけられたということなので、なかなか思うにまかせなかったという部分もあるのかもしれないけれど。 作品には納得していないにもかかわらず、例によって例の如く、ロビーで監督をつかまえてサインをもらってしまう。 我ながら、しょうがないなあ。 
|