|
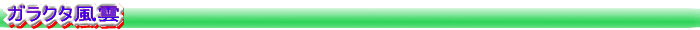
朝食はセブの潮風(2日目)
2月23日(木)
セブの朝は寒かった。ベッドには薄いタオルケットがあるだけだったので、これで充分にしのげるのだろうと思っていたのだが、なんと明け方には寒くて目が覚めてしまった。少なくとも、夜間にクーラーを使う必要はまったくなさそうだ。
ベッドに枕銭の10ペソと一緒に「毛布が欲しい」のメモを残してレストランへ。
相変わらず、潮風が心地よい。海よりのテーブルに席をとる。すぐ目の前では朝の日差しに海面がキラキラと輝いている。光の中に、両脇に竹でできたフロートを突き出したバンカーボートがシルエットとなって浮かんでいる。まるで絵に描いたような光景だ。
 |
ただし、絵には絶対に描かれない現実というものもある。僕たちが朝食を食べる席のすぐ下に地元の子どもがやってきていて、「コインを投げてくれ」と僕たちにしきりに声をかけてきた。
これが僕にとっては非常につらかった。僕にはどうしても彼らにコインを投げるということができなかった。コインが惜しいというわけではない。金額などたかが知れている。だが、コインを投げた瞬間、子どもたちをものもらいの立場におとしめるような気がしてならなかった。もちろん、子供たちに金をばらまいていいことをした気になるような、あるいは子供たちが金に飛びつく様子を見て楽しむような、そんな観光客とは一緒にされたくない、という気持ちも強かったと思う。子供たちにしてみれば、こちらのそんな思惑など関係なく金が手に入った方がいいに決まっている、ということはわかってはいてもどうしても割り切ることができなかった。
だから、必死に彼らの方を見ないようにした。そして、子供と目が合ってしまうと、黙って首を振った。それ以後、子供の姿が見えた時にはなるべく海側のテーブルには座らないようになってしまったのだけれど、なんだかとてもつらかった。
朝食はトースト、目玉焼、ハムにコーヒーという実にオーソドックスな正統派ビーチ・リゾートの朝食メニューが旅行費用にセットとなっていた。ごく普通の料理なのだけれど、調味料が日本と微妙に違うので実においしい。テーブルの上にあるバナナケチャップ(デルモンテの商品です)を目玉焼にかけて食べるとこれがおいしいんだ。その他にレッドデビルというタバスコのような真っ赤な調味料も置いてあって、これも見た目ほど辛いというわけではない。トーストだってただバターやマーマレードを塗っただけなのに妙においしい。ただ、群がるハエを追い払いながら食べなければならないのだけはたまにきずではあるが。
ビーチの方を見ると、潮の引いた砂浜に打ち上げられた海草の掃除をしている。ほうきでかき集めてはトラックの荷台に放りあげているのだが、4トントラック1台では運びきれないほどの量の海草だ。この海草が食料になればなあ、などと思ってしまう。いずれにせよ、どんなに海草が砂浜に打ち上げられようが、ちゃんと掃除をしてゴミひとつないきれいな浜にしてくれる。エルニドもそうだったけれど、これこそがプライベート・ビーチの素晴らしさだ。
コーヒーをのんびりと飲み、海をのんびりと眺める。さて、今日1日、なんの予定もなし。
コテージに戻るとちょうどベッドメーキングのさいちゅうで、メモを見たから毛布を持ってきたよ、と気さくに声をかけてくれる。客と従業員という感じではなく、友達どうしという感じで声をかけてくれるのが心地よい。ダイバー・ショップの人間の「おたがい友達じゃないの、ちったあ我慢してよ」という感じとは全く違って、「友達だもん、何でも言ってよ」って感じ。フィリピン人のこういうところって大好き。
水着に着替え、マスク、フィン、シュノーケル、ブーツなどを持ってビーチヘ。木陰にある長椅子(正式には何て言うのだろう。あの背もたれの角度が調節の出来る木製のベンチみたいなやつ)を確保してから、ジャブジャブと海の中へ入っていった。水はやや冷たいが、透明度はなかなかのもの。腰ぐらいの深さになったところでシュノーケリングの器材を身に付けて泳ぎ始める。
残念なことにそれほど魚がいない。それでも日差しを背中に浴びながらきれいな海の中をのぞきこんで泳いでいると、時間のたつのも忘れてしまう。
泳ぎながらズッと右側の方に回り込むと、岩場のところに地元の子供達がいた。4才ぐらいから小学校低学年ぐらいの子供達が6〜7人ぐらい。
「マガンタン・ハポン(こんにちわ)」
タガログ語で声をかける。だが、子供達はボケッとした表情のまま誰も返事をしない。
「アナン・パガラモ?(名前、何ていうの)」
もう一度話しかけると男の子が「ボンビ」とブッキラボウに答えた。で、他にも話しかけようと思ったのだが、話しかける言葉が何も思い浮かばず、
「シゲ・ナ、ボンビ(じゃあね、ボンビ)」
とだけ言ってそこを離れた。
泳ぎ疲れてビーチに戻るとワンダー・レーンのフレッドさんが来ていた。海に来ると疲れというものを知らなくなる政子が泳ぎ続けている間、僕はフレッドさんを相手にいろいろな話をした。例えば、セブには日本語学校が2軒あって、「サクラ日本語学校」と「サトウ日本語学校」というのだとか、フレッドさんには12才を頭に4人の子供がいて、それがみんな男の子であるとか、そんな他愛もないことをいろいろと話す。
フィリピン関係の本が出るとかたはしから読んでいるので、フィリピンについてはかなり知っているつもりだが、それでも本を読んだだけでは決して知ることのできない知識というものもある。こうして他愛もない会話をしていると、なんとなく今まで見えなかったことが見えてくるような気がする。
政子が海からあがってくる。長椅子(ホントに何て言うんだろう、あれ)に体をのんびりと休ませて、ポツリポツリと言葉をかわしたり、ボンヤリと海を眺めたり、持ってきた本を読んだりして、ぜいたくに時間を過ごす。
何もしないでいると、不意に「時間がもったいない!」なんて焦燥感にかられたりもするのだが、そのたびに「のんびりするために来たんじゃないか」と自分に言い聞かせる。貧乏性がすっかり身に付いていて、ぜいたくな時間の過ごし方ができなくなっているらしい。我ながら情けない。
ビーチに遊びに来ているのは全部で10人ちょっとくらいだった。
日本人の若い男たちとフィリピンの女の子たちのグループも来ていた。フレッドさんによると、日本から来ている学生だということだが、なんとなく好きになれない雰囲気があって近寄らなかった。
それから5〜6才ぐらいのかわいらしい女の子を連れたビヤ樽のような体格をしたおばさんが来ていた。おばさんは明かに西洋人なのだが、女の子の方はフィリピン人のようだった。なんとなく好奇心を刺激されて声をかけてみると、彼女は松下エレクトリックスに勤めているドイツ人ということだった。被女は「オハヨウゴザイマス」「シゴトシゴトシゴト」と知っている日本語を披露してくれた。お返しにこちらも「グーテンターク」「イッヒ・カン・スプラッハ・ドイチェン・ニヒト(私はドイツ語をしゃべれません)」と知っているドイツ語を披露する。しかし、女の子とどういう関係なのかはわからなかった。ひどくシャイな女の子で、こちらから話しかけても決して返事をしようとはせず、一人っきりで黙々と遊んでいた。
ビーチで寝転がっていると、カランカランと鐘を鳴らしながらアイスクリームを売りに来た。これを政子さんが素通りさせるわけがなく、15ペソでふたつ購入。フィリピン名産のマグノリアのアイスクリーム。ウベという紫いものアイスクリームが絶品なのだ。
昼には食堂でサンドイッチとフルーツサラダを食べ、サンミゲール・ビールを飲む。なんというしあわせ。
午後3時すぎに水着から着替えて散歩に出る。リゾートの中をグルグルと歩き回ると、裏の方がかなり広くて、ほとんどジャングルのようになっている。その中にポツンポツンと南国の花が咲いていたりするのだが、足もとには動物の小さな糞がコロコロとたくさん転がっていた。しばらくして、放し飼いのヤギの群れに出会ったのでヤギの糞だったのだろう。赤ちゃんのヤギがとにかく可愛らしく、なんとか写真に撮ろうとしたのだが、子ヤギは逃げるし親ヤギは怖いしでいい写真を撮ることはできなかった。
ゲー卜を抜けてリゾートの外に出てみる。塀に沿って舗装されていない小道があり、その反対側には丈の低い植物が広がっている。その中で子供を連れた女性が焚き技を拾い集めている。日差しが強烈だ。
その小道を歩き出すと、ゲートのところにいたサイドカーを付けたオートバイがスッと近寄ってきた。トライシクルという乗り物で、ジプニーなどの交通手段のない地区では貴重な庶民の足となっている乗り物だ。バタバタなどと呼ばれることもある。
そのバタバタから僕たちに声がかけられた。
「乗らないか?」
「いや、いいよ」
「どこに行くんだ?」
「この辺を歩き回るだけさ」
「乗りなよ」
「いやいや、歩くからいいの」
なんという不毛なキャッチボール。こちらはただ近所を歩いてみたいだけなのに、先方は全然あきらめる様子もなく、傍たちにピッタリくっついてくる。こちらが根負けするまで頑張ろうという気だろうか。こういうのって、正直いって疲れる。
今度はゲートから自転車に乗った男性がやってきて声をかけてくる。
「どこに行くんだ?」
「いやね、この辺をね、歩き回りたいだけなの」
自転車にもまとわりつかれるのか、とうんざりすると、意外にも披はバタバタのドライバーにひとことふたこと何かを言ってそのバイクを追い返してしまった。そして破は
「この先に写真を撮るのにいい場所があるから案内してあげるよ」
と言って僕たちの仲間に加わった。う−ん、判断保留だ。
できたら、ほっといてほしいななどと思いながら、彼と話をしながらブラブラと歩く。会話は英語混じりの日本語だ。みんな日本語が達者なのにはとにかく驚く。そのことからも、いかに多くの日本人がセブに来ているのかが分かる。きっと、日本語がしゃべれなければてきめんに収入に響いてしまうのだろう。
リゾートの塀に沿ってしばらく歩くと、お菓子や飲み物やちょっとした生活雑貨を扱うサリサリ・ストアのあるT字路にぶつかった。ニワトリやヒヨコやヤギがやたらとうろうろしている。その子ヤギがとにかく可愛らしくて、一匹欲しいと本気で思ってしまう。
そこを左に曲がった。太陽がちょうど真正面にくるのでひどくまぶしい。
炎天下の道をトボトボと歩く。道の右側にはトウモロコシなどを植えた貧弱な畑があり、その背後にはすぐにジャングルが広がっている。いたるところに椰子の木のシルエットが浮かび、日本とは全く異なる風景をなしている。どこか遠くからスピーカーで何かわめいているような声が聞こえる。自転車の彼に聞くと薬売りの声だという。車で村々を回っては口上を述べ立てて薬を売るのだそうだ。ガマの油売りみたいでなんだか面白そうだが、そういう車が回ってくるということは、薬局も病院も不足しているということなのだろう。
途中、学校から帰る女子学生と何人もすれちがった。日本でいえば中学生ぐらいだろうか。すれちがうたびに、はにかんだような笑顔を見せてくれた。
しばらく歩いたところに子供たちの集まっている場所があった。3メートルほど低くなったところに小さな池があって、子供たちがすっぱだかで泳いでいる。写真を撮るのにいい場所とはここのことだった。
海水と真水が半々に混ざった池で、深さは6メートルぐらいあるという。子供たちの絶好の遊び場になっているようで、僕たちが姿を現わすと、子供たちははしゃいで次々と飛び込みを披露してくれた。オチンチンを出した男の子たちがドボンドボンと水に中に飛び込んでいくのだが、岩にぶつかったりしないのか、お互いに頭をぶつけたりしないのか、思わず心配になってしまう。
「池の中の子供たちにコインを投げてやってくれないか」
 |
自転車の彼が僕に向かってそう言う。池の中の子供たちもそれを期待するかのように僕たちの方を見あげている。しかたがないのでコインを放ってやると、子供たちは大騒ぎをしてコインに飛びついてはしゃいだ。どうにも割り切れない気分だ。子供たちは歓んでいる。そんなに考え込むことはないのだろうか。単純に子供たちが歓んでいる姿を見て、サンタクロースのような気持ちになっていればいいのだろうか。やはり、割り切れない。
以前、バタンガスという港からミンドロ島のプエルト・ガレラというところへ行くフェリーに乗ったとき、多くの船客が海の中の子供たちにコインを投げているシーンに出会ったことがある。コインを投げている者の中には若いフィリピン人の姿もあった。決して金持ちとも思えない彼らなのに、きわめて自然にコインを子供たちに投げていたのがなんとなく印象に残っている。また、マニラでフィリピン人の友人と歩いているとき、道端の浮浪者から差し出された空缶に彼らが実にさりげなく小銭を放りこむのも何度も見ている。自分だってそれほどゆとりがあるわけではないのに、平然とそういう行為を彼らは行なうのだ。
多く持つ者が持たない者に分け与えるといってしまえばそれまでの話しだが、僕にはどうしても馴染めない感覚だ。こういう感覚的な距離を乗り越えられたなら、もっとフィリピンのことがわかるようになるのだろう。だが、なかなかそこまでは辿り着けそうにない。
自転車の彼は次に、その池のすぐ脇にあるひとまわり小さい池を見せてくれた。こちらの池は子供たちの遊びではなく、地元の人たちが洗濯に使っている池なのだそうだ。やはり、海水と真水が半々ということで、そうした水で洗濯しなければならないことからも小さな島での真水の貴重さが窺われる。ハドサン・ビーチ・リゾートでもシャワーなどに使う水をタンク・ローリーで運んできて使っているし、リゾートによってはポリ容器に水を買わなければシャワーを浴びることのできないところもあると聞いている。ふだん何気なく使っている水の重要さが、外国にやってきて初めてわかるというわけだ。きっと、畑の作物を維持するのもいろいろと大変なのに違いない。
それにしても暑い。道に戻ると地面からの照り返しで頭がクラクラする。
「あそこに行って何か飲もうよ」
少し離れた所にサンミゲールの看板を見つけて指差す。遠目には大きめのサリサリストアがあるように見えた。
だが、近くまで行くと、それはガードマンが入口に立つリゾートだった。アギス・インと看板が出ている。ゲートをくぐって中に入れさせてもらう。
中にはコテージ、プール、レストランがあったが、客の姿はどこにも見えなかった。とても清潔で静かな場所で、ハドサンと比較すると雲泥の差だ。どことなく上品な雰囲気の漂うリゾートだ。
オープンエアのレストランに入る。木を組み合わせて作られた天井の高い素敵なレストランだ。3人でジュースを飲み、のんびりとくつろぐ。ハドサンにいると、常にいろいろな人間がまわりにいるので、なんとなく神経を疲れさせてしまうようなところがあるのだが、ここはとにかく静かで気が安らぐ。レストランにいた親子らしきふたりの女性も気持ちのよい人で、即座にこのリゾー卜が気に入ってしまう。ただし、残念なことにこのリゾートにはビーチがない。セブのリゾートでビーチがないというのは致命的だ。
マンゴー・ジュースを飲み、ついでにアギス・インのオリジナルTシャツを政子と色違いで買う。ホント、これできれいなビーチでもあればこっちに泊まるのだが。
アギス・インを出ると、自転車の彼は自宅が近くにあるからと去っていった。案内してくれたお礼にと10ペソを渡そうとしたのだが、彼は受け取ろうとしなかった。やたらとこちらの金が目当てでまとわりつく人間が多かっただけに、彼のその反応がひどく嬉しかった。
今度は太陽を背にしてさきほど来た道を逆に歩き出す。ハドサン・ビーチから出てきた道を戻らずに、さらに歩くと、道の傍らで老人がギターを作っているのに出会った。ギターはセブの名産品である。そこでしばらくギターを作る様子を見させてもらう。完全な手作りだ。一般のギターがどのようにして作られるのかは知らないが、このようにしてひとつひとつ丹念に作るということはないだろう。ひとつできあがるのにどれだけ時間がかかるのやら。
さらに先まで歩くと、だんだん人家が多くなってくる。人家といっても小屋といった方がイメージしやすいような小さな建て物ばかりだ。
「この先には泥棒がいるからね、行かない方がいいよ」
庭で手仕事をしていた男性から声をかけられる。自分ひとりのときなら気にしないのだが、妻と一緒のときにトラブルに巻き込まれるのはいやだったのでその忠告に素直に従って来た道を戻ることにする。
「あのとき、ああ言われたけど、本当に危ないのかしら」
「さあてね、大丈夫だとは思うけど、知らない土地だからね」
いまだにあのときのことを思い出してはこんな会話をかわしているのだが、ホントはどうだったのだろう。
またもや、真正面にあるのはギラギラの太陽だ。顔面がジリジリと音をたてて焦げていくような気がする。すると、うまくしたものでアイスクリームの入ったケースを肩から下げたオニイサンが声をかけてきた。見ると、ビーチでアイスクリームを売っていたオニイサンだ。ちょうど家に帰ってきたところらしい。さっそくアイスクリームをふたつ買うことにする。
「マカノ(いくら)?」
「ニジュッペソね」
「ニジュッペソー! さっき買ったときは15ペソだったじゃないか」
僕が少し大袈裟に叫ぶと
「冗談だよ冗談。15ペソだよ。冗談なんだから」
彼は慌てて訂正した。その慌て方がおかしかった。どうやら、人のいい男らしい。
 |
部屋で少し休んでから食堂に行く。夕食はパパイヤサラダ、グリーンサラダ、チキンアドボ(チキンの煮込み)、ポークアドボ、エビ、カニ、イカ、ラプラプという魚料理、そしてサンミゲールが3本。食堂から見える夕日が見事だ。空一面が紫色に染まっている。心地よい潮風にふかれながらサンミゲール・ビールを片手にシーフードに舌づつみをうち夕日を眺める。なんというぜいたく。なんというしあわせ。
3日目へ 戻る
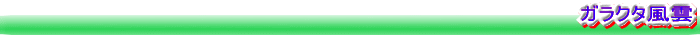
|