|
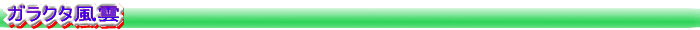
朝食はセブの潮風(1日目)
2月22日(水)
さて、朝だ。時間は8時50分。
僕は異様に重たいダイビング・バッグをガラゴロひきずりながら家を出た。セブだ。セブヘ行くのだ。今年度最大のイベント、セブ旅行へと出発する時がやってきたのだ。今は埼玉県の川口市なんてところをとぼとぼ歩いているけれど、夕方にはセブのビーチ・リゾートでのんびりと潮風にふかれるのだ。そして、サンミゲール・ビールでも飲みながら、ゆっくりと夕日でも眺めるのだ。うっとうしい日常のあれこれなどすべて忘れて、フィリピンの風にどっぶりと身をまかせてしまうのだ。
人によってはきっと、たかがセブ、なんて思うのかもしれない。村上春樹の『ダンスダンスダンス』風に言うならば、「だってセブでしょう? そんなの大磯に行くのとたいして変わらないわよ。カトマンズに行くわけじゃないもの」、あるいは「でもまあセブですから。ジンバブエに行くわけじゃないですから」というわけだ。だけど、僕たち夫婦にとっては大イベントなのだ。もう、今年最大のビッグイベントはこれで決定ってなもんなのだ。
結婚した年は新婚旅行でフィリピンのエルニド・リゾートに行き、ふたりでひたすらダイビングをした。もちろん、この旅行がこの年の最大のイベント。
次の年は夏にサイパンを計画していたのだが、どういうわけか直前になってルバンク島ダイビング・クルーズなどという企画に捕まってしまい、これに参加。ふたたびフィリピンヘ行き、これまたこの年最大のイベントとなった。
ルバング島ダイビング・クルーズで全財産を使い果たした翌年、つまり昨年はつつましやかに八丈島でダイビングにいそしんだ。残念ながらビッグとはいいがたいが、これまたこの年の最大のイベントだったのである。
そして、今年最大のビッグイベントが、このセブ旅行というわけだ。昨年はスケールダウンして八丈島で我慢したけれど、今年はもうめいっぱい楽しんでしまうのだ。待ってろよ、セブ。今年はお前を相手にギンギンに頑張ってしまうからな。ダイビング・バッグに詰め込まれたふたり分のシュノーケリング器材が活躍の時をいまや遅しとお待ちかねだぜ。
てなことを考えながらバス停に向かって田舎道を歩いていたわけだが、それにしても荷物が重い。自分ひとりの荷物ならばさほど重くもならないのだけれど、政子の着替えやら二人分のシュノーケリング器材やらなにやらかにやらいろいろさまざまなものが入っているので、とてつもなく重い荷物となってしまった。必要のないものは可能なかぎり置いてきたつもりなのだが、それでも二人分の荷物となるとかなりの分量となるものだ。
バスで南浦和駅まで出て、9時19分の南浦和始発の京浜東北線に乗る。かつて、ダイビング・バッグを持って通勤電車に乗り込み、悲惨な目にあったことがある。さすがに9時を過ぎればもう混んでいないだろうとは思ったが、念のために始発電車を狙った。なかなか細かいことにも気をつかって計画をたててあるのだ。
上野から京成スカイライナーに乗り換え。数日前に新宿の交通公社で買ってあったチケットよりも1本前のスカイライナーに間にあったので、窓口で列車を変えてもらって10時20分のスカイライナーに乗り込む。成田に着く時間が予定よりもかなり早くなってしまうが、遅れるよりはいい。特に昭和天皇の葬儀を控えて、成田でのチェックが厳しくなっているという話も聞くので、なるべく成田に早く着いた方が安心だ。
成田空港に到者。
コーヒーを飲んだり、空港内の色々な店をのぞいたりして時間をつぶし、11時55分、北ウイングにあるJAL団体カウンターで航空券を受け取る。成田からセブまでのチケット、26日に乗るセブからマニラまでのチケット、そして27日に乗るマニラから成田までのチケットの3枚がセットになっていることを確認する。
よし、大丈夫、と思ったのだけれど……ちょっと待ってよ。なに、このチケットに貼り付けてある紙。「あなたの帰国便の再確認は72時間前に必ず下記オフィスヘ連絡して下さい」だって。自分で帰りの航空券のリコンファームをしろっていうの? 冗談! 僕の英語力で、電話でリコンファームなんかできるわけがないじゃん。こういうことって、旅行会社でやってくれるんじゃないの? えーと、どうすればいいんだ。まず、ここに書いてある番号のところに電話をかけて、相手が出たら「リコンファーム・プリーズ」って言うんだよな。そして、この用紙に書いてある予約ナンバーを言えばいいんだけれど、そこで何かを言い返されたらどうすればいいの。きっと、電話じゃ聞き取れないだろうな。もしかして、予約されてません、なんてことを言われたら何て言えばいいんだろう。困った……。どうしよう。不安がじわ〜とこみあげてきちゃうじゃないか。
とりあえず、心配してもしょうがないことは忘れて、通関手続きを済ませる。はい、無事通過。そして、免税店。政子があれやこれやと香水の匂いを試すのをのんびりと椅子に座って待つ。それにしても、どうしてあれっぽっちの液体にあれだけの金を払う気になるのか。普段はスーパーのチラシを仔細に検討したあげく、「今日はスーパー・マルエツで卵の特売日ですからあなたも来てちょうだい」などと言っている人がである。本当に、女というものはわからない。
ようやく、免税店も突破。なんだか、テレビ・ゲームをやっているみたいだ。いくつもの難関があって、それをひとつひとつクリアしていかなければならないのだから。誰か、家を出てから飛行機に乗るまでをシュミレーションゲームにすると面白いんじゃないだろうか。途中で武器を手に入れると税関でひっかかったりして。
エックス線検査、金属探知機の連続攻撃をかわして搭乗ゲートヘ。
窓の外にこれから乗る飛行機の姿が見えている。ボーイング747、ジャンボ。昔、この飛行機を初めて見たときは「でっけえなあ」とただひたすらびっくりしたものだが、最近ではなんとも思わない。常識では、こんなでかいものが空を飛ぶはずがないと思うべきなのだろうが、そう思う前に「飛ぶ」という事実をいやというほど見せつけられてしまうのだから、疑問に思う余裕すらない。飛ぶものは飛ぶんだからしかたがない。しかし、常識で考えると、こんなものが飛ぶわけがないよなあ。
などとくだらないことを考えながらボンヤリと飛行機を見ていたら、ネットでぎゅうぎゅうにパックされた荷物が運ばれてきた。あの荷物のかたまりの中に僕たちの荷物もあるわけだ。荷台がグインと上にあがる特殊車両で荷物を飛行機の胴体の高さまで持ち上げ、貨物室の中へ荷物を押し込む。ところが、どういうわけか荷物は途中までしか入らない。何度やりなおしてもだめだ。いったん引っ張り出してからもう一度押し込んだり、横の方から押してみたりといろいろ試みている様子だが、どうしても機内に納まろうとしない。それを見兼ねた他の男が車の上にあがってきて一緒に荷物を押したりしている。まさか、その様子をじっと見ている者がいようとは向こうも思っていないだろうが、なにしろこちらは退屈なのだ。
「まったく、最近の若いもんはしょうがねえな。そっちの方をしっかり押しなって」
「ハイ」
「違うんだよ、そこを押すんじゃなくて、そっちの方をな、そうそう、ホレ、行くぞ」
「ハイ」
なんてことを言ってるんじゃないかな、なんてことを想像したりして。
結局、最終的には3人がかりで荷物をなんとか機内に押し込んで落着。貨物室のドアが閉まりロックされるところまで見届けると、僕たちから少し離れたところにいたグループから拍手が出た。その光景に注目しているのは自分たちだけかと思っていたら、どうやらみんなが注目して見ていたみたい。
近くにいた人が
「あのドア、途中で開かないだろうな」
ボソリ、とそう言った。数日後のハワイで飛行機の貨物室のドアが吹き飛ぶ事故が起こることになるのだが……。
で、成田発セブ経由マニラ行きのフィリピン航空437便。その飛行機の乗客はなんと日本人ばかりだった。以前利用したことのあるマニラ直行便だとフィリピン人の若い女性の姿がかなり目立ったのだけれど、セブ経由便になるとフィリピン人の姿はほとんど見られないらしい。僕の席のまわりにいるのは、日本人ばかり。しかも、どういうわけか年配のおじさんがやたらとたくさんいる。機内サービスのアルコールで顔を真っ赤にしてはフラフラと機内を歩き回り、やたらと嬉しそうにお互いに肩をたたきあってはダミ声をあげている。それから、初めて飛行機に乗ったとおぼしきおばさんたちもいる。はしゃいで写真を撮りまくっているグループがそれだ。
それに較べて若者たちはおとなしい。僕の左隣りの席では学生と思われる二人組の男がガイドブックを開きながら心もとなげに入国申請書の記入をしていた。
とにかく、右も左も前も後ろもみんな日本人。よくまあ、これだけの日本人がセブに行くものだ。いったい、何をしに行くというのだろう。なんて、自分たちのことは棚に上げておいて、思わず感心してしまう。おかげで、これから外国に行くという緊張感が全然わいてこない。飛行機の中はまだまだ日本が続いている。
しかし、間違いなく飛行機はフィリピンに向かっている。機内アナウンスは英語とタガログ語だ。だけど、僕を含めて乗客の大半は、タガログ語どころか英語だってろくに聞き取れないのだから、機長のアナウンスなどほとんど聞いていない。なにしろ、毛布をもらうのにブランケットという単語がなかなか思い出せずに冷や汗をかいてしまうような客(つまり僕)がいるのだ。英語のアナウンスがわかるはずがない。なあに、アナウンスなどわからなくたって、乗り過ごしたりはしないさ。
スチュワーデスにスコッチ&ソーダを頼み、エド・マクベインの『サディーが死んだとき』を読む。外国旅行に出るときにはいつも87分署シリーズを持っていくことにしている。エド・マクベインなら間違っても退屈するということはない。そして、隣りの我が妻はというと、サンミゲール・ビールを飲みながら、フィリピン航空のスチュワードの観賞。悔しいことになかなかの美形が揃っているのだ。
エド・マクベインを読み終えたところで、ちょうどセブに到着した。定刻通り。19時を指している時計を現地時間の18時に直す。
飛行機からタラップに出ると、いかにも南国らしい特有の香りを含んだ空気がねっとりとからみついてくる。どう表現したらいいだろう。少し甘ったるいような、それでいて刺激的なような、なんとなく不思議に懐かしい香りがする。フィリピンの匂いだ。イヤッホー! また来たんだ、フィリピン。僕の大好きな国にまた来たんだ。また、来れたんだ。
到着ロビーに入る。ここまで来るともうすっかりまわりはフィリピンだ。ついさっきまで大騒ぎしていたおじさん、おばさんたちの姿が、急に目立たなくなってしまう。入れ替わりに、フィリピンという国が圧倒的な存在感をもってドーンと迫ってくるからだ。
セブの空港は初めてだ。マニラあたりと比較すると、かなりローカルな雰囲気がする。到着したのが夜だったせいもあるだろうけど、なんとなく薄暗い体育館という感じ。とても、国際線の発着する空港だとは思えない。なんだか、無性に嬉しくなってしまう。
通関手続きをする窓口に向かう。木製の机がポンと置いてあるだけだ。僕のパスポートを見た係官が「フィリピンは初めてか?」と聞いてくる。これは2冊日のパスポートだけれど、フィリピンは6回目だというと彼はニコッと笑ってスタンプをポンと押してくれた。
「マラミン・サラマッポ(どうもありがとうございます)」
こういうときはタガログ語でていねいにお礼を言うにかぎる。
通関手続きを無事に終えて、次は機内預けの荷物の受け取り。もちろん、荷物がグルグルまわってくるターンテーブルなんてものはない。木製の細長い台があって、飛行機から運ばれてきた荷物がヨイショとばかりにその台の上に並べられていく。そこから自分の荷物を取るだけ。実に実にイ・ナ・カ。ローカルな空港なのです。近代的な機械の姿など全くないのだ。
2人分のシュノーケリングの道具や着替えのぎっしり詰まったダイビングバッグをカートに乗せて、出口へ向かう。例によって、ツアー名や個人名を書いたカードをかかげた迎えの人たちがそこで押しあいへしあいをしている。いったん出口を出てしまうと、人ゴミの中でゴチャゴチャにされてしまうにちがいない。ここはなんとか、出口の内側から自分を迎えに釆た人間を見つけなければ。
だけど、これがなかなか見つからない。向こうも自分が迎えに来た客を見つけようと必死で、次々と僕に向かって名前やツアー名を叫んでくるのだけれど、どれも僕じゃあない。他の日本人は、どうやら自分を迎えに来た人間を見つけたようで、どんどん空港の外に姿を消していってしまうけれど、ぜんぜん僕たちを迎えに来る人間がいないじゃないか。
なかなか自分の迎えが見つからず、やや不安になりかけたころに、僕の名前を呼ぶ声がようやく聞こえてきた。ビンゴ! オレ俺おれ、手を上げて合図をして、空港の外に出る。すっごい人ゴミ。どうしてこんなに人がたくさんいるんだ? エーイ、寄るな寄るな、俺の荷物に手をかけるんじゃねえ。自分の荷物は自分で持つぞ。こらこら、俺のうしろでギターなんか弾くな。チップなんかやらねえぞ!
僕たちを迎えに来ていたのは、ワンダー・レーンという現地の旅行会社のスタッフだった。僕たちが旅行を申し込んだ会社ではなくて、僕たちが旅行を申し込んだツーリスト・プラザという会社が現地で契約している旅行会社なのだろう。
迎えに来てくれたスタッフは2名だった。フレッドさんという40才ぐらいの男性と、ロルゥナさんという30才ぐらいの女性。挨拶するなり僕は、今すぐにここの事務所で航空券のリコンファームができるか、と尋ねた。ここでリコンファームを済ましてしまえば、あとで電話をかけなくてすむからだ。ところが、ロルゥナさんがあとでリコンファームをしてくれると言うので、大喜びでタクシーに乗り込んだ。よかった、これで英語の電話をかけないで済んだ。妻の前で恥をかかないで済んだ。それっ、ハドサン・ビーチ・リゾートへ一直線だ。(ちなみに、あとで知ったのだけれど、ハドサン・ビーチ・リゾートには電話がないので、リコンファームなどしたくてもできなかったのでした)
空港を離れると、すぐに道の両側にあった人家もまばらとなった。街灯がほとんどないので薄暗くてよくわからないのだけど、どうやら道のすぐかたわらまでジャングルが押し寄せてきているようだ。ひどく不気味な雰囲気だ。空港からちょっと離れただけでこんなにさびれてしまったら、ビーチは一体どんなところなのだろう。
タクシーはサイドカーを付けたオートバイと次々にすれちがいながら、舗装されていない細い道をガタガタと激しく揺れながら走り続ける。不安がじわりじわりとこみあげてくる。
僕たちが滞在することになっているハドサン・ビーチ・リゾートは、セブ島とは橋でつながれたマクタン島にある。タンブリ、コスタベリヤ、コーラルリーフといったセブを代表する高級リゾートが並んでいる島だ。そして、セブ空港があるのもマクタン島だ。小さな島なのだけれど、暗い夜道を走ったせいか、どこをどう走ったのか見当もつかなかった。
タクシーの中でロルゥナさんが簡単なレクチャーをしてくれる。英語とかたことの日本語での説明だ。まだガイドになったばかりということで、なかなか日本語がスムーズに出てこない。そのことをしきりに申し訳ながるのだけど、本来ならばこちらが英語で聞き取るべきなのだ、と僕は思う。だけど、きっとそういうことが通用しない日本人旅行者も大勢いるのだろうな、残念だけど。
スプリングのすっかりいかれたタクシーで凸凹道を走り続け、いい加減お尻が痛くなったころにハドサン・ビーチ・リゾートに到着した。ガイドブックによると、『ビーチは小ぢんまりしているが、目の覚めるような白砂が孤を描き、その美しさはマクタン一といっていいのがハドサン・ビーチ。他のリゾートと違って、リッチなリゾート気分は期待できないが、清潔でシンプルなコテージ(43室)は、ダブルで400〜500ペソの値段からするとお得』となっている。タンブリ、コスタベリヤといった設備が整いすぎているところよりも、素朴な雰囲気の残っているビーチの方がフィリピンらしさを満喫できるだろうというのが、このビーチを選んだ理由だった。
それだけに、リゾートの入口にガードマンの立っているゲートがあるのには驚いてしまった。ものものしい雰囲気に一瞬たじろいでしまう。ガードマンが警備しなければならないほど治安が悪いのだろうか。ふと、そんなことを考えて不安にもなってしまう。もっとフランクでオープンなリゾートを予想していただけに、ガードマンの存在は意外だった。あとになってみれば、入場料を払ってビーチに遊びに来る人たちがいるので、そのためのゲートにすぎないとわかったのだけれど、このときはなんとなく期待を裏切られてしまったような気がしてしまった。もっとも、政子の方は、途中の不気味な雰囲気にすっかり呑まれてしまっていたので、ガードマンの姿を見てほっとしたということだったが。
ゲートを通ってすぐの左側がフロント。ここでまずスケジュールの打ち合わせをする。こちらとしては、特に予定をたてずにその日その日の気分次第で行動したいのだが、ロルゥナさんの方としてはスケジュールを確定したいらしく、「あしたはどうしますか? アイランド・ホッピングに行きますか? ダイビングはいつ行きますか?」と聞いてくる。とりあえず、明日はビーチでのんびりとシュノーケリングでもやって、あさってはアイランド・ホッピングに行って、ダイビングはやるとしたらしあさってだけれど、やるかどうかはあとで決める、ということを拙い英語でなんとか伝える。あさってだのしあさってだのという英語など知らないので、これだけのことを伝えるだけでも四苦八苦してしまう。つくづく英語がペラペラしゃべれたらなあと思う。
トラベラーズチェックのドルをペソに両替してもらう。両替のレートは1ドルが20ペソ。リゾートでの両替は公式レートよりもやや低くなるということだが、それほど気にすることはあるまい。また、円からペソヘの両替ももちろんできるが、前回の旅行で残ったドルがあるので、まずはドルから使うことにする。
とりあえず100ドルを2,000ペソに替えてもらい、そこからアイランド・ホッピング代を支払う。アイランド・ホッピング代はひとり30ドルなのでふたりで1,200ペソ。残りの800ペソのうち、100ペソをチップ用に細かくしてもらう。リゾート内での食事は全てサインで済むので、とりあえずチップなどに使う小銭だけが手元にあれば大丈夫だろう。残りの円、トラベラーズ・チェックはパスポートなどと一緒にセーフティ・ボックスに預かってもらう。
フロントを出ると、左側がビーチで右側にコテージが並んでいる。僕たちのコテージは4−2。荷物を運んでくれた男性に10ペソのチップを渡す。チップにいくらぐらい出すのが適切なのかは知らないけれど、基本的に10ペソずつ出すことにしてしまう。ガイドブックにはチップは1ペソなんて出ているけれど、それはもう何年も前のことではないだろうか。まあ、5ペソでも充分だとは思ったが、少しでもリゾート内で楽しく過ごしたいので30円程度をけちるのはやめておくことにする。
コテージには驚くべきことになんとクーラーがついていて、グオングオンと騒がしい音をたてながら涼風を吹き出していた。以前、ニッパハットと呼ばれる竹と椰子の葉で作られたコテージを利用したときの経験で、クーラーなどなくても充分に涼しく寝られるということを知っていたので、まさかクーラーがあるなどとは考えてもみなかった。貧乏旅行をする客ばかりとは限らないので、さすがにニッパハットというわけにはいかなかったものとみえる。僕としては、ニッパハットの素朴さが好きなのだけど。
クーラーのスイッチは入れたままにして、さっそくレストランに向かう。再びガイドブックを見ると、『レストラン。ここは、海に突き出した形になっている吹き抜けタイプ。目の前には静かに波打つ真っ青の海が水平線まで見渡せるし、遠くに浮かぶサンタロサ島の島影もいいアクセントになっている。木造りのテーブルに、テーブルクロスをかけただけだが、ロケーションをじっくり楽しみたいときには逆に心地よいもの』とある。なるほど、海側のテーブルに座ると、実に気持ちがいい。すでに暗いので眺めを楽しむというわけにはいかないけれど、レストランの中を通りすぎていく潮風に吹かれながら飲むサンミゲールの味は最高だ。特に空腹は感じていなかったので、マンゴー、パパイヤ、バナナなどがミックスされたフルーツサラダをつまみながら、ビールを飲む。実に実に気分がいい。ビールをひとくち飲むたびに心地よい潮風がフワッと通り過ぎていくのがなんとも素敵だ。
レストランには、他には日本人の団体客が一組だけ来ていた。20人くらいで、どうやらダイビングで来ている団体のようだ。
そのグループのリーダーらしき男が実に実になれなれしい雰囲気で話しかけてきた。明日の朝からクルーザーでダイビングに出るのだけれど、一緒に来ませんかと言うのだ。
「ダイバーでしょ。さっきダイビングバッグを持ってたから。クルーザーでね、あそこに見える島の向こう側まで行って潜るんですよ。一緒に行きましょうよ。器材なら私の方で用意しますから」
しかし、クルーザーで回るのは一昨年に経験して充分に懲りている。気のあった仲間と一緒というのならいいのだろうけれど、そうでない場合にはクルーザーというのはあまりにも挟すぎる。閉じられた世界でずっと他人と一緒に過ごさなければならないので、あまりのんびり出来ないのだ。そのうえ船酔いでかなりつらい思いをするという悲惨な可能性もある。
「いや、遠慮しておきますよ。おととしね、クルーザーでルバング島の方をまわったんだけど、船酔いで苦しんだから」
丁重に御辞退申し上げる。
だが、彼はそのくらいで引き下がったりしなかった。
「そうですか。でも、このあたりのビーチはあまり良くないですよ。ダイナマイト・フィッシングをやっちゃったから。セブのダイビング・ポイントも、もうすでに過去のものですよ。どうです、みんなに言ってもらっちゃ困るけど、他のメンバーよりずっと安い料金にしておきますから」
どうもそのものの言い方に信用しきれないニュアンスが感じられ、いずれにせよビーチでのんびりと過ごしたかったので、重ねて御辞退申し上げる。
「さっき見てきたら、ここのビーチには海草がたくさんうちあげられて、あまりよくないですよ」
彼は最後にそう言うと、自分の団体の方へ戻っていった。あちらさんとしては親切のつもりなのだろうけれど、それこそ余計なお世話だ。
それにしても、ダイバーと見ればすべてお友達という態度で接してくるのはどこのダイビング・ショップでも一緒なのかな、と思って笑ってしまった。僕たち夫婦がダイビングのライセンスを取得したショップも、客はすべてお友達という感覚で商売をやっていて、そのあげくにトラブルをおこしたりもしていたのだけれど。
今回はそれほどダイビングに執着するつもりはなかったので、気が向かなければダイビングはしなくてもいいなと思っていた。いったん海の中に潜ってしまえばこれほど楽しいことはないのだが、ダイビングポイントまで時間をかけていったり、器材の準備をしたりといった、ダイビングに付随するもろもろのことがらがうっとうしくて、それならシュノーケリングだけでもいいなと思っていた。ようするに、怠惰なダイバーなのである。そして、ここで彼にダイビングに誘われたことによって、逆に今回はダイビングはやめておこうかな、という気になってしまった。
それに、ダイビングは金がかかるわりに当たり外れが大きい。大いに期待して潜って最低のポイントだったりすると、ショックはなおさら大きい。ましてや、新婚旅行で潜ったエルニドに匹敵する浮遊感覚を味わえるポイントがセブにあるとも思えない。やめておこうかな、ということになってしまうのである。
レストランを出てブラブラとリゾートの中を歩く。暗くて足下がよく見えないが、ビーチまで降りてみようかと話していると、「コンバンワ」と声をかけられた。二人のフィリピン人が近づいてくる。そして、こっちにプールがあるからと案内してくれる。
ガイドブックによると『プールは木々に囲まれてなかなかのムード。変形した四角形でまわりには白いチェアやテーブルが置かれているし、近くにプール・バーもある。真っ白のテーブルと鮮やかなコントラストを出している青色のプールの底には、HadSanという文字が描かれ、南国ムードを一層盛り上げている。ビーチ際にはないけれど、それだけに一瞬、高原のリゾートと思わせるような演出なのだ』とある。海に来てプールで泳ぐなどというもったいないことをする気はまったくないのだが、案内するというものを断わることもないので、のんびりとついていく。
プールはコテージのすぐ真裏にあった。なるほど、ガイドブックに書いてある通りのプールである。ただし、僕にはそのプールが特別に魅力的なものとは思えなかった。白く濁った汚い水がたまった小さなプールでしかない。とても、ここで泳ぐ人間がいるとは思えない。ガイドブックなどこの程度のものである。
特に面白いものもないのでコテージに戻ろうとすると、プールに案内してくれた男がウエストポーチから貝細工を取り出してきた。貝のネックレスを買わないかという。なんと、早くも土産物攻勢だ。あまりじゃけんにもしたくないが、真面目に相手をするのもバカバカしい。彼らにしてみれば大事な商売だろうが、貝のネックレスを買う気などさらさらない。
なんとか断わると、今度は「アシタ、ダイビング、行クカ?」と聞いてくる。明日はシュノーケリングだ、と答えると、ダイビングは行かないのか? シュノーケリングの道具は持っているか? としつこくつきまとう。とにかく、僕たちを相手になんらかの商売をしようというのだ。リゾートの入口にゲートはあっても、こういう人間の出入りは自由ということらしい。
貝細工はいらない、シュノーケリングの道具は持っている、ダイビングはやらない、そう言ってきっぱりと断わる。だが、それくらいであきらめたりはしない。じやあ、明日買ってくれ、約束だ、などと勝手に約束にしてしまう。このいい加減さとずうずうしさに免じて貝細工ぐらい買ってやろうかという気にもなるのだが、残念ながらデザインが気に入らないうえに値段も高い。約束なんかしていないよ、と言って彼らと別れる。だが、別れ間際に彼は僕に耳打ちしてこう言った。
「ハッパ、イラナイカ?」
ハッパ、つまり大麻のこと。まったく、ちょっと気を許すとすぐこれだ。せっかくの申し出ではあるが、丁重に御辞退申し上げ、コテージに戻った。
さて、朝だ。時間は8時50分。
僕は異様に重たいダイビング・バッグをガラゴロひきずりながら家を出た。セブだ。セブヘ行くのだ。今年度最大のイベント、セブ旅行へと出発する時がやってきたのだ。今は埼玉県の川口市なんてところをとぼとぼ歩いているけれど、夕方にはセブのビーチ・リゾートでのんびりと潮風にふかれるのだ。そして、サンミゲール・ビールでも飲みながら、ゆっくりと夕日でも眺めるのだ。うっとうしい日常のあれこれなどすべて忘れて、フィリピンの風にどっぶりと身をまかせてしまうのだ。
人によってはきっと、たかがセブ、なんて思うのかもしれない。村上春樹の『ダンスダンスダンス』風に言うならば、「だってセブでしょう? そんなの大磯に行くのとたいして変わらないわよ。カトマンズに行くわけじゃないもの」、あるいは「でもまあセブですから。ジンバブエに行くわけじゃないですから」というわけだ。だけど、僕たち夫婦にとっては大イベントなのだ。もう、今年最大のビッグイベントはこれで決定ってなもんなのだ。
結婚した年は新婚旅行でフィリピンのエルニド・リゾートに行き、ふたりでひたすらダイビングをした。もちろん、この旅行がこの年の最大のイベント。
次の年は夏にサイパンを計画していたのだが、どういうわけか直前になってルバンク島ダイビング・クルーズなどという企画に捕まってしまい、これに参加。ふたたびフィリピンヘ行き、これまたこの年最大のイベントとなった。
ルバング島ダイビング・クルーズで全財産を使い果たした翌年、つまり昨年はつつましやかに八丈島でダイビングにいそしんだ。残念ながらビッグとはいいがたいが、これまたこの年の最大のイベントだったのである。
そして、今年最大のビッグイベントが、このセブ旅行というわけだ。昨年はスケールダウンして八丈島で我慢したけれど、今年はもうめいっぱい楽しんでしまうのだ。待ってろよ、セブ。今年はお前を相手にギンギンに頑張ってしまうからな。ダイビング・バッグに詰め込まれたふたり分のシュノーケリング器材が活躍の時をいまや遅しとお待ちかねだぜ。
てなことを考えながらバス停に向かって田舎道を歩いていたわけだが、それにしても荷物が重い。自分ひとりの荷物ならばさほど重くもならないのだけれど、政子の着替えやら二人分のシュノーケリング器材やらなにやらかにやらいろいろさまざまなものが入っているので、とてつもなく重い荷物となってしまった。必要のないものは可能なかぎり置いてきたつもりなのだが、それでも二人分の荷物となるとかなりの分量となるものだ。
バスで南浦和駅まで出て、9時19分の南浦和始発の京浜東北線に乗る。かつて、ダイビング・バッグを持って通勤電車に乗り込み、悲惨な目にあったことがある。さすがに9時を過ぎればもう混んでいないだろうとは思ったが、念のために始発電車を狙った。なかなか細かいことにも気をつかって計画をたててあるのだ。
上野から京成スカイライナーに乗り換え。数日前に新宿の交通公社で買ってあったチケットよりも1本前のスカイライナーに間にあったので、窓口で列車を変えてもらって10時20分のスカイライナーに乗り込む。成田に着く時間が予定よりもかなり早くなってしまうが、遅れるよりはいい。特に昭和天皇の葬儀を控えて、成田でのチェックが厳しくなっているという話も聞くので、なるべく成田に早く着いた方が安心だ。
成田空港に到者。
コーヒーを飲んだり、空港内の色々な店をのぞいたりして時間をつぶし、11時55分、北ウイングにあるJAL団体カウンターで航空券を受け取る。成田からセブまでのチケット、26日に乗るセブからマニラまでのチケット、そして27日に乗るマニラから成田までのチケットの3枚がセットになっていることを確認する。
よし、大丈夫、と思ったのだけれど……ちょっと待ってよ。なに、このチケットに貼り付けてある紙。「あなたの帰国便の再確認は72時間前に必ず下記オフィスヘ連絡して下さい」だって。自分で帰りの航空券のリコンファームをしろっていうの? 冗談! 僕の英語力で、電話でリコンファームなんかできるわけがないじゃん。こういうことって、旅行会社でやってくれるんじゃないの? えーと、どうすればいいんだ。まず、ここに書いてある番号のところに電話をかけて、相手が出たら「リコンファーム・プリーズ」って言うんだよな。そして、この用紙に書いてある予約ナンバーを言えばいいんだけれど、そこで何かを言い返されたらどうすればいいの。きっと、電話じゃ聞き取れないだろうな。もしかして、予約されてません、なんてことを言われたら何て言えばいいんだろう。困った……。どうしよう。不安がじわ〜とこみあげてきちゃうじゃないか。
とりあえず、心配してもしょうがないことは忘れて、通関手続きを済ませる。はい、無事通過。そして、免税店。政子があれやこれやと香水の匂いを試すのをのんびりと椅子に座って待つ。それにしても、どうしてあれっぽっちの液体にあれだけの金を払う気になるのか。普段はスーパーのチラシを仔細に検討したあげく、「今日はスーパー・マルエツで卵の特売日ですからあなたも来てちょうだい」などと言っている人がである。本当に、女というものはわからない。
ようやく、免税店も突破。なんだか、テレビ・ゲームをやっているみたいだ。いくつもの難関があって、それをひとつひとつクリアしていかなければならないのだから。誰か、家を出てから飛行機に乗るまでをシュミレーションゲームにすると面白いんじゃないだろうか。途中で武器を手に入れると税関でひっかかったりして。
エックス線検査、金属探知機の連続攻撃をかわして搭乗ゲートヘ。
窓の外にこれから乗る飛行機の姿が見えている。ボーイング747、ジャンボ。昔、この飛行機を初めて見たときは「でっけえなあ」とただひたすらびっくりしたものだが、最近ではなんとも思わない。常識では、こんなでかいものが空を飛ぶはずがないと思うべきなのだろうが、そう思う前に「飛ぶ」という事実をいやというほど見せつけられてしまうのだから、疑問に思う余裕すらない。飛ぶものは飛ぶんだからしかたがない。しかし、常識で考えると、こんなものが飛ぶわけがないよなあ。
などとくだらないことを考えながらボンヤリと飛行機を見ていたら、ネットでぎゅうぎゅうにパックされた荷物が運ばれてきた。あの荷物のかたまりの中に僕たちの荷物もあるわけだ。荷台がグインと上にあがる特殊車両で荷物を飛行機の胴体の高さまで持ち上げ、貨物室の中へ荷物を押し込む。ところが、どういうわけか荷物は途中までしか入らない。何度やりなおしてもだめだ。いったん引っ張り出してからもう一度押し込んだり、横の方から押してみたりといろいろ試みている様子だが、どうしても機内に納まろうとしない。それを見兼ねた他の男が車の上にあがってきて一緒に荷物を押したりしている。まさか、その様子をじっと見ている者がいようとは向こうも思っていないだろうが、なにしろこちらは退屈なのだ。
「まったく、最近の若いもんはしょうがねえな。そっちの方をしっかり押しなって」
「ハイ」
「違うんだよ、そこを押すんじゃなくて、そっちの方をな、そうそう、ホレ、行くぞ」
「ハイ」
なんてことを言ってるんじゃないかな、なんてことを想像したりして。
結局、最終的には3人がかりで荷物をなんとか機内に押し込んで落着。貨物室のドアが閉まりロックされるところまで見届けると、僕たちから少し離れたところにいたグループから拍手が出た。その光景に注目しているのは自分たちだけかと思っていたら、どうやらみんなが注目して見ていたみたい。
近くにいた人が
「あのドア、途中で開かないだろうな」
ボソリ、とそう言った。数日後のハワイで飛行機の貨物室のドアが吹き飛ぶ事故が起こることになるのだが……。
で、成田発セブ経由マニラ行きのフィリピン航空437便。その飛行機の乗客はなんと日本人ばかりだった。以前利用したことのあるマニラ直行便だとフィリピン人の若い女性の姿がかなり目立ったのだけれど、セブ経由便になるとフィリピン人の姿はほとんど見られないらしい。僕の席のまわりにいるのは、日本人ばかり。しかも、どういうわけか年配のおじさんがやたらとたくさんいる。機内サービスのアルコールで顔を真っ赤にしてはフラフラと機内を歩き回り、やたらと嬉しそうにお互いに肩をたたきあってはダミ声をあげている。それから、初めて飛行機に乗ったとおぼしきおばさんたちもいる。はしゃいで写真を撮りまくっているグループがそれだ。
それに較べて若者たちはおとなしい。僕の左隣りの席では学生と思われる二人組の男がガイドブックを開きながら心もとなげに入国申請書の記入をしていた。
とにかく、右も左も前も後ろもみんな日本人。よくまあ、これだけの日本人がセブに行くものだ。いったい、何をしに行くというのだろう。なんて、自分たちのことは棚に上げておいて、思わず感心してしまう。おかげで、これから外国に行くという緊張感が全然わいてこない。飛行機の中はまだまだ日本が続いている。
しかし、間違いなく飛行機はフィリピンに向かっている。機内アナウンスは英語とタガログ語だ。だけど、僕を含めて乗客の大半は、タガログ語どころか英語だってろくに聞き取れないのだから、機長のアナウンスなどほとんど聞いていない。なにしろ、毛布をもらうのにブランケットという単語がなかなか思い出せずに冷や汗をかいてしまうような客(つまり僕)がいるのだ。英語のアナウンスがわかるはずがない。なあに、アナウンスなどわからなくたって、乗り過ごしたりはしないさ。
スチュワーデスにスコッチ&ソーダを頼み、エド・マクベインの『サディーが死んだとき』を読む。外国旅行に出るときにはいつも87分署シリーズを持っていくことにしている。エド・マクベインなら間違っても退屈するということはない。そして、隣りの我が妻はというと、サンミゲール・ビールを飲みながら、フィリピン航空のスチュワードの観賞。悔しいことになかなかの美形が揃っているのだ。
エド・マクベインを読み終えたところで、ちょうどセブに到着した。定刻通り。19時を指している時計を現地時間の18時に直す。
飛行機からタラップに出ると、いかにも南国らしい特有の香りを含んだ空気がねっとりとからみついてくる。どう表現したらいいだろう。少し甘ったるいような、それでいて刺激的なような、なんとなく不思議に懐かしい香りがする。フィリピンの匂いだ。イヤッホー! また来たんだ、フィリピン。僕の大好きな国にまた来たんだ。また、来れたんだ。
到着ロビーに入る。ここまで来るともうすっかりまわりはフィリピンだ。ついさっきまで大騒ぎしていたおじさん、おばさんたちの姿が、急に目立たなくなってしまう。入れ替わりに、フィリピンという国が圧倒的な存在感をもってドーンと迫ってくるからだ。
セブの空港は初めてだ。マニラあたりと比較すると、かなりローカルな雰囲気がする。到着したのが夜だったせいもあるだろうけど、なんとなく薄暗い体育館という感じ。とても、国際線の発着する空港だとは思えない。なんだか、無性に嬉しくなってしまう。
通関手続きをする窓口に向かう。木製の机がポンと置いてあるだけだ。僕のパスポートを見た係官が「フィリピンは初めてか?」と聞いてくる。これは2冊日のパスポートだけれど、フィリピンは6回目だというと彼はニコッと笑ってスタンプをポンと押してくれた。
「マラミン・サラマッポ(どうもありがとうございます)」
こういうときはタガログ語でていねいにお礼を言うにかぎる。
通関手続きを無事に終えて、次は機内預けの荷物の受け取り。もちろん、荷物がグルグルまわってくるターンテーブルなんてものはない。木製の細長い台があって、飛行機から運ばれてきた荷物がヨイショとばかりにその台の上に並べられていく。そこから自分の荷物を取るだけ。実に実にイ・ナ・カ。ローカルな空港なのです。近代的な機械の姿など全くないのだ。
2人分のシュノーケリングの道具や着替えのぎっしり詰まったダイビングバッグをカートに乗せて、出口へ向かう。例によって、ツアー名や個人名を書いたカードをかかげた迎えの人たちがそこで押しあいへしあいをしている。いったん出口を出てしまうと、人ゴミの中でゴチャゴチャにされてしまうにちがいない。ここはなんとか、出口の内側から自分を迎えに釆た人間を見つけなければ。
だけど、これがなかなか見つからない。向こうも自分が迎えに来た客を見つけようと必死で、次々と僕に向かって名前やツアー名を叫んでくるのだけれど、どれも僕じゃあない。他の日本人は、どうやら自分を迎えに来た人間を見つけたようで、どんどん空港の外に姿を消していってしまうけれど、ぜんぜん僕たちを迎えに来る人間がいないじゃないか。
なかなか自分の迎えが見つからず、やや不安になりかけたころに、僕の名前を呼ぶ声がようやく聞こえてきた。ビンゴ! オレ俺おれ、手を上げて合図をして、空港の外に出る。すっごい人ゴミ。どうしてこんなに人がたくさんいるんだ? エーイ、寄るな寄るな、俺の荷物に手をかけるんじゃねえ。自分の荷物は自分で持つぞ。こらこら、俺のうしろでギターなんか弾くな。チップなんかやらねえぞ!
僕たちを迎えに来ていたのは、ワンダー・レーンという現地の旅行会社のスタッフだった。僕たちが旅行を申し込んだ会社ではなくて、僕たちが旅行を申し込んだツーリスト・プラザという会社が現地で契約している旅行会社なのだろう。
迎えに来てくれたスタッフは2名だった。フレッドさんという40才ぐらいの男性と、ロルゥナさんという30才ぐらいの女性。挨拶するなり僕は、今すぐにここの事務所で航空券のリコンファームができるか、と尋ねた。ここでリコンファームを済ましてしまえば、あとで電話をかけなくてすむからだ。ところが、ロルゥナさんがあとでリコンファームをしてくれると言うので、大喜びでタクシーに乗り込んだ。よかった、これで英語の電話をかけないで済んだ。妻の前で恥をかかないで済んだ。それっ、ハドサン・ビーチ・リゾートへ一直線だ。(ちなみに、あとで知ったのだけれど、ハドサン・ビーチ・リゾートには電話がないので、リコンファームなどしたくてもできなかったのでした)
空港を離れると、すぐに道の両側にあった人家もまばらとなった。街灯がほとんどないので薄暗くてよくわからないのだけど、どうやら道のすぐかたわらまでジャングルが押し寄せてきているようだ。ひどく不気味な雰囲気だ。空港からちょっと離れただけでこんなにさびれてしまったら、ビーチは一体どんなところなのだろう。
タクシーはサイドカーを付けたオートバイと次々にすれちがいながら、舗装されていない細い道をガタガタと激しく揺れながら走り続ける。不安がじわりじわりとこみあげてくる。
僕たちが滞在することになっているハドサン・ビーチ・リゾートは、セブ島とは橋でつながれたマクタン島にある。タンブリ、コスタベリヤ、コーラルリーフといったセブを代表する高級リゾートが並んでいる島だ。そして、セブ空港があるのもマクタン島だ。小さな島なのだけれど、暗い夜道を走ったせいか、どこをどう走ったのか見当もつかなかった。
タクシーの中でロルゥナさんが簡単なレクチャーをしてくれる。英語とかたことの日本語での説明だ。まだガイドになったばかりということで、なかなか日本語がスムーズに出てこない。そのことをしきりに申し訳ながるのだけど、本来ならばこちらが英語で聞き取るべきなのだ、と僕は思う。だけど、きっとそういうことが通用しない日本人旅行者も大勢いるのだろうな、残念だけど。
スプリングのすっかりいかれたタクシーで凸凹道を走り続け、いい加減お尻が痛くなったころにハドサン・ビーチ・リゾートに到着した。ガイドブックによると、『ビーチは小ぢんまりしているが、目の覚めるような白砂が孤を描き、その美しさはマクタン一といっていいのがハドサン・ビーチ。他のリゾートと違って、リッチなリゾート気分は期待できないが、清潔でシンプルなコテージ(43室)は、ダブルで400〜500ペソの値段からするとお得』となっている。タンブリ、コスタベリヤといった設備が整いすぎているところよりも、素朴な雰囲気の残っているビーチの方がフィリピンらしさを満喫できるだろうというのが、このビーチを選んだ理由だった。
それだけに、リゾートの入口にガードマンの立っているゲートがあるのには驚いてしまった。ものものしい雰囲気に一瞬たじろいでしまう。ガードマンが警備しなければならないほど治安が悪いのだろうか。ふと、そんなことを考えて不安にもなってしまう。もっとフランクでオープンなリゾートを予想していただけに、ガードマンの存在は意外だった。あとになってみれば、入場料を払ってビーチに遊びに来る人たちがいるので、そのためのゲートにすぎないとわかったのだけれど、このときはなんとなく期待を裏切られてしまったような気がしてしまった。もっとも、政子の方は、途中の不気味な雰囲気にすっかり呑まれてしまっていたので、ガードマンの姿を見てほっとしたということだったが。
ゲートを通ってすぐの左側がフロント。ここでまずスケジュールの打ち合わせをする。こちらとしては、特に予定をたてずにその日その日の気分次第で行動したいのだが、ロルゥナさんの方としてはスケジュールを確定したいらしく、「あしたはどうしますか? アイランド・ホッピングに行きますか? ダイビングはいつ行きますか?」と聞いてくる。とりあえず、明日はビーチでのんびりとシュノーケリングでもやって、あさってはアイランド・ホッピングに行って、ダイビングはやるとしたらしあさってだけれど、やるかどうかはあとで決める、ということを拙い英語でなんとか伝える。あさってだのしあさってだのという英語など知らないので、これだけのことを伝えるだけでも四苦八苦してしまう。つくづく英語がペラペラしゃべれたらなあと思う。
トラベラーズチェックのドルをペソに両替してもらう。両替のレートは1ドルが20ペソ。リゾートでの両替は公式レートよりもやや低くなるということだが、それほど気にすることはあるまい。また、円からペソヘの両替ももちろんできるが、前回の旅行で残ったドルがあるので、まずはドルから使うことにする。
とりあえず100ドルを2,000ペソに替えてもらい、そこからアイランド・ホッピング代を支払う。アイランド・ホッピング代はひとり30ドルなのでふたりで1,200ペソ。残りの800ペソのうち、100ペソをチップ用に細かくしてもらう。リゾート内での食事は全てサインで済むので、とりあえずチップなどに使う小銭だけが手元にあれば大丈夫だろう。残りの円、トラベラーズ・チェックはパスポートなどと一緒にセーフティ・ボックスに預かってもらう。
フロントを出ると、左側がビーチで右側にコテージが並んでいる。僕たちのコテージは4−2。荷物を運んでくれた男性に10ペソのチップを渡す。チップにいくらぐらい出すのが適切なのかは知らないけれど、基本的に10ペソずつ出すことにしてしまう。ガイドブックにはチップは1ペソなんて出ているけれど、それはもう何年も前のことではないだろうか。まあ、5ペソでも充分だとは思ったが、少しでもリゾート内で楽しく過ごしたいので30円程度をけちるのはやめておくことにする。
コテージには驚くべきことになんとクーラーがついていて、グオングオンと騒がしい音をたてながら涼風を吹き出していた。以前、ニッパハットと呼ばれる竹と椰子の葉で作られたコテージを利用したときの経験で、クーラーなどなくても充分に涼しく寝られるということを知っていたので、まさかクーラーがあるなどとは考えてもみなかった。貧乏旅行をする客ばかりとは限らないので、さすがにニッパハットというわけにはいかなかったものとみえる。僕としては、ニッパハットの素朴さが好きなのだけど。
クーラーのスイッチは入れたままにして、さっそくレストランに向かう。再びガイドブックを見ると、『レストラン。ここは、海に突き出した形になっている吹き抜けタイプ。目の前には静かに波打つ真っ青の海が水平線まで見渡せるし、遠くに浮かぶサンタロサ島の島影もいいアクセントになっている。木造りのテーブルに、テーブルクロスをかけただけだが、ロケーションをじっくり楽しみたいときには逆に心地よいもの』とある。なるほど、海側のテーブルに座ると、実に気持ちがいい。すでに暗いので眺めを楽しむというわけにはいかないけれど、レストランの中を通りすぎていく潮風に吹かれながら飲むサンミゲールの味は最高だ。特に空腹は感じていなかったので、マンゴー、パパイヤ、バナナなどがミックスされたフルーツサラダをつまみながら、ビールを飲む。実に実に気分がいい。ビールをひとくち飲むたびに心地よい潮風がフワッと通り過ぎていくのがなんとも素敵だ。
レストランには、他には日本人の団体客が一組だけ来ていた。20人くらいで、どうやらダイビングで来ている団体のようだ。
そのグループのリーダーらしき男が実に実になれなれしい雰囲気で話しかけてきた。明日の朝からクルーザーでダイビングに出るのだけれど、一緒に来ませんかと言うのだ。
「ダイバーでしょ。さっきダイビングバッグを持ってたから。クルーザーでね、あそこに見える島の向こう側まで行って潜るんですよ。一緒に行きましょうよ。器材なら私の方で用意しますから」
しかし、クルーザーで回るのは一昨年に経験して充分に懲りている。気のあった仲間と一緒というのならいいのだろうけれど、そうでない場合にはクルーザーというのはあまりにも挟すぎる。閉じられた世界でずっと他人と一緒に過ごさなければならないので、あまりのんびり出来ないのだ。そのうえ船酔いでかなりつらい思いをするという悲惨な可能性もある。
「いや、遠慮しておきますよ。おととしね、クルーザーでルバング島の方をまわったんだけど、船酔いで苦しんだから」
丁重に御辞退申し上げる。
だが、彼はそのくらいで引き下がったりしなかった。
「そうですか。でも、このあたりのビーチはあまり良くないですよ。ダイナマイト・フィッシングをやっちゃったから。セブのダイビング・ポイントも、もうすでに過去のものですよ。どうです、みんなに言ってもらっちゃ困るけど、他のメンバーよりずっと安い料金にしておきますから」
どうもそのものの言い方に信用しきれないニュアンスが感じられ、いずれにせよビーチでのんびりと過ごしたかったので、重ねて御辞退申し上げる。
「さっき見てきたら、ここのビーチには海草がたくさんうちあげられて、あまりよくないですよ」
彼は最後にそう言うと、自分の団体の方へ戻っていった。あちらさんとしては親切のつもりなのだろうけれど、それこそ余計なお世話だ。
それにしても、ダイバーと見ればすべてお友達という態度で接してくるのはどこのダイビング・ショップでも一緒なのかな、と思って笑ってしまった。僕たち夫婦がダイビングのライセンスを取得したショップも、客はすべてお友達という感覚で商売をやっていて、そのあげくにトラブルをおこしたりもしていたのだけれど。
今回はそれほどダイビングに執着するつもりはなかったので、気が向かなければダイビングはしなくてもいいなと思っていた。いったん海の中に潜ってしまえばこれほど楽しいことはないのだが、ダイビングポイントまで時間をかけていったり、器材の準備をしたりといった、ダイビングに付随するもろもろのことがらがうっとうしくて、それならシュノーケリングだけでもいいなと思っていた。ようするに、怠惰なダイバーなのである。そして、ここで彼にダイビングに誘われたことによって、逆に今回はダイビングはやめておこうかな、という気になってしまった。
それに、ダイビングは金がかかるわりに当たり外れが大きい。大いに期待して潜って最低のポイントだったりすると、ショックはなおさら大きい。ましてや、新婚旅行で潜ったエルニドに匹敵する浮遊感覚を味わえるポイントがセブにあるとも思えない。やめておこうかな、ということになってしまうのである。
レストランを出てブラブラとリゾートの中を歩く。暗くて足下がよく見えないが、ビーチまで降りてみようかと話していると、「コンバンワ」と声をかけられた。二人のフィリピン人が近づいてくる。そして、こっちにプールがあるからと案内してくれる。
ガイドブックによると『プールは木々に囲まれてなかなかのムード。変形した四角形でまわりには白いチェアやテーブルが置かれているし、近くにプール・バーもある。真っ白のテーブルと鮮やかなコントラストを出している青色のプールの底には、HadSanという文字が描かれ、南国ムードを一層盛り上げている。ビーチ際にはないけれど、それだけに一瞬、高原のリゾートと思わせるような演出なのだ』とある。海に来てプールで泳ぐなどというもったいないことをする気はまったくないのだが、案内するというものを断わることもないので、のんびりとついていく。
プールはコテージのすぐ真裏にあった。なるほど、ガイドブックに書いてある通りのプールである。ただし、僕にはそのプールが特別に魅力的なものとは思えなかった。白く濁った汚い水がたまった小さなプールでしかない。とても、ここで泳ぐ人間がいるとは思えない。ガイドブックなどこの程度のものである。
特に面白いものもないのでコテージに戻ろうとすると、プールに案内してくれた男がウエストポーチから貝細工を取り出してきた。貝のネックレスを買わないかという。なんと、早くも土産物攻勢だ。あまりじゃけんにもしたくないが、真面目に相手をするのもバカバカしい。彼らにしてみれば大事な商売だろうが、貝のネックレスを買う気などさらさらない。
なんとか断わると、今度は「アシタ、ダイビング、行クカ?」と聞いてくる。明日はシュノーケリングだ、と答えると、ダイビングは行かないのか? シュノーケリングの道具は持っているか? としつこくつきまとう。とにかく、僕たちを相手になんらかの商売をしようというのだ。リゾートの入口にゲートはあっても、こういう人間の出入りは自由ということらしい。
貝細工はいらない、シュノーケリングの道具は持っている、ダイビングはやらない、そう言ってきっぱりと断わる。だが、それくらいであきらめたりはしない。じやあ、明日買ってくれ、約束だ、などと勝手に約束にしてしまう。このいい加減さとずうずうしさに免じて貝細工ぐらい買ってやろうかという気にもなるのだが、残念ながらデザインが気に入らないうえに値段も高い。約束なんかしていないよ、と言って彼らと別れる。だが、別れ間際に彼は僕に耳打ちしてこう言った。
「ハッパ、イラナイカ?」
ハッパ、つまり大麻のこと。まったく、ちょっと気を許すとすぐこれだ。せっかくの申し出ではあるが、丁重に御辞退申し上げ、コテージに戻った。
2日目へ 戻る
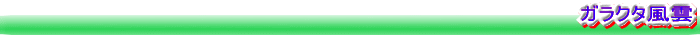
|