|
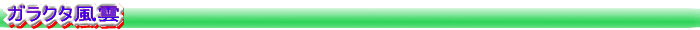
朝食はセブの潮風(6日目)
2月27日(月)
朝、8時。目が覚めると雨が降っていた。ホテルの窓から見下ろすマニラの街はすっかり雨に包まれている。最後の日だというのに、あいにくの天気になってしまった。
僕たちはまず、ホテルのレストランで食事をとった。バイキング形式の食事。まあまあの味だが、相変わらず体調の方が順調とは言い難く、食欲がない。せめて、ヨーグルトだけでも食べようと思ったが、マグノリアのヨーグルトが絶妙に不味く、見事に二人ともヨーグルトを残してしまった。
近くのテーブルには、二組のカップルがいた。男性は二人とも日本人、そして女性は二人ともフィリピン人。マニラに来ると、必ず目にする光景だ。男性の方は仕事で来ている様子で、アラブがどうのこうのという話をしている。そして、女性の方は女性どうしでタガログ語の会話をしている。こういうカップルを目にすると、全てが売買春というイメージにつながってしまうのだが、はたして事実はどうなのだろうか、なんてことが気になってしまう。
今日はキアポなどへ土産物を買いに行く予定になっているのだが、12時にはホテルに戻ってこなければならない。飛行機の時間が2時25分なのだ。あまり時間に余裕はない。速攻で行動を開始しなければ……。だが、その前にすることがある。
僕たちにはマニラに小さなガール・フレンドがいた。ルバング島ダイビング・クルーズに参加した時に、ショッピングに行ったデパートの入口のところで宝くじを売っていた女の子。可愛らしい男の子だなと思って一緒に写真を撮ったりして仲良くなったのだが、その写真を送るために住所と名前を聞いたらなんと女の子だったというのが知り合ったきっかけ。その後、何度もクリスマス・カードを交換したりしている。
今回はマニラの滞在時間が短いので会うことができないが、せめてプレゼントぐらいしようと思って、日本からサンリオの缶ペンセットを持ってきていた。彼女の誕生日にプレゼントとして日本から郵送したのが届かなかったらしいので、今度はマニラ市内から郵送しようというわけだ。
で、ホテルのフロントに行くと、そのすぐ横にある小さな土産物の店で切手を買ってきてくれと言われる。開店の9時までちょっと時間があったので、10分ほど時間をつぶしてから切手を買いに行く。すると今度は、重量オーバーなので郵便局に行かないとだめだと言われる。ホテルのフロントで郵便局の行き方を聞くと、こちらはタクシーを使わなければならないと言う。どうせショッピングで外へでかけるつもりだったのでかまわないけれど、いやはや、小包ひとつ送るのも大仕事だ。
僕たちはホテルの前からタクシーに乗って、小雨の降るマニラの街中へとでかけていった。
郵便局はホテルからタクシーで5分ぐらいのところにあった。石造りの古そうな建物だ。タクシーには待ってもらうことにして、郵便局の中へ。
何も分からないので、とにかく手近な窓口へ行き、小包を差し出した。係員に中身を聞かれて、缶ペンケースやシャープペンシルが入っていることを説明する。誕生日プレゼントだということまで付け加える。これで簡単に送れるだろうと思っていると、何かよく分からないことを聞いてくる。よく聞くと「レジスターで送るのかどうなのか」というようなことを尋ねているのだが、肝心のレジスターという単語の意味が分からない。速達とか書留とかいう意味なのだろうけれど、分かるわけがない。オタオタしていると、何だかよく分からないうちに隣の窓口ヘまわされてしまった。
隣の窓口でもレジスターがどうのこうのと聞かれるが、とにかく「オレ分かんねえよぅ」ということを全身で表現して、なんとか小包を押し付け郵送料を支払う。よく分からんが、何とか発送できたのではないだろうか。
タクシーに戻って今度はキアポのキンタ・マーケットに行ってもらう。
キアポというのはキアポ教会、サンタクルス教会を中心に発展した庶民の街である。マビニ通りを中心とするエルミタ地区が観光客のための歓楽街、アヤラ通りを中心とするマカティ地区がオフィスの立ち並ぶビジネス地区であるとするならば、キアポは文字通り地元の人たちのための街だ。日曜日には教会で神様に祈り、そしてショッピングを楽しむ人たちでごったがえす。あまりにも雑然としていて、初めて来た者は圧倒されてしまうかもしれないが、僕の大好きな街だ。
ただし、交通公社のポケット・ガイドには「大変な混雑だし、迷路のような小路地や薄暗いビルなども多く、安心して旅行者が徒歩観光できるようなところではなさそう。車窓からの見物にとどめたい」などと書いてある。文章を読むかぎりではキアポを歩いたことのない人が書いているらしいが、こういうガイド・ブックはとことんバカにして、自分の好きな街を好きなように歩こう。マニラで暮らすごく普通の人を見ようと思ったら、キアポを歩いてみるにかぎる。車の窓から街を見て何が分かるものか。
タクシーがパッシグ川を越える。この川に沿って少しさかのぼればあの有名なマラカニャン宮殿があるのだが、このあたりの雑然とした雰囲気からは想像もつかない。また、パッシグ川は(真偽のほどはさだかではないが)ギャングなどが殺した死体を捨てるのに利用している川であるという話もあり、こちらの方はやや分かるような気もする。そのパッシグ川にかかる橋の下に民芸品を扱う店が軒を連ねている。ここが僕たちの第一の目的地、キンタ・マーケットだ。
ここでタクシーをおりると、若い運転手が「この辺はスリが多いから気をつけるように」と注意してくれた。さいわいなことにフィリピンでそういう被害を受けたことはないが、なにせ勝手の違う異国である、注意するに越したことはない。
ここでは政子がバッグをいくつも貰った。例によって必殺のディスカウント攻撃の登場だ。気に入ったバッグがあるとそれを手にとってじっくりとチェックして、それからおもむろに値段の交渉に入る。
「マカノ?」
「ツウ・サーティ」
「ディスカウント?」
「ツウ・フィフティーン」
「ディスカウント?」
以前ならここでさらに値段を下げるか、それとももうここまでしか下げられないと言うか、その辺がはっきりしていたのだが、最近ではやり方がかわってきたようだ。この時点ですぐに「いくらで買いたいのか、そっちから値段を言ってよ」と言ってくるようになっていた。どこの店に行っても同じなので、この辺りの全部の店が一致団結して客との値段交渉のやり方を変えてしまったらしい。
「ワン・フィフティ」
横から口を出してドーンと安い値段を言ってみる。そこからまたやりとりがあって、最終的には180ペソなり190ペソといった値段に落ち着いた。いかにもフィリピンらしい、竹を編んで作ったバッグ。安いわりに意外と見た目がよくお洒落な感じもする。他に刺繍のしてある布製のバッグも買う。
それにしても、前に来た時にもここで同じようなバッグをいくつも買っている。土産物に配ってもいるのだろうけれど、どうしてそんなにたくさんバッグを買うのか、男の僕にはどうにも理解のできないことだ。
キアポでの買い物が終ると、次の目的地、マラテ地区のハリソン・プラザに向かうことにする。キアポからはエルミタ地区を挟んだ反対側にある総合ショッピング・センターで、ここにはシューマー卜やルスタンといった百貨店がある。
そこでタクシーをつかまえようと大通りに出たのだが、どういうわけかタクシーがなかなか通りかからない。そこで、ジプニーを利用することにする。
ジプニーというのはジープを改造した乗り合いバスのようなもので、マニラで最もポピュラーな交通機関だ。日本のバスとは異なり、好きなところで乗れて好きなところで降りることができる。しかも、料金がやたらと安い。2ペソもあれば、マニラのどこにでも行ける。ところが、残念なことに路線が複雑で、どのジプニーに乗ればどこに行けるのかがなかなか分からない。土地勘のない旅行者には、使いこなすのはちょいと難しい。
しかし、タクシーが来なければジプニーに乗るしかないのだ。何が何でも乗るのだ。僕たちはケソン大通りにあるジプニー乗り場で、通りかかるジプニーの運転手に片端から「ハリソン・プラザ!」と声をかけた。だが、世間は無情だ。運転手に声を掛けている間に、手慣れた連中がドンドンとジプニーに飛び乗って、あっと言う間に満員になってしまうのだ。そして、ズンズンと走り去ってしまうのだ。しかも、天気は雨。だんだん悲壮感すら漂ってきてしまう。
雨に濡れた髪を振り乱し、悪戦苦闘のあげくにようやくジプニーに乗り込む。
ジプニーに乗り込むと、みんながギュウギュウに席を詰めて座らせてくれる。ジプニーに乗っていちばん嬉しい瞬間だ。どんなに混んでいるときでも、必ずお互いに譲り合って座らせてくれる。フィリピンの人々の素晴らしい習慣だ。
日本の通勤電車の中で平気で大股を広げて座っている輩を見るたびに、つい彼らのことを思い出してしまう。お互いに譲り合ってお互いに楽をしようとする。彼らにとっては当り前のことなのだ。その当り前のことが、とてつもなく嬉しく感じてしまうのだから、日本というのはホントに貧しい国なのだと思ってしまう。
「バヤド。ダラワン・サ・ハリソン・プラザ(ハリソン・プラザまで二人)」
運転手にそう声をかけて、5ペソを手渡す。運転手は前を向いて運転を続けたまま器用にその金を受け取り、やはり運転を続けたまま2ペソ50センタボのお釣りを返してきた。ひとり1ペソ25センタボということらしい。物価が値上がりしているわりに、ジプニーの料金はあまり上がっていないようだ。
途中で他の客が降りて車内がすいてきたところで、「ハリソン・プラザについたら教えてくれる?」と運転手に頼み込む。「分かってるよ」というポーズが返ってきてひと安心。のんびりと窓の外の風景を楽しむ。ジプニーはリサール公園の脇を通りすぎる。初めてひとりでマニラに来たとき、この公園のベンチで昼寝をしたっけ。そんなことがふいに思い出されておかしくなる。若かったのだなあ。
見慣れた町並が目の前を通り過ぎていく。そして、ハリソン・プラザ。ふたりでジプニーを飛び降りて歩き出す。ふと、いま乗っていたジプニーの方を振り返ると、運転手がこっちを見ている。手を振ると、ニッコリ笑って手を振り返してくれた。助手席に乗っていた客も笑顔で手を振ってくれる。なんだか、嬉しくなってしまう。
ハリソン・プラザでは、まずシューマート・デパートの2階に直行した。ここにはかなり広い靴売り場がある。日本のデパートではちょっと考えられないほど広いフロアを靴売り場にあてている。川口のイメルダの異名を持つ政子がここを素通りできるわけがない。前にここで買った靴がいたく気に入っているだけになおさらだ。しかし、残念なことに残り時間が少ない。ゆっくりと靴を選んでいる余裕などありはしないのだ。政子は10分間だけという過酷な条件で靴を捜し始める。だが、10分もたたないうちに「欲しい靴はない」、きっぱりと言い切って靴選びを終了した。
さて、次なる目的は椰子酒だ。日本にいる知人にぜひともフィリピンの椰子酒を買って帰ろうと決めていたのだ。本当はシューマー卜の1楷でフィリピンのアイドル歌手のレコードなんかも買いたかったのだけれど、貴重な時間はとりあえず椰子酒にまわさなければならないとあきらめ、ルスタン・デパートに移動する。
ルスタンの入口でキアポで買った荷物を預ける。フィリピンのデパートでは、バッグや紙袋などは入口で預けなければならない。最初はこの習慣にとまどったが、万引き防止のためなのだろう。
さっそく1階にあるリカーショップへ。だが、目指す椰子酒はここにはなかった。ヨーロッパから輸入したという椰子酒があることはあったのだが、僕が買いたいのはフィリピンで造られている「LAMBANOG」という銘柄の由緒正しき椰子酒なのだ。紅毛碧眼の毛唐の造った椰子酒など飲めるものか。う−ん、前の時にはここで買ったのだがなあ。
ここで悔しがっていると、若くて可愛い女子店員が僕のウエスト・ポーチを見て
「どこでダイビングしてきたの?」
と話しかけてきた。僕のウエスト・ポーチはダイビング・ショップで買ったものなので、知っている人が見れば一目でダイビングをやるということがばれてしまうのだ。
「セブで」
「あら、私、日本人の友達とアルガオ・ビーチにダイビングに行ったことがあるのよ」
「へえ、君もダイビングをするの?」
「ううん、私はついていっただけ」
なんて会話をかわしてしまう。ホント、気さくに声をかけてくるんだから。嬉しくなってしまう。ま、それはともかくとして、椰子酒だ。
ルスタンを出て、デパートの前にいたガードマンに「椰子酒の買えそうな店を知らないか」と聞いてみる。するとそのガードマンは「ルスタンの中にあるリカー・ショップに行け」と言う。いやいや、今そこに行ってきたばかりなのだよ。そのことを説明すると、彼は別のガードマンと相談を始め、さらにタクシーをとめてその運転手とも相談し、ピスタン・ピリピノに行けばあるかもしれない、という結論に達した。ピスタン・ピリピノというのは観光客を相手にフィリピンの民芸品などを売る店がギッシリと並んでいる場所である。とてもじゃないが椰子酒を売っているとは思えない。僕が買いたい椰子酒は一般の観光客が土産に買うようなしろものではないのだ。フィリピンの貧乏な連中がてっとりばやく酔っ払うために飲むような酒なのだ。しかし、とりあえずは地元の人間の意見を尊重してタクシーに乗り込むことにする。
ところが、タクシーが走り出してすぐに、「自分の知っている店に行けば椰子酒がある」と運転手が言い出した。半信半疑のままそれに従うと、連れていかれたのは僕が初めてマニラに行った時に団体で連れ込まれた土産物の店。日本から来る団体観光客を相手にいい値段でつまらないものを売りつけているような店だ。間違ってもこんな店に椰子酒があるわけがない。どうやら、僕たち二人はいいカモだと思われてしまったらしい。この店で買い物をすれば、このタクシーの運転手になんらかのバックペイが支払われるのだろう。
僕はタクシーを店の前に待たせたまま店内に入り込み、「オ客サン、ネックレス、ドウ? 安イデスヨ」とまとわりつく売り子に椰子酒のないことを確認すると即座にタクシーまでとってかえし、運転手に向かって「ワラッ!(ないよっ)」とひとこと叫んだ。そして、再びタクシーに乗り込み、僕の欲しがっている椰子酒は決して土産物屋にはないことを口を酸っぱくして運転手に説明し、そのうえで売っている店を知らないかと聞いた。
だが、彼には心当たりはないという。信じられない。僕は今まで椰子酒はフィリピンで比較的ポピュラーな酒だと思っていたのだが、どうやらそういうものでもないらしい。
椰子酒は手に入らなかったが、時間もなくなってきたので僕たちはそのままホテルに戻ることにした。
シラヒス・ホテルに着き、タクシーの料金を聞くと、運転手は椰子酒が見つからなかったのだから金は取れないとしょんぼりした口調で言う。乗る時にはピスタン・ピリピノまで20ペソという約束で乗ったのでタクシーのメーターは倒していなかったのだ。土産物屋に連れ込まれた時にかなりきつい口調で文句を言ったのでなんだか可哀想になってしまい、30ペソ渡してタクシーを降りた。ピスタン・ピリピノに行くよりも距離を走ったのだからそのくらいは渡してもいいだろう。
結局、椰子酒は手に入らないまま部屋に戻った。短時間のうちにひどく疲れてしまった。よく考えてみると、朝食を食べに部屋を出てから3時間ちょっとしかたっていないのだ。
11時50分。荷物をまとめて一息ついたところへロビーから電話が入った。ガイドが下で待っているというので、重いバッグをかついでロビーまで降りる。本当ならグワラグワラと引きずるところなのだが、あまりの重さにバッグの底に付いているキャスターがバッグの底を突き抜けて壊れてしまっていた。冗談ごとではない重さなのだ。
ロビーでチェックアウトを済ませながら、昨夜と同じガイドに、椰子酒を買いたい旨を伝える。ルスタンまで行ったのだが買えなかったことなども付け加えると、分かってるんだか分かってないんだか、なんとも気のなさそうにうなずいた。セブのロルゥナさんに比べて、なんとも無愛想で面白味に欠ける男だ。
車に乗り込むと、この男が運転手に「この日本人、椰子酒が欲しいんだとさ」というようなことを告げる。もちろんタガログ語だが、かたことの単語や口調からそのくらいのニュアンスは伝わってくる。むこうは日本人の客がタガログ語をひとことでも理解できるとは思っていないのだろうが、実に不愉快な男だ。
ともあれ、空港に向かう途中で2軒のリカー・ショッブに寄ってもらった。だが、ついに椰子酒に出会うことはできなかった。前の時には実に簡単に買うことができたのだが、いったいどこに行ってしまったのだろう。悔しいが仕方がない。あきらめて空港に向かうことにする。
結局、政子は靴、僕は椰子酒というマニラにおける2大目標をついに達成しそこねてしまった。
空港に到着。
車から降ろした荷物を自分でかついで空港に入る。BLTBツアーズのスタッフは誰も荷物運びを手伝う気はないようだ。ま、こちらとしてもキャスターの壊れたバッグをズルズルと引きずられるのもまっぴらなので、自分でかついだ方がいいのだけれども、それでもやはり癇にさわる。
そのスタッフは空港の入口まででさっさと帰ってしまった。こちらの姿が見えなくなるまでずっと手を振っていてくれたロルゥナさんとは雲泥の差だ。今までの経験からすると、空港の中まで一緒に入ってきてこちらの世話をしてくれるスタッフが必ず一人はいたものだが、最近ではそういったサービスはこちらの払った金に含まれていないらしい。それに、空港使用料の200ペソも当然、旅行会社が負担するものと思っていたのだが、それも旅行代金には含まれていなかったらしい。今まで利用した旅行会社は必ずここで空港使用料を手渡してくれたものだが、今回はそれがなかった。たまたま手元に多少のペソが残っていたからいいようなものの、それがなかったらここでまたてんやわんやの大騒動を繰り広げなければならなくなるところだ。つくづくと不愉快になる。次に来るときにはマニラでのスタッフを確認したうえで、BLTBだけは避けてやる、とかたく決意してしまう。
荷物のチェックを終え、PALのカウンターで搭乗手続きを済ませ、荷物をそこで預けてしまう。身軽になって次は出国手続き。
かつて、この出国カウンターに向かう入口のところで袖の下を要求されたことがある。機内持ち込みの荷物は一人ひとつまでと決まっているのだが、僕はカバンをふたつ肩から下げていて、それを理由にこちらから金をせびり取ろうとしたのだ。だが、今回はそんなこともなく無事に通過。
ちなみに、そのような男に対しては、ニッコリ笑って「そんなこと言ってもダメだよ」という感じに手を振れば、それで済む。あまり大袈裟に考える必要はない。
出国手続きを無事に済ませると、政子は一直線に免税店へ。義弟に頼まれた酒や母への土産の香水、会社への土産のチョコレートなどを一気に買いまくる。ペソ、ドル、円の3種の通貨を同時に使用して、円以外の金をきれいに使い切る。見事としかいいようがない。しかし、同時に3種もの通貨を使用したので、自分がいくら払ったのかまるで分からなくなってしまい、安い買い物をしたのかどうかすら判断がつかなくなってしまう。しばらく、ドルでいくら払って、ペソでいくら払って、円がいくらだったから、全部を円に換算すると……などとしきりに考えていたが、ついに結論は出なかったようだ。
その間、僕の方はのんびりと荷物の番。時々ウェイトレスが「オ客サン、飲ミ物ハァ?」とやって来るが、「イヤイヤ、結構デェス」と断わり、頭上の表示が「NOW
BOADING」になるのを待つ。だが、なかなか搭乗中の表示に変わらない。時間が迫ってきたので不安になり、出発ゲートへと進むことにする。
税関の手荷物のチェックで係官が「ピストル、アル?」と冗談を言いながらボディチェックをする。しかめつらしい表情で「オレ、つまんねえ仕事してるよな」といわんばかりに義務的なチェックをするだけの日本に比べて、人間味があっていい。どうせボディチェックなんてお互いにつまらないんだから、せめて冗談のひとつも……と思っても日本じゃ無理か。
それから、これは以前にはなかったことなのだが、サイフの中をチェックされた。ペソの持ち出し金額のチェックだ。ペソの外国への持ち出し金額は以前から制限されてはいたけれど、それをいちいちチェックするということはなかった。それだけ国の財政が苦しくなっているということなのだろう。現在、フィリピンはマルコスが生み出した山のような対外債務を抱えて四苦八苦している。少しでもペソの海外流出を防ごうという苦肉の策なのだろう。
出発ゲートでウジャウジャといる日本人に混じって搭乗のインフォメーションを待っていると、飛行機の機体整備のために離陸が1時間以上遅れるという日本語の放送が流れた。なんと、PAL、プレイン・オールウェイズ・レイトが現実のものとなってしまったのだ。げっそりしながら、旅行の間ずっとノートにつけていた旅の覚え書きを書くことで時間をつぶすことにする。だが、1時間ほどたった項、出発がさらに遅れるという放送が流された。成田までたどり着いても、そこから家まで帰れるかどうか分からないギリギリの時間になってしまいそうだ。
しばらくすると、PALのスタッフがパンとジュースを持ってきて、航空券をチェックしながらの配布を始める。そのパンとジュースを貰うために列の後ろに並ぶと、なんだか難民かなにかになったような気分になる。もっとも、気楽な性分のせいか、そういう体験が面白くてしょうがないのだが。
パンは煮込んだ豚肉の入った中華マンジュウのようなもので、奇妙な味ながらも意外とうまかった。日本のファースト・フードの店に並べれば、わりと売れるのではないだろうか。
またしばらくすると、今度は予想だにしなかった事態が生じてきた。トイレに行きたくなっても、行くわけにいかないという実に困った事態に陥ってしまったのである。なにしろ、トイレに行くと、例によって蛇口をひねってくれたり、タオルを差し出してくれたりする人間がいて、チップが必要になるのだが、ペソは免税店できれいに使いきっている。少し残しておけばよかったと思っても後の祭り。僕のポケットの中から1ペソだけはかき集めることができたので、なんとか政子をトイレに送り出しはしたが、まさか、こんなところでペソが必要になるとは思ってもみなかった。もっとも政子は「他の日本人もチップを払ってなかったから」と言って1ペソを持ったまま戻ってきたのだけれど。
結局、飛行機は3時間遅れて離陸した。客の中には「日本に戻ってももう新幹線がない、どうしてくれるんだ」と日本人スタッフに食ってかかり、成田にホテルを手配させたりしている者もいた。気持ちはよく分かるが、こちらは飛行機が落ちるよりは遅れた方がまだましだと思って諦めることにする。どうやら、ハワイで飛行機事故があったばかりで、そのために普段以上に神経質になっていたらしいのだが、とにかく自分の乗った飛行機が落ちるくらいなら、他のことは何だって我慢できる。
だが、いつまでもブツブツ文句をいう奴がいる。近くのシートに座っている二人の男がわざとまわりの客に聞こえるように、
「この飛行機は絶対に落ちるぞ。ここで修理ができないから、日本に行ってから修理するっていうんだからな……」
と言い続けている。非常に不愉快な奴らだ。絶対に落ちると思ったら、なんであんたらは乗ってるんだ? 乗らなければいいではないか。まったくもう、どうしてこういうくだらない男が世の中にいるのか。飛行機が遅れたということよりも、こういう不愉快な反応をしめす人間にうんざりしてしまう。
通常、マニラ−成田間は4時間かかるのだが、この時は機長が急いだためか3時間半で成田に到着した。なんと30分も飛行時間を短縮してしまったのだけれど、いいのかね? もちろん、墜落もなければ不時着もなし。きわめて順調なフライトだった。
さて、ようやく日本だ。だが、ここで気を許してはならない。果たして、家まで帰ることのできる交通機関がまだあるかどうか、なかなかきわどいところなのだ。
機内に預けた荷物を受け取るなり、あわてて税関のチェックカウンターヘと直行する。政子が必死の形相で早く中を見てくれといわんばかりに迫ったためか、ほとんど中をチェックせずに通過。
スカイライナーはすでになくなっていたので、政子が箱崎行きのリムジン・バスのチケットを買いに走り、その間にこちらは荷物をABCのカウンターヘとかつぎこんで配送の手続きを済ませる。そして、文字通りすべりこみで23時発のリムジン・バスに飛び乗った。
だが、まだ安心はできない。箱崎から自宅まではまだまだ遠いのだ。さいわい高速道路がすいていたので、バスは順調に走り、1時間かからずに箱崎に到着する。あわててタクシー乗り場に走ると、なんとそこにはすでに列ができている。この後ろに並んでいたのでは電車がなくなってしまう。ターミナルの後ろから外に飛び出して、そこで通りかかったタクシーをつかまえる。そして、一気に東京駅へ。
24時20分。大宮行き最終の京浜東北線がホームに入ってきた。これに飛び乗ってようやく一息ついた。やった、なんとかこれで家に帰れる。
南浦和駅で京浜東北線を降りて、タクシーで自宅へ。午前1時30分、僕たちはようやく我が家へとたどり着いた。そして、僕たちの楽しかった休日はこの時に終った。セブにいた時にはあれだけのんびりと過ごしていたのに、セブを離れるなり途端に時間は急激に加速され、いやおうなしに日常の時間へと戻らされてしまった。
さて、最後に後日談をいくつか報告してこの拙い文章を終えることとしよう。
約束通り写真を送ったアルネルからは、手紙が2通来ている。家族はみな元気で、僕たちがまた来る日を楽しみにしているという。「俺のアイスクリームを食べるためにまたおいでよ」と彼の手紙には書いてあった。
ロルゥナさんからもポストカードが2通届いた。彼女のお薦めのボラカイ・アイランドの砂浜と海の写った素敵なポストカードで、見ているとまたフィリピンの海に行きたくなってしまう。「また、あなたたちのガイドをさせてくださいね」彼女のポストカードにはそう書いてあった。
マニラの宝くじ売りの少女からも、缶ペンケースを無事に受け取ったという手紙が来た。前の手紙に、経済的な問題で小学校を続けられるかどうか分からないと書いてあったけれど、なんとか勉強を続けると言ってきたのでほっとした。ただし、今度はお母さんが病気で寝込んでしまったという。色々と楽ではなさそうだ。
そしていま、政子のおなかの中では僕たちの赤ちゃんがスクスクと育っている。この旅行記を1年近くかけてのんびりと書いているうちに、すっかりおなかが大きくなってしまった。来年の2月には生まれる予定になっている。「次は赤ちゃんも連れてセブに行こうね」、まだ生まれてもいないのに、僕たちはそんなことを話しあっている。でも、家族で何度も行けたら素敵だろうな、と思う。ハドサンのレストランに座って、海から吹いてくる風に包まれたなら、とても素敵だろうな、と思っている。いつの日か、子供を連れて家族で、セブの風に会いに行こう。その頃にはアルネルの子供も大きくなっているに違いない。いつになるのかは分からないが、今からその日が楽しみでならない。
(1989年11月20日)
戻る
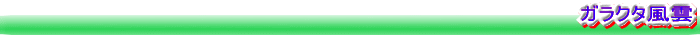
|