|
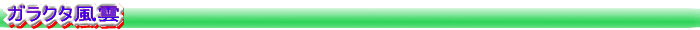
ああ、脳細胞は今日も減りゆく
記憶力がなんだ!
ジェラルド・A・ブラウンの『超能力者ハザード』には抜群の記憶力を持つ主人公が登場する。なにしろ、「イギリスの国王でいちばん嫡出子が多いのは、どの国王?」と聞かれると、即座に「エドワード一世だ。二人の王妃に十六人の子供を生ませている。王妃はカスティリャのエレアノールとフランスのマルグリット。エドワードは1307年に35才で死んでいる」と答えてしまうくらいだから、並みの記憶力の良さじゃない。ま、そこまで極端な例を出すまでもなく、冒険小説の世界には、記憶力の良い人間がゾロゾロと出てくる。例えば、ボブ・ラングレーの『北壁の死闘』には、こんなシーンがある。
「電話を入れろ。誰か信用できる人は?」
「ドクター・ル・グラス。仕事上でも親しいの。誰かが聴き込みに来たりすると、きっと教えてくれるわ」
「その人に、体調が悪いと話せ。仕事の肩代わりも頼んでおくことだ。状況が思わしくなかったら、220925番に電話を入れ、ルークを呼び出せ。相手が出たら『ご栄転、おめでとうございます。これで果物市場も大きく発展いたします』という。わかったか?」
僕ならここで、間違っても「はい」などとは答えない。だが、ヒロインのヘレーネは素直にここで「はい」と答えているのだから、やはり記憶力はいいのだろう。 また、ローレンス・プロックの『魔性の落とし子』にもとんでもない記憶力の持ち主が登場する。
「きのうの午後、きみのおふくろさん、ぼくん家の前を車で通ったぜ」と彼は言った。エアリエルは何気なくうなずいた。「車のナンバーは」と彼は続けた。「664−AQT。ダットサン。おやじさんのはフォード・トリノ。LJK−914」
エアリエルはぽかんと彼を見つめた。
「ぼくはある人間に関心をもつと、そいつのことを何かと知りたくなるんだ。それでちょっとばかり調査をする。それだけのこと。きみのおやじさんはアシュレー・クーパー・ホーム・プロダクツ社の貿易部にいる。きみはおやじさんの職場の番号知ってるかい?」
「番号?」
「電話番号さ。787−5645。内線番号342」
どうしてこんなことが覚えられるのだ。全く信じられない。僕なんか自慢じゃないが、自分の車のナンバーすら覚えていない。それどころか、家族の誕生日も妻の血液型も会社の住所も大学の卒業年度も深プラでたまに顔を会わせる人達の名前も、なあんにも覚えられないでいるのだ。どうだ、驚いたか。ハッハッハッ……、俺はなあ、俺はなあ、記憶力が悪いんだ! 人一倍、極端に記憶力が悪いんだ! だから、小説の中に記憶力の極端にいい人間が出てくると、羨ましいやら悔しいやら、とてもとても複雑な気持ちになってしまうのだ。
どんなに記憶力が悪いかというと……
先日のことだ、広島、大阪、仙台とまわる出張に出ることになった。間違っても、飛行機や新幹線の中で退屈などすることのないように、エド・マクベインの87分署シリーズを持っていこうと思った。そこで、シリーズの作品リストを取り出して、はてさてどこまで読んだろうかと考えた。余人はいざ知らず、僕は、シリーズ物になると自分の読んだ本のタイトルがまるで覚えられないでいる。ディック・フランシスにしても、ロバート・B・パーカーにしても、どの本を読んで、どの本を読んでないのかがまるで分らなくなってしまっている。たとえ読んだということに確信が持てたとしても、その内容を思い出すことなど、まずないに等しい。
そこで、ウーンと唸り、リストを睨みつけ、薄れかけた記憶の中を探ることになる。まず、『人形とキャレラ』は読んだ。それは、はっきりと覚えている。ストーリーは全く覚えていないが、人形の出てくる話を読んだ記憶だけはある。では、『八千万の眼』か……。しかし、これも読んだような気がする。じゃあ、『警察』からか。
本棚に行き、『警察』をひっぱり出し、念のために裏表紙のあらすじを読んでみる。ウーン……なんとなく読んだような気がするのだが……。しかし、読んだことがあるのに思い出せないなんてことがあるのかね。思い出せないってことは読んでないってことじゃないのかな。しかし……。読んだような気もするんだよなあ。
試しに、次の『はめ絵』を出してみる。裏表紙のあらすじを読むと、ウーン、これは、読んだ、よ、う、な……オイオイ、読んでるよ、これ! この本は間違いなく読んでるよ。読んだことがあるよ。と、言うことはだ、『警察』も読んでるってわけだ。じゃあ、次に読むのは『ショットガン』じゃないか。
というように、87分署の次に読む本を見つけ出すだけで、こんなに混乱するほど、僕の記憶力には欠陥があるのだ。
そして、悔しいことに『ショットガン』の中には、こんなシーンがあった。ちょっと長いけれど引用してみると……
「あたしの電話は、ワシントン6−3841番よ。今夜あとで、あんたがガール・フレンドと別れてから電話して」
「今夜は彼女と会わないんだ」
「会わないの?」アンはびっくりしたように尋ねた。
「ああ、彼女は水曜の晩は学校だ」
「だったら、話はきまったわ。勘定をすまして」
「払うよ。だが、何もきまってはいないよ」
「あたしといっしょに来るのよ」アンはいった。「六回セックスをやって、それからあたしが何か晩御飯を作って、それからまた六回やるのよ。明日の朝、お勤めは何時から?」
「返事はノーだ」クリングがいった。
「いいわ」アンはにこやかにいう。
「でも、電話番号は書いといて」
「書いておく必要はないよ」
「まあ、頭のいい刑事さん。では番号は?」
「ワシントン6−3841」
……ねえ、誰か教えて。どうして、こんなふうに人の電話番号が覚えられるの?
しかし、僕の素晴らしき無記憶力はこの出張の帰りに、遂に真の実力を発揮したのである。仙台駅で読む本のとぎれてしまった僕は慌ててキヨスクに飛び込み、文庫化されたばかりの連城三紀彦の『少女』を買ったのだが、この短編集のふたつめの作品「少女」まで読んで、突然に思い出したのだ、すでにこの本を読んだことがあるということを。「少女」を読むまではきれいさっぱり忘れていたのだが、僕はこの本をハードカバーで持っていて、とっくの昔に読んでいたのだ。ひとつめの「熱い闇」を読みながら、どこかで読んだような気がするな、とは思ったのだが……。
先日、ついに30才の誕生日を迎えてしまった。僕の脳細胞は今日も着々と減りつつある。
(初出:日本冒険小説協会会報「ワープロ版イーグル」第26号/昭和63年)

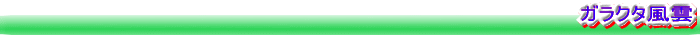
|