|
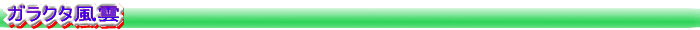
『美人島征服』登場!
淑女スパイ、<モデスティ・ブレイズ>シリーズの第1作、『唇からナイフ』が講談社ウィークエンドブックスから出版されたのが昭和41年7月15日。ギャビン・ライアルの『深夜プラス1』が早川のポケットミステリーから出版されたのが昭和42年2月15日。そして、アリステア・マクリーンの『女王陛下のユリシーズ号』がハヤカワノヴェルズから出版されたのが昭和42年3月15日。
当時、現場にいたわけではないので断言することは出来ないが、これを見るとどうやら冒険小説の翻訳が我が国で本格的に始まったのは昭和40年代になってからと言うことができそうだ。そうなると、それ以前には冒険小説の好きな人間は一体どういう本を読んでいたのであろうか。ふと、そのことに興味を覚えた僕は、自分の本棚の中に昭和40年以前に書かれた冒険小説を捜してみた。
その結果見つけたのが梶野悳三の『美人島征服』であった。昭和34年8月10日に桃源社より発行された海洋冒険小説である。梶野悳三という作家がどういう小説を書いていた人なのかは知らないが、どうやら昭和40年以前にはこのような小説が読まれていたらしい。
今回はいつものおふざけ、ダジャレをやめて、大真面目にこの『美人島征服』を紹介することにしよう。
話は明治12年の秋に始まる。
旧篠山藩士の池直人は全財産2百円を持って東京に出てきたのであるが、その金を何者かに盗まれてしまう。さて、困った、と腕組みしていると、今度は自分のカバンの中から5百円の大金が出てくる。
「これは妙だ!」直人は目をパチクリ。
いつの間にかカバンかいれちがっていたのである。早速その金を届けに行くと、直人は金の持ち主の入江義文、肥後鶴見の二人と意気投合し、彼等について海竜丸という2千百トンの日本一の船で大海原へと乗り出すことにする。
まったくもって安易でいいかげんな導入部であるが、このくらいであきれかえっていてはいけない。この小説はもっともっと奥が深いのである。
入江先生より航海の目的についての話が始まる。
「われわれ人間はこの地球に生まれたかぎり、どこへでも住む権利をもっている。それは神から与えられた人間の特権で、何人もこれを犯すことが出来ない。ところが西洋人種は一竿の国旗を無人の地にたててこれわが版図なりとして、他国人の入るを許さない。
それが万国公法をもって許されるならば、われわれにもまた先取権があるはずだ」
「アフリカ大陸から海に注ぐザンベツという大河がある。長さ数百里に達してその流域はきわめて豊饒だ。アフリカ南部はすべて各国にくいあらされているが、その中間南緯20度より赤道に至るザンベツ川の流域三百万里にあまる広大なる土地は、未開の処女地である」
その広大な土地を開拓して、そこに新日本国を建設する、それが航海の目的だったのである。そのため、ルソン、ボルネオ、ジャバ、スマトラの諸島を巡航しながら、交易をして準備をととのえて、蛮土におしわたろう、というのである。戦後に書かれた小説であるとは思いたくない設定ではあるが、許して先に進むことにしよう。
船の中にはひとくせもふたくせもある男ばかりが乗りこんでいた。その中に一人の美少年もいた。十七、八の少年水夫。名を本荘四洲丸という。小柄で、すべすべした肌をして、女にしてみたいような若者である。
−こいつ、もしかすると変性男子かもしれんぞ。
直人はそう思うと、なにかこう悩ましい気分になって来るのであった。(変性男子とはつまりオカマのことでありますね)
海竜丸は香港に着いた。そこにはありとあらゆる皮膚の色をした人種が歩いていて、日本人は見るからにパッとしない。
「アハハハハハ、じゃあこうしよう。これは君なんかことに大賛成だと思うが、世界中で最も美人を産するのは、トルコ領のアルメリアだ。そこでは美人市場が立っとる。そこでわれわれの国が出来たら、とりあえずアルメリア美人を百人ほど仕入れてきて、君たちにわけるんじゃね。そうして人種改造を行なうのだ。どうじゃね、この案は」
などという会話を平気でかわしている。かなりやばいんじゃないだろうか、こういう考えって。
この香港で四洲丸は女であることがばれて船を下ろされてしまう。
海竜丸はさらに進み、ボルネオに到着するが、そこで土人に襲われたり、支那人の海賊に襲われたりする。直人たちは逆にその支那の海賊船を乗っ取るが、その船には香港で下ろした筈の四洲丸がいた。彼女の本当の正体は支那の海賊王の娘、倩だったのである。そして海賊船にはもう一人、倩の妹の春妹も乗っていた。
倩はすっかり直人に惚れてしまい、なにかというと直人に抱いてもらいたがるのである。
バタビヤで直人と倩は事故でジャングルの奥地に紛れこみ、土人部落に掴まってしまう。ここでも直人はマラ族の酋長の娘、ポ二姫に惚れられてペロペロと顔を嘗められてしまうのであるが、このへんの土人は性交が唯一の慰安であるので、女の性欲もすこぶる猛烈烈であるという。
このへんでたいていの読者はあきれかえってしまうのであるが、もう少し我慢してつきあってみよう。
酋長は酋長で倩に惚れてしまうのであるが、折りよく病気にかかってしまう。それを直人がモルヒネ注射で直してしまい、今度は神さまの扱いを受けることになってしまう。かくして物語は『冒険ダン吉』の世界へと突入していくのである!
結局、直人はポ二姫と結婚をしてマラ族の酋長の座におさまり、倩を二号とすることにするが、婚礼の最中にトミニ族の襲撃を受けてしまう。
直人は嫁にする筈のポニ姫は放り出して、倩と二人で命からがら逃げ出すが、川に出たところで奴隷商人のトムに掴まってしまう。この男がトミニ族に銃を渡していたためにマラ族は敗れてしまったのである。
このあたりでようやく半分ぐらいなのだが、実にあほらしいストーリー展開に呆然としてしまい、本を放り出すのを忘れてしまう読者も続出することだろう。この後も『インディ・ジョーンズ』プラス『ロマンシング・ストーン』割る百というような大冒険が続き、ようやくのことで直人と倩は海竜丸に帰りつくのであるが、その辺の冒険ははぶくことにしよう。
海竜丸に戻ると、新たなる冒険が直人たちを待っていた。ジャワの独立運動を援助して欲しいという要請が海竜丸に舞い込んで来たのである。直人たちは早速ジャワに向かい、独立運動勢力と合流した。
ある日、武芸大会が行われ、直人は倩の妹の春妹と対することになった。小娘とはいえ、拳法の使い手だ。油断は出来ない。
直人は春妹につかみかかる。瞬間、かわされて前にのめる。ヒラリとおどり上った春妹のすらりと伸びた白い足が直人の首にからみついて、首をしめる。
直人は狼狽して、やけくそに首をうちふった。その目に思いがけないものが入ってきた。力演のあまり春妹の下ばきの前がほころびてきたのである。直人はこんもりもりあがったスロープから、まだ開ききらない春をまつ一輪の花から、下もえのやわらかい草まではっきり見てしまったのである。
「もうだめだ。とてもかなわん」
ドシンと尻餅をついて、直人はふーっと息をついた。
実にとんでもないエピソードであるが、このあとも、直人たちは猪狩りに出て、地元のテングリ一族の女たちに襲いかかられてその欲望の餌食にされたり、そういったどうでもいいような、それでいてこの小説の本質であるようなエピソードが続き、最後の五分の一でようやく本筋、ジャワの独立運動の話しに入るのである。
直人たちの活躍により、ジャワ中に独立の気運が高まっていく。しかし、今ひとつというところで、彼らが支援していた二人の王に海竜丸の人間は裏切られてしまう。バタビヤの総督が秘かに申しいれてきた和儀の交渉を受け入れてしまったのである。もうひと押しというところまできて直人たちの努力は無駄になってしまったのだ。
「それで私たちはどうなるの」
倩が直人に尋ねた。
「元の木阿弥さ。つまらん道草をくったと諦めて、最初の目的通りアフリカへいくんだな」
こうして海竜丸はあっさりとジャワの独立を諦めて、希望の地、アフリカをめざして印度洋にのりだしたのだった。
信じられないかもしれないが、ここで『美人島征服』は一巻のおしまいなのである。まるで『戦時標準船荒丸』ではないか。これからという肝腎なところで終わってしまうのである。
それにしても、とんでもない小説があったものである。この小説の作者は日本が戦争に負けたということを知らないのではないだろうか。本気でそう思いたくなってしまう。面白いことは面白いのだが、あまりにもバカらしい。
冒険小説の翻訳が本格的に始まるまで、ホントにこんな本が読まれていたのだろうか。翻訳冒険小説がいくらでも読め、日本でも優れた冒険小説が多く書かれている時代に生まれ育ったことを心から感謝したくなる小説だった。
(初出:日本冒険小説協会会報「ワープロ版イーグル」第13号)
追記:
古典SF研究会の藤元直樹さんによると、この『美人島征服』のストーリーは、明らかに矢野龍渓の『浮城物語』の再話なのだそうです。うーん、単なる時代錯誤のバカ話だとばっかり思っていたら。
またさらに、梶野悳三の『海の先駆隊』という作品も、矢野龍渓の作品を下敷きにした小説だということです。
うーん、なかなか奥が深い。そして、そういう深い奥にあるいろいろなことを、ちゃんと知っている人がいるものです。さすがです。
というわけで、藤元さん、情報ありがとうございました。

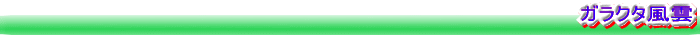
|