|
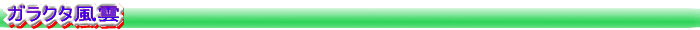
風繼續吹
(1)
イム・ホー監督の新作、『風繼續吹』が完成したという情報を得てからすでに一年以上の時間が流れていた。にもかかわらず、この作品が香港で上映されたという知らせが届く気配は一向になかった。どうしてしまったのか。いいかげん待ちくたびれた頃に、イーグル・カンパニーのジェームズ・H・鷲尾氏から連絡が入った。『風繼續吹』のビデオが手に入ったという連絡であった。
しかし、『風繼續吹』は劇場未公開作品である。当然ながらいまだビデオ化はされていない。そのビデオが正式のルートで手に入るはずがなく、そのことを問いただすと、鷲尾氏はこう説明した。
「一方的に送られてきたものなので、確実なところはよくわからないが、どうやら試写室で上映したものをビデオ撮りしたもののようだ。もちろん、そうなると違法な行為によって作られたビデオということになる。だがね、もろもろの状況から推測すると、どうもビデオ撮りを指示したのはイム・ホー本人ではないかと思えるんだが……」
映画を作った監督が自分自身で海賊版ビデオの製作を指示する! そんなことがありうるのだろうか。そんなことをしたところで、なんのメリットもないではないか。だが、さらに説明を聞くうちに、しだいに事情が飲み込めてきた。
『風繼續吹』は、その中に好ましくない描写があるということで、中国政府から圧力がかかり、そのために上映の見通しがたたなくなっているらしいのである。もっとも、中国サイドが圧力の存在を認めるわけもなく、あくまでも信憑性の極めて高い噂という域を出るものではないのだが。
そういえば、アルフレッド・チョン監督の『火爆城市』も、中国の圧力によって上映が中止に追い込まれたのだという話しを聞いたことがある。この作品を日本に配給するはずだったイーグル・カンパニーによると、プロデューサーのサモ・ハンから上映中止になった旨の連絡はきたが、その理由については一切説明がなかったという。ただ一回だけおこなわれた試写会でこの作品を観た僕は、よほどラッキーだったということだろう。かろうじてジャッキー・チェンの『新ポリス・ストーリー』に流用された九龍城爆破のシーンで『火爆城市』の映像の片鱗に触れることはできるものの、あの傑作アクション活劇が一般公開されることなく闇に葬られるのだとしたら、それはもう、勿体ないどころの話しではない。しかし、真っ向から中国の天安門事件を批判した映画を中国政府が嫌い、圧力がかかるのも止むを得ないことだろう。
さて、『風繼續吹』についてはさらに、製作元のトムソン・フィルムが、『風繼續吹』をオクラにするということを条件に、中国本土での映画撮影にいろいろと便宜をはかってもらえるという裏取り引きに応じたという噂もあるらしい。トムソンといえば、チェン・カイコー監督を起用して『さらばわが愛〜覇王別姫』を製作した会社である。となると、なにやらもっともらしく聞こえてくるではないか。
かくして陽の目をみる可能性が極めて薄くなった『風繼續吹』であるが、それに抗議するために監督自らが海賊版のビデオを製作し、世界中の映画関係者に送りつけた、というのが鷲尾氏の推理であった。
ウ〜ム……僕は唸った。はたして本当にそんなことがありえるのだろうか。真偽のほどはよくわからないが、とにかくイム・ホー監督の新作が観られるのであれば、嫌も応もない。なにしろ、『レッド・ダスト』以来、四年ぶりの新作である。僕はさっそくそのビデオを借りることにした。
(2)
数日後、鷲尾氏から送られてきたのはビデオだけではなかった。簡体字ではなく繁体字の中国語で書かれた分厚いコピーが同封されていた。表紙には「李光華探索的日子〜風繼續吹製作記録 厳浩著」とある。どうやら『風繼續吹』の製作にまつわるイム・ホーの手記のようだ。発行元の欄には香港影業協會とある。しかし、そのような本が出版されたというような噂はついぞ聞いたことがない。鷲尾氏に問い合わせの電話を入れると、イーグル・カンパニーの香港支局が手に入れたものとのことだった。本来なら香港影業協會から発行されるはずであった『風繼續吹』の製作手記であるが、どういうわけかゲラ刷りのあがった段階で出版が取り止めとなってしまい、そのことを聞きつけたスタッフが裏から手をまわして手に入れてくれたものらしい。
映画がオクラになったことといい、その製作手記の出版が中止になったことといい、なにやら穏やかならざるものを感じるが、とにかく僕はビデオを観ることにした。そして、激しく興奮した。あの『レッド・ダスト』が、実はこの作品を撮るための準備にすぎなかったのではないかと思えるほどの、重厚でなおかつドラマチックな作品であった。
僕は興奮覚めやらぬまま、勢いにのって「李光華探索的日子」にとりかかった。中国語など全然読めず、毎号送られてくる「電影双周刊」にしても写真だけみて喜んでいるような僕ではあるが、今回は最低限の意味だけは理解しようと、辞書を引きながら読み進めていった。その結果、この映画の背景にあるものが数多く見えてきた。中国側がこの作品の上映を嫌う理由も充分にうなづけた。
イム・ホーの『風繼續吹』は、完全なノンフィクションの映画化だったのである。しかも、中国にとって、中国共産党にとって、マイナスのイメージとなるエピソードを内包した映画だったのだ。
(3)
一九九一年。私は台湾金馬奨授賞式に出席するために台湾を訪れた。さいわいなことに『レッド・ダスト』は台湾で非常に高い評価を受け、グランプリを初めとする八つの部門で賞をいただくことができた。それは、私の人生の中でも、最も華々しい瞬間であったといえよう。
だが、空いた時間を利用して訪れた台北市郊外にある故宮博物院で、私はより興奮をもたらすものに出会った。それは院の一階に掲示されていた一枚の地図だった。その地図には、北京の紫禁城から台湾まで、膨大な量の文物を運んだルートが描かれていた。ルートは途中で三本に分かれ、それぞれが船、列車、トラックを次々と乗り継ぎ、延々と運ばれていることを示していた。その途中には戦闘があったことを表わす爆発のマークがいくつもいくつもついていた。
私はその地図の背後に壮大なドラマがあることを感じた。それをなんとしてでも知りたい、そして、そのドラマを映画にしたい、私は切実にそう思った。金馬奨を受賞したことによる精神の高揚が続いていたのかもしれない。とにかく、私はその瞬間に『風繼續吹』にとりつかれたのだ。私の頭の中には『風繼續吹』のことしかなくなってしまったのだった。
私はさっそく資料収集を始めた。だが、故宮博物院の文物移送に関する資料は意外なほど乏しかった。そこで、私は何度も台湾に足を運び、当時の現場にいた人たちへのヒアリング調査を繰り返した。話しを聞く相手は高齢の人が多く、すでに亡くなっている人も少なくはなかった。
何人も話を聞くうちに、文物移送にかかわった人たちが全員、中国の文化を守ったことに対する強烈な誇りを持っていることにいやでも気づかされた。彼らは皆が皆、中国の伝統的な文化を自分たちが体をはって守ったのだという強い自負心を持っていた。
私が話を聞きにいくと、彼らは胸をはって誇らしげに答えるのだ。
「私はあの長い旅を通じて中国人の文化を守り抜いた。そのことだけで私は胸をはって生きてくることができた。先祖にも子孫にも自慢できる貴重な業績だ」
彼らの多くは国民党兵士として文物移送の任務にかり出され、そのまま家族と引き離されて台湾に渡ってしまったという者も少なくはなかった。すぐに大陸に戻って家族と合流するつもりでいた彼らにとって、台湾におけるその後の人生が順調であるわけがなく、ほとんどの者が多くの困難を抱えたまま台湾での生活を乗り切ってきていた。そして、その困難な道のりを支えてきたものは、彼らが運んだ故宮博物院に展示されている文物であったのだ。
私はそれまで、戦時のドサクサにまぎれて国民党が紫禁城の宝物を盗み出したのだというイメージをいくぶんか持っていたように思う。だが、それはとんでもないあやまちであった。彼らは、中国の文化を守るという崇高な目的のために、さまざまなものを犠牲にしてきたのだ。日本軍の侵攻、共産党との対立といった緊迫した状況下に、よこしまな目的の入り込む余地などありはしなかったのだ。彼らにとって、それは聖なる戦い以外のなにものでもなかった。
やがて、いくつもの取材の中から、主人公となるべき人物を見つけ出したと私は確信した。名前を李光華という。彼は文物移送の旅において、常に指揮官の横に控えて補佐の役を勤め、事態が暗礁に乗りあげそうになるたびに機転をきかせて問題を解決したのだという。しかも、戦闘の際には真っ先に武器を持って敵の中に飛び込んでいく血気盛んな若者でもあったらしい。人間的に魅力のある人物だったらしく、彼を知る者は皆懐かしそうに目を細めて彼のことを誉めたたえるのであった。
そこで私は取材のターゲットを李光華に絞り込み、引き続き情報の収集につとめることにした。
(4)
以上が『風繼續吹』製作のきっかけに関するエピソードである。
イム・ホー監督の取材は続き、小さなエピソードの積み重ねによって、次第に李光華の素顔が浮び上がってくる。そして、その取材行はついに李光華が幼少の日々を過ごした中国河北省滄県にまで伸びる(『風繼續吹』を撮り終えた今となっては、もうイム・ホー監督に中国本土での取材が認められることはあるまい)。そこで、イム・ホー監督は李光華の父が何者かに襲われて謎の死を遂げているという事実に出会う。一九二四年、李光華が九歳の時の事件であった。
李光華の父は当時の河北省ではかなり名の知れた武術家であったらしい。特に得意としていたのが棒術であったという。伝説によると、壁に止まったハエを棒で突いて落とし、なおかつ壁には一切のあとを残さないほどの名人であったという。その父親を殺した犯人はついに捕まらず、現在にいたるも真相は謎に包まれている。だが、今も村に残る噂によると、土地の権力者が李家に代々伝わる家宝、青龍玉と呼ばれる翡翠の彫り物を狙って刺客を送り込み、そのために命を落としたのであろうということであった。
映画『風繼續吹』は、その父親殺害の場面で幕をあける。
棒を手にかまえる男を十数人の黒装束の男たちが取り囲む。男たちの手には刃物がにぶい光を放っている。
ゴホッ、囲まれた男が血を吐く。自分の血をみて、けげんそうな表情で男がつぶやく。
「毒……」
取り囲む男たちに勝ち誇ったような表情が浮かぶ。何らかの方法ですでに毒を飲ませてあったのだろう。
男たちの一人が刃物を振りかざして背後から襲いかかる。囲まれた男は振り向きもせずに、背後の男を手にした棒で叩きのめす。
だが、すでに毒が回り始めているのであろう。次第に足元が怪しくなってくる。
ふらついたところを狙って、黒装束の男が一人、また刃物を突き出して襲い掛ってくる。それを再び一瞬の早業で打ち倒すが、それが限界であった。
ガクリと膝をついたところを数人に同時に襲いかかられ、何人かは叩きのめすものの、すべての刃物を防ぎ切ることはできなかった。
血しぶきが飛び、男が倒れる。
黒装束の男が一人、倒れた男の懐をまさぐり、血にまみれた翡翠の彫り物を奪い取る。
少年が一人、真新しい墓を前に立ちすくんでいる。少年の手には、使い込まれた一本の棒がしっかりと握られている。
びょうびょうと風が吹いている。
少年は墓に背を向けると、ゆっくりと歩き出した。その後ろ姿にマリア・コルデロの歌う挿入歌がかぶさっていく。痛々しいまでに情感のこもったスローバラード。
「一九二四年 中国河北省」
画面にゆっくりと文字が浮び上がる。
マリア・コルデロの今にも泣き出しそうな歌声が次第に盛り上がり、ゆっくりとひいていく。静かにタイトルが現われる。
「風繼續吹 〜RED DUSTⅡ〜」
そして、物語は一気に一九三二年の北京へと飛ぶ。
(5)
いうまでもなく、このオープニングシーンに登場する少年が幼き日の李光華である。だが、李光華の消息は一九二四年のこの事件以降ぷっつりと途絶える。再び彼が姿を現わすのは、一九三二年になってからだ。その間、李光華がどこで何をしていたのかは、イム・ホー監督がいくら取材を続けても分からなかったらしい。
さて、李光華は一九三二年になって北京の故宮博物院(紫禁城)に姿を現わし、映画はその姿を追っていくのであるが、まずはそれに先立つ関連の歴史について簡単に触れておこう。
孫文が南京を首都として中華民国を建国したのが一九一二年である。それから九年後の一九二一年に中国共産党が結成され内戦が始まる。そして一九二四年、国民党は北京まで軍を進め、十一月にはラスト・エンペラー、溥儀が紫禁城より退去。国民党政府は紫禁城をはじめとする数カ所に保管されていた文物の点検を一斉に開始し、一九二五年九月に故宮博物院を設立している。私腹を肥やさんとした宦官のためにすでに多くの文物が売り捌かれていたとはいえ、まだまだ膨大な量の貴重な文物が残されていた。
ところが、一九三一年九月十八日に満州事変が発生。その翌年の一月二十九日に第一次上海事件が起こり、三月に満州国が建国され、しだいにきな臭い時代へと突入していくことになる。
そして一九三二年、日本軍の侵攻に危機感を覚えた国民党政府は故宮博物院の文物の移送を決定し、梱包作業に取りかかる。しかし、なにぶんにも量が膨大で、なおかつ作業中の盗難を防ぐために複数人が互いにチェックしながらリストとの照合をおこなって梱包していくのであるから、作業は難航をきわめた。そのため、近在の学生などもかき集められこの作業に従事させられたりしたのだが、この時参加した学生の中に李光華の姿があったのである。
そして、これ以後、李光華は常に故宮博物院の文物の移送にかかわり続けることになるのだ。
(6)
映画は李光華の姿を中心に、一九三二年秋に始まる梱包作業、一九三三年二月の第一回目の運び出し(百台以上の大型トラックで北京西駅へ運び、そこで三十九両編成の特別列車二編成に積み替え、鄭州、徐州を経由して浦口まで運び、そこで今度は貨物船に積み替えて揚子江を抜けて上海のフランス祖界まで運ぶという大がかりなもの。一万九千五百五十七箱の荷物を運ぶために、同様の移送が五回にわたっておこなわれている)といった情景を描いていく。
主人公李光華を演じるのは張衛健(ディッキー・チョン)。一時はポスト周星馳としてコメディ映画に多く出演していた彼であるが、彼の本質はコメディにはないと主張するイム・ホー監督が主役に起用したものらしい。張衛健としては初の大役といえよう。
張衛健が演じる李光華は、(最初のうちは)他者が内面に踏み込んでくることを拒絶するやや神経質で寡黙な若者として描かれる。彼の真面目な働きぶりを認めた軍の指揮官、曹健南(牛馬)がなにかと李光華の面倒をみるのだが、彼はなかなか心を開こうとしない。
だが、上海でのある事件をきっかけに、若者は曹健南に徐々にうちとけはじめる。そして、中秋節の夜、揚子江のほとりで酒を飲み交しながら李光華は曹健南に自分の夢を語るのだった。
「俺は飛行機乗りになりたい。風に乗って、自由に空を飛べるようになりたい」
翌日、曹健南は若者に一冊の本を贈る。軍隊が使っている飛行機操縦法のテキストブック。李光華はこの後、この本を常に持ち歩き、繰り返し読みふけることとなる。
(7)
一九三六年。七月七日の盧溝橋事件をきっかけに日本と中国は全面戦争に突入する。そのため、上海すらすでに安全ではないと判断した国民党政府は、文物を南京にまで疎開させる。だが、日本軍の勢いは国民党政府の予想をはるかに上回っていた。
八月四日、北京陥落。八月十三日、上海に日本軍が上陸。そして、十一月十二日には上海が陥落。南京市内は難民でごった返していた。文物の移送にかかわっていた兵士の中には、家族を心配して任務を投げ出す者も現われていた。だが、李光華はどんどん文物移送にのめりこんでいく。
南京からの文物の移送は三つのルートに分かれる。
まず、八十箱は船に積まれて揚子江を遡上し、武昌から貨車に積み替えて長沙へ。ここで共産党ゲリラの襲撃を受けるが、トラックに積み替えて貴陽の百キロ西に位置する安順というところまで運ばれる(この八十箱は後に重慶郊外の巴県という場所にまで移される)。
また、七二八六箱は陸上を二年半の歳月をかけて四川省の峨眉まで移送されるが、途中の鄭州、徐州等で日本軍による空襲を受けている。
そして映画は、残りの九三六九箱の移送の様子を描いていく。曹健南が指揮し、李光華が従うこの移送は、空襲の合間を縫って十二月八日に開始された。チャーターするはずだった船が戦況の悪化に恐れをなして姿を消してしまうというアクシデントが発生するが、李光華が機転をきかせて二隻のイギリス船をチャーター。なんとか南京を離れたのは日本軍が南京入場を果たす五日前のことであった。
そして、漢口、宜昌、重慶と移動していくが、途中で何度も共産党ゲリラに襲われたり、日本軍の空襲を受けたりして、長江上流約五百キロの辺地、楽山に辿り着くまでに三年近い歳月がかかってしまっている。
なお、この時点では既に第二次国共合作が成立していたはずなのだが、地方ではそれらの統制が徹底していなかったらしく、各地で衝突が繰り返されていたらしい。そのため、李光華らの移動は、常に日本軍と共産党ゲリラに悩まされることとなる。
だが、楽山に辿り着くことによって、ようやく李光華たちに休息の時が訪れるのだった。
(8)
楽山で李光華は、父の形見として持ち歩いていた棒がきっかけとなって一人の武術家、張志成(元華)と出会い、正式に武術を習い始める。また、張志成の娘、張美[王其](陳明眞)とも出会い、ふたりは恋に落ちていく(さすがにイム・ホー監督はこういう場面の描写が達者で、じつにさりげなく、なおかつ効果的な映像でふたりの心の動きを描いている)。そして、今では李光華を実の息子のように可愛がっている曹健南も、初めは内にこもってまわりに溶け込もうともしなかった若者の変わりように目を細めるのだった。
そのままなにごともなく六年の歳月が流れる。上海で梱包作業を手伝っていた十七歳の若者も、いつしか三十歳になっていた。
だが、ある夜、李光華は故宮博物院より運ばれてきた木箱のひとつをこじ開けようとしているところを仲間に発見されて逮捕されてしまう。そして、問い詰める曹健南に李光華は真相の全てを告白するのだった。
そもそも李光華が文物移送に参加した目的は、家宝の青龍玉を取り返すことであった。父を殺されて奪い取られた青龍玉は、土地の実力者から賄賂としてその地域を管理する役人の手に渡り、その役人からさらに上司の手にわたり、何人もの手を経て皇帝の宝物庫にしまいこまれていたのであった。賄賂が当然のこととしてまかり通る当時の中国では、珍しくもなんともないことであった。
そのことをようやく探り出したところへ事変が発生し、故宮博物院の文物の移送が開始されることとなる。李光華はあわててその作業に潜り込むが、文物の量があまりにも膨大すぎて青龍玉がどこにあるのかがどうしてもわからない。そのうえ、いつしか当初の目的よりも、文物を日本軍や共産党ゲリラから守ることにのめりこんでいってしまう。
かくして、孤独だった人生に、初めて仲間と生きる目的とが与えられたのであった。
だが、楽山での平和な日々が続くうちに、李光華の胸の内に青龍玉を取り戻すという当初の目的がよみがえってくる。さいわい、曹健南が管理していた目録を盗み見ることによって、青龍玉のありかも分かっていた。青龍玉を取り返したなら軍を抜け出して、張美[王其]と世帯を持ちたいという新たな夢が李光華にとりついていく。
李光華は胸の内にしまい込んでいたことを一気に吐き出していく。それを聞いて曹健南は大きく溜息をつく。
「確かにその翡翠はお前の家に代々伝えられた家宝なのかもしれん。だが、だからといってお前に渡すわけにはいかん。今では、この目録に載っているものはすべて政府の財産なのだ。今回の戦争で政府の財政はひどく苦しい状態になっているだろう。その状態を乗り切るために、この文物が必要になるかもしれんのだ」
結局、李光華の行為は不問にふされることとなる。そして、曹健南のはからいによって、張美[王其]との婚礼もとどこおりなくおこなわれるのだった。
だが、歴史は再び李光華を混乱の中に引きずり込んでいく
一九四五年八月十五日。ポツダム宣言によって日本敗戦が確定し、日中戦争が終了する。だがしかし、それは国民党と共産党が全面的な戦争状態に再突入するということでもあった。
一九四六年。疎開していた文物の移送が再び開始される。今度は南京へと帰る旅だ。李光華は南京まで荷物を運んだ時点で軍を離れることを家族に誓い、行軍の先頭に立つ。
三か所に分けられていた文物はいったん重慶に集められ、それから南京へと向かった。だが、戦争によって道路は荒れ果て、橋は失われ、移送は困難をきわめた。
一方、国共内戦は共産党有利に傾き、北京は共産党軍の大軍の中に孤立しつつあった。そして、李光華の帰りを待つ楽山では……。
(9)
イム・ホーの手記をベースに映画のストーリーを駆け足で記してきたが、問題なのはこの後で描かれるエピソードであろう。イム・ホーが取材にもとづく完全な実話であると主張する以上、このあとのエピソードは中国にとっておおやけにはされたくない事件であるはずだ。というのも、楽山の村が共産党ゲリラに襲われ、住民のほとんどが虐殺されるという場面がこのあとスクリーンに展開されてしまうからなのである。長年にわたって国民党軍をかばい続けてきた、というのがその原因であった。
事実であるとするならば、この映画の公開をめぐって、中国が圧力をかけたという噂も納得がいく。ようやく世界中が天安門事件のことをなかったこととして忘れようとしている時に、この映像はいささかショッキングすぎるだろう。「やはり中国は怖い」、誰もがそう思ってしまうにちがいない。イム・ホー監督の意図はあくまでも故宮博物院の文物移送という壮大なドラマを描くことにあり、楽山における虐殺事件はその中のいちエピソードにすぎないとしても、中国の神経を逆なでせずにおれない映画であることだけは間違いあるまい。そもそも、この題材を選んだ時から、国民党寄りの映画にならざるを得ない宿命でもあったのだ。
しかし、この場面の描写がなるべく残虐なものにならないように気を配っているという様子は映像からよく伝わってくる。イム・ホー監督には戦争の悲惨さを描こうというつもりは一切ないらしく、この場面に限らず抑制のきいた演出が全編を通してのトーンとなっている。イム・ホー監督の過去の作品同様、ここにおいて描かれているのも、歴史という逆らいがたい巨大な流れに翻弄されていく男や女の姿なのである(ただし、それだけではないことはあとで説明する)。
(10)
共産党ゲリラの襲撃を受け、村人が次々と倒れていく中、武術家である父、張志成の活躍によって、張美[王其]だけは生き延びて村を脱出する。
なお、オープニングシーンやこの場面のアクション演出は元華と元奎が担当しており、イム・ホー監督の作品としては珍しく派手な立ち回りをみることができる。もっとも、派手といったところでチン・シウトンの演出するようなファンタスティックなアクションシーンというわけではない。これらの武闘シーンが映画全体のバランスを崩すことのないように、充分に抑制されたリアルなアクション演出が心掛けられている。
張美[王其]は父が使っていた一本の棒だけを握りしめて、村を後にする。風がびょうびょうと吹き抜けるその場面は、父を亡くして村を去る幼き日の李光華にピタリと重なっていく。そして、張美[王其]は李光華のあとを追って南京へと向かうのだった。
一方の南京では、文物を台湾に疎開させる作業が始まっていた。すでに共産党ゲリラが各地で蜂起しており、大陸のうちに安全な保管場所を見つけることができなかったのである。
台湾への海上輸送は三回に分けておこなわれた。
第一回目は一九四八年十二月、海軍の輸送艦「中鼎輪」を使っておこなわれた。この「中鼎輪」が南京へ回航された時、すでに船には台湾へ逃れようという海軍の家族たちが乗り込んでいて満員の状態で、とても荷物を積み込む余地などなかった。そのために、海軍総司令がわざわざ艦まで出向いて下船するように説得しなければならなかったという一幕も挿入される。すでに、国民党の敗色が濃厚となっていたのである。
なお、ここで登場する海軍総司令を演じているのはイム・ホー監督本人である。イム・ホー監督はいつも自作の中でさりげなくいい役を演じているので、今回もどこかに登場するだろうとは思っていたのだが。
第二回目の移送は翌一九四九年一月六日、商船「海滬輪」によっておこなわれている。
そして第三回目の移送が一月二十八日、輸送艦「崑崙」によっておこなわれるのであるが、その積み込みのシーンが『風繼續吹』最大のクライマックスとなる。そして、この場面によって『RED DUSTⅡ』というサブタイトルの持つ意味が初めて明らかになる。この映画はただ単に『レッド・ダスト』と同じ時代を描いたというだけではなく、もうひとつの『レッド・ダスト』といわざるを得ないようなクライマックスを迎えるのである。
(11)
輸送艦「崑崙」は華南方面への軍事補給物資輸送の任務も負っていたため、南京に停泊できる時間は二十四時間とタイムリミットが切られていた。しかも、共産党勢力が妨害工作のために南京に潜入しているという情報もあり、積み込み作業は深夜に行なわれることとなった。
だが、運の悪いことに、積み込みがおこなわれる翌日は旧暦の大晦日にあたっていた。そのため、積み込み作業にあたる労働者が揃わない。李光華は労働者を集めるために駆けずりまわるのだが、その間に接岸した「崑崙」に台湾へ避難する海軍総司令部の人員たちが家族を連れて乗り込んでしまう。大きな荷物を背負い、幼い子供の手を引いて船に押し寄せる人の波、波、波。みごとなまでに『レッド・ダスト』のクライマックスシーンがここに再現される。
第一回目の移送の時と同じように海軍総司令が来て下船を呼びかけるが、すでに南京にせまった危険は誰の目にも明らかなので、いっこうに混乱は収まらない。
ようやく労働者をかき集めて港に戻った李光華は、かまわず文物の積み込みを開始する。乗組員の寝室、食堂、医務室、甲板上、ありとあらゆる場所に荷物を積みあげていく。
スペースが完全になくなると、李光華は斧をふるって士官室の事務机を叩き壊し、そのスペースにも荷物を積み込んでいった。
そして、その混乱のさなかに張美[王其]がついに李光華に追いつくのである。が、積み込みの様子を陰から見ていた共産党ゲリラが張美[王其]を捕えようとする。それに気づいた李光華が右手に銃、左手に棒を持って、人波の中に飛び込んでいく。今まさに出発せんとする船から曹健南が声の限りに李光華を呼ぶ。銃声が響く。悲鳴。怒号。李光華の右手の銃が夜空に向けて繰り返し火を吹く。あわててうずくまる群衆の中を、李光華が駆け抜ける。張美[王其]をおさえた男の持つ銃が一直線に李光華に向けられる。そして……。
(12)
果たして最後までストーリーをばらしてしまっていいものやら、散々悩んだのだが、この作品が日本で公開される見込みもなさそうだし、ここまでストーリーを書いてしまったのだから、最後まで全部書いてしまうことにする。もし、最後まで知りたくないという人は、この先を読まないようにしていただきたい。
右腕を銃で撃ち抜かれながらも、李光華は鬼神のように棒をふるい張美[王其]を救い出す。そして、離岸せんとする船から伸ばした曹健南の手に張美[王其]をたくすが、自らは岸壁に取り残されてしまう。『レッド・ダスト』の悲劇がここでも繰り返されてしまうのである。だが、離れていく張美[王其]に向かって李光華は叫ぶのだ。
「必ず台湾まで辿り着いてみせる。待ってろ!」
遠ざかる船をいつまでも見送る李光華。吹き続ける風が李光華の髪をなぶる。
張衛健の歌う主題曲「風繼續吹」が、その場面にかぶさっていく。哀調を帯びたバラード。
やがて船が見えなくなると、李光華は積み残した木箱のひとつに腰をおろした。何年も何年も苦労して運んできたにもかかわらず、積み切れなかった箱がそこには山のように残されていた(資料によると、このときおよそ七五〇箱の文物が積み残されたということだ)。
李光華はふと、自分の座っている木箱にこじ開けようとした跡があることに気付く(ここでピタッと主題曲がとまる)。それは、かつて李光華自身が、青龍玉を取り戻そうとしてこじ開けようとした跡だった。
(13)
一九四九年十一月二十九日。重慶西郊外の白子駅飛行場に二機のダグラスC54が翼を休めていた。周辺では砲声が鳴り響き、難民の行列が慌ただしくいきかっていた。すでに、この重慶をはじめとするほんの数カ所の都市を残して、中国は共産党軍の手に陥ちていた。そして、重慶が陥ちるのも、もはや時間の問題でしかなかった。
三台のトラックが飛行場の中に走り込んできて、ダグラスC54の隣にとまった。トラックに乗っていた男たちが飛び降りて、木箱をトラックから飛行機に積み替えていく。その木箱に入っていたのは、河南博物館に保管されていた殷墟の発掘品であった。最後の最後の瞬間になって、最も貴重な発掘品が取り残されていたことが判明したのである。
すでに重慶は混乱のきわみにあり、発掘品を運び出すような余裕はなかった。だが、飛行機の手配や発掘品の移送という困難な任務を、一人の男が中心となってやりとげたのだった。その男は、荷物が無事に積み込まれたことを確認すると飛行機に乗り込んだ。そして、操縦席に腰をおろすと、ポケットからボロボロに擦り切れた本を引っ張り出してコックピットに置いた。軍隊が使っている飛行機操縦法のテキストブックだ(この男が李光華だということは誰にだってわかるのだけれど、カメラはいっこうに男の顔を写そうとはしない。いわゆるお約束の演出というやつである)。
それを見た仲間が声をかける。
「おいおい、まさか本をみなけりゃ操縦できないっていうんじゃないだろうな」
「なに、単なるお守りさ」
男は笑いながら答えて、慣れた動作でスイッチを入れていった。エンジンがうなり、プロペラが回り出す。そして、滑走路を走り出したダグラスC54は滑らかに空に浮び上がった(前の場面でピタッととまった主題曲の続きがここでスッと流れはじめる。だが、それはすでに哀調を帯びたバラードなどではない。力強い生命力に溢れた歓喜の歌だ)。
操縦桿を握る男の顔がようやくスクリーンに映る。もちろん李光華だ。ここで主題曲がグイと盛り上がる。思わず快さいを叫びたくなってしまうような場面だ。この時のディッキー・チョンの表情が実によくって、ディッキー・チョンのファンにとっては至福の瞬間であるにちがいない。
そして、スクリーンにはさりげなく、李光華の胸に下げられた精巧な彫り物を施された翡翠の玉が映るのだが、次の瞬間には空の彼方へと去りゆくダグラスC54の姿に切り替わってしまう。
字幕で「重慶が共産党軍の手に陥ちたのは、その翌日、十一月三十日のことであった」という説明が入り、エンドクレジットが流れ出す。
(14)
イム・ホー監督は「電影双周刊」のインタビューにこう答えている。
「私は今までずっと、歴史という巨大な流れに翻弄される人間の姿を描いてきました。それが私のテーマだったのです。しかし、しだいに「何かが違う」という気がしてきました。『風繼續吹』にとりかかろうと取材を始めて、ようやくその正体が分かってきました。人間は流されるだけではない。果敢に歴史に立ち向かい、自らの力によって進路を勝ち取ることもできるのだ。李光華について調べていくうちに、そのことが分かってきたのです」
つまり、イム・ホー監督にとって、『風繼續吹』は自らの力によって運命を切り開いた男の物語なのである。わざわざ『レッド・ダストⅡ』という英題をつけた背景には、そのことによって自分の作品である『レッド・ダスト』に挑戦するというような監督の心意気が反映されているのではないだろうか。
さて、ダグラスC54で台湾に向かった李光華は果たして無事に張美[王其]と会うことができたのか? その後いかなる人生を送ることになったのか? 映画はその疑問に答えようとはしない。そして、イム・ホー監督の手記にも、その後のことは何も記されてはいない。ただ、こう記されているのみである。
「中華文明の原点ともいうべき殷墟の発掘品を見ようと思ったならば、台北郊外の故宮博物院を訪ねれば、誰でも見ることができる。ダグラスC54は最後の荷物を無事に台北まで送り届けたのだ。だが、青龍玉と呼ばれる翡翠の彫り物は故宮博物院の所蔵目録に記載されてはいない。なぜなら、それはいま台南に住む若い娘さんの胸に下げられているからだ。もちろん、その娘さんの祖父の名は、李光華という」
(15)
イーグル・カンパニーの鷲尾氏の話によると、『風繼續吹』の海賊版ビデオは世界中の映画関係者のもとに送られたらしいということだったが、その後、この映画が業界で話題になったという話は聞いていない。突然、香港から送られてきた正体の知れないビデオに目を通そうという物好きがいなかったのか? それとも、見たうえで無視されてしまったのか? いずれにせよ、今のところ『風繼續吹』は完全な幻の映画と成り果ててしまっている。
「田荘荘監督の『青い凧』だって日本で公開できたんです。イーグル・カンパニーで『風繼續吹』を配給してくださいよ」
映画を観て興奮した僕は、鷲尾氏に『風繼續吹』がいかに凄い映画であるのかを力説し、日本での上映をそそのかした。だが、製作会社にこの映画を配給する意志がない以上、日本の配給会社に出来ることは何もなかった。そして、僕にできることといえば、こうして「電影風雲」というささやかな場でこういう映画があるのだということを紹介するぐらいのことでしかないのだ。
さて、『風繼續吹』はこのまま陽の目を観ることなく幻の映画として葬り去られてしまうのだろうか。それとも、いつの日かその姿を人々の前に現わすことになるのだろうか。いまのところ、前者の可能性の方が高そうだが、できることならば映画館のスクリーンで再会したいものである。
(初出:「電影風雲1994」1994年)

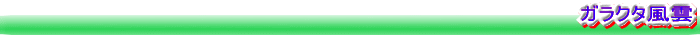
|