|
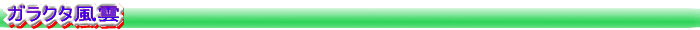
火爆城市
(ルパン三世 九龍の財宝)
第1章 企画
監督アルフレッド・チョンは語る
ボーホー・フィルムの事務所を訪れた私を、サモ・ハンはにこやかに迎えてくれた。一週間ほど前の撮影で肩の関節を痛めているはずなのだが、サモ・ハンの身のこなしには、そのような気配など微塵も感じられなかった。まことにもって、たいした男だ。80年代からこのかた、この男が香港映画界をエネルギッシュにひっぱってきたのだ。この男がいなかったならば、香港映画界の発展はかなり遅れていたにちがいない。
「さっそくだけれど、見てもらえたかな」
応接室のソファーに腰をおろすなり、私は用件を切り出した。ぜひ目を通してほしいと言って、日本製のアニメ・ビデオ一本と、コミックス数冊を渡してあった。それを気に入ってもらえたならば、秘かにあたためている企画について話しを聞いてもらう約束になっていた。
「見た。気に入ったよ。アニメの方は『龍猫』の監督の作品だね。面白かったよ。あの作品を映画化しようというのかね」
「厳密に言うならばノーだ。キャラクターだけを使いたい。あのキャラクターを使って作りたい作品があるんだ。もちろん、舞台は香港に移し、主人公も香港人に変える」
「オリジナルのキャラクターではいけないのかね」
「いけないことはないが、日本のマーケットを考えているんでね。このキャラクターは、日本では何度もテレビアニメ化されているかなりポピュラーなキャラクターなんだ。それに、僕はこのキャラクターがとても気に入っているのでね。ぜひとも自分の手で映画化したい」
「ということは、正式にキャラクター使用料を払ったうえで映画化したい、そういうことだね」
「イエス」
「なるほど。で、僕に話しを持ってきたのは何故だい? 君だったら、わざわざ僕に話しを持ってこなくても、自分で企画を進めるだけの実力はあるはずだが」
「いや。ぜひともあなたの力を借りたい。かなり金のかかる映画になる予定なので、あなたほどの実力者のバックアップが不可欠なんだ。とりあえず、僕が考えていることはこの企画書の中に書いてある。忙しいのに時間を取らせて申し訳ないが、目を通しておいてもらえないだろうか」
私は20ページほどのラフな企画書をサモ・ハンに渡した。その中には、私が映画化しようと思っている作品の基本的なストーリー、意図、アイデアがぎっしりと詰め込まれていた。これを読みさえすれば、サモ・ハンはとびついてくるにちがいないという自信があった。
「わかった。預からせてもらうよ」
サモ・ハンは受け取った企画書を二つ折りにすると、ジャケットの内ポケットにしまいこんだ。
「いい返事を期待しているよ」
「君がつまらない企画を持ってくるわけがないじゃないか。それだけは信用しているよ。ところで、君から借りたあのコミックスとビデオだけれど、タイトルは何と読むのかね。うしろの二文字はいいとして、あとは日本独自の文字だから読めないのだけれどね」
私は思わずニヤリとほくそ笑んだ。あとで教えるときの効果を狙って、わざと教えないでおいたのだ。
「『ルパン3世』、それがあの作品のタイトルだ。つまり、あの世紀の大怪盗アルセーヌ・ルパンの孫が主人公なのさ」
私の答えにサモ・ハンは大いに納得がいったらしく、大きくうなずいた。
サモ・ハンから返事の電話が入ったのは三日後のことだった。
「例の映画の件だが、レイモンド・チョウに話しをした。やっこさんはもうすっかり乗り気でね。勝手に話しを進めて悪いんだが、ウチのボーホー・フィルムとゴールデン・ハーベストが全面的にバックアップすることにした。それでいいね。九龍城に関する香港政庁との折衝もすべてゴールデン・ハーベスト側がおこなう。かなり難しい交渉になるとは思うが、なんとかなるだろう。九龍城に関する許可がとれれば、その時点でプロジェクトはゴーだ。今のうちに脚本を準備しておいてくれ」
サモ・ハンは一気にまくしたてた。
「脚本については、だいたいの骨組みはできてる。ただ、女性の扱い方にいまいち満足がいかないので、もう一度手を加えたあとでリー・ピクワーに渡そうと思っている」
「わかった。その辺は自由にやってくれ。ところで、この作品を映画化すれば、君はまた中国政府から睨まれることになる。そのことはちゃんと分かっているね」
「もちろん。覚悟の上ですよ」
「よし。ならいい。こちらも可能なかぎりバックアップしよう。ただし、ひとつだけ条件がある。僕をあの警察官の役で使ってほしいのだけどね。その条件を飲んでもらえるのならば、喜んで協力するよ。だが、もしいやだと言うのならば…」
「それはもう、こちらからお願いしたいくらいのものですよ」
「よし、決まった。しかし、君も懲りない男だな。『彼女はシークレット・エージェント』の時だって、だいぶ横槍が入ったというのに。だが、それでこそアルフレッド・チョンだ。中国の奴らに香港人の心意気を見せてやろうじゃないか。いや、世界中に香港人魂ここにありってやつを見せてやるんだ。いいか、アルフレッド、このプロジェクトは絶対に成功させるぞ」
サモ・ハンは一方的に盛り上ると電話を切った。
この瞬間、私の代表作ともなるべき作品『火爆城市(ルパン3世 九龍の財宝)』の製作が動き出したのだ。
第2章 製作準備
女優フローラ・モクは語る
そこには九龍城に住む住民のおもだったメンバーがズラリと顔を揃えていた。それぞれが一様に不安そうな表情をしている。無理もない。立ち退きを求めてしつこくやって来ていた役人がパッタリと姿を見せなくなり、一部取り壊しの始まっていた工事が急に中断したところに、突然集会の知らせがはいったのだ。しかも、その集会の主催者は映画会社なのだ。いったい何が始まろうとしているのか。皆が皆それを考えたが、見当もつかなかった。見当がつかないまま集まってきたのだ。だが、何があろうとも自分の家だけは開け渡さない、全員の表情の中にその決意だけは疑いようもなく毅然として存在していた。わたしたちは九龍城で生まれ、九龍城で育ってきたのだ。九龍城を離れることなど考えたくもなかった。
定刻になり、映画会社の人間が姿を現わした。その中によく知った顔を見つけて、わたしたちの間にどよめきが湧き上った。サモ・ハン・キンポー。香港に住んでいて彼の顔を知らない者などひとりもいない。そのサモ・ハンが一行の中にいたのだ。それに、俳優のレオン・カーファイ、映画監督のアルフレッド・チョンもいた。いったい、彼らがわたしたちに何の用があるというのだろう。
「こんにちわ、皆さん。忙しい中をわざわざお集まりいただきましてありがとうございます。今日はぜひとも皆さんに聞いていただきたいお願いがあって集まってもらいました」
一行を代表してサモ・ハンが話しを始めた。
「お願いのひとつめは、私たちの作る映画に出ていただきたい、ということです。私たちは今、九龍城を舞台にした映画を企画しています。その映画に、九龍城に住む全員の方に出ていただきたい。いかがでしょうか」
思いもかけぬ話しだった。わたしたち全員の顔に、当惑の表情が浮かんでいたことだろう。だが、サモ・ハンはかまわずに話し続けた。
「お願いのふたつめは、九龍城を私たちに譲っていただきたい、ということです。撮影が始まるまでに、九龍城からよそへ移っていただきたい」
サモ・ハンがそこまで言ったとき、いっせいに非難の声が湧き上った。わたしは当然だと思ったが、なぜか一緒になって叫びをあげようという気にはなれなかった。落ち着き払って皆の野次がおさまるのを待っているサモ・ハンを見ていると、不思議と心が揺れ動くのだ。ただ追い出されるわけではない、そう思わせる何かがサモ・ハンの態度にはあった。
ようやく皆の叫びがおさまってくると、サモ・ハンは話しを続けた。
「皆さんが反対するのももっともなことです。九龍城こそが皆さんの家なのですから。しかし、いつまでも九龍城に住むわけにもいかないということも事実です。皆さんがいかに抵抗されようとも、いずれは九龍城は取り壊されます。それが時代の流れというものなのです」
サモ・ハンは自分の少年時代の話しを始めた。ジャッキー・チェン、ユン・ピョウ、ユン・ケイ、ユン・ワーといった仲間と一緒に過ごした、京劇学校時代の話しを目を細めて語った。
「私はいつまでもその時間が続けばいいと思っていました。しかし、時代は移り変わるものなのです。何物といえども、ひとつところにとどまることはできません。そのことは皆さんもよくご存知のはずです。いずれは出ていかなければなりません。ならば、せめて賢い選択をして下さい。私たちは、映画から生じる収益の一部を皆さんにお分けするつもりでいます。もちろん、出演料は別にお支払いします。政府から出る補償金にこの金額を上乗せすれば、新しい生活を始めるための資金としては充分な額となるはずです。
私たちは、皆さんが自分たちの家を大切に思う気持ちを充分に理解しているつもりです。ですから、私たちが作る映画は、九龍城を離れる皆さんへの贈り物であると考えてみて下さい。皆さんと九龍城の姿を映画の中にとどめることができるのです。小さなお子さんがいる方は、その子が大きくなったときに、この映画を通じて今の自分を見せることができるのです。皆さんが育った九龍城の姿を見せることができるのです。ぜひとも、そういったこともお考え下さい」
サモ・ハンは話を終えた。わたしたちの間に再びざわめきがおこった。九龍城を出ていきたくはない。だが、いずれ出ていかなければならないということをわかってはいるのだ。わかっていて、わざと考えないようにしてきたのだ。しかも、今提示された条件は決して悪いものではない。だが、やはり九龍城を出ていきたくはない。
どうどうめぐりだった。
サモ・ハンに替わってアルフレッド・チョンが話し出した。『彼女はシークレット・エージェント』など、スクリーンで見る彼はひょうきんでだらしのない男だが、こうして目の前にいる彼は別人のようにしっかりして見えた。彼は自信たっぷりに自分が作ろうと思っている映画について語り出した。
わたしたちは黙って耳を傾けた。彼らが作ろうとしている映画の全貌が見えてくるにつれて、わたしは次第に感情が高ぶってくるのが自分でもわかった。本当にこんな映画を作ろうとしているのだろうか。中国政府がどう反応するか、それが気にならないのだろうか。
「私は中国人である前に香港人であると自分では思っています。ですから、香港人として「ノー」と言うべきときには断固としてノーと言っておきたい。そのためにも、なんとしてでもこの映画を作りたい。皆さんの理解と協力を求めてやみません」
彼はそう言うと話を終えた。わたちたちは黙り込んだ。いま聞かされた映画を彼に作らせたい、その思いがわたしたちに広がっていくのが手に取るようにわかった。
映画会社の人間が引き続いて話しを始めたが、わたしはもう聞いてはいなかった。頭の中で映画のシーンを描き始めていたのだ。わたしは自分をヒロインにして、空想の世界に映像を展開させていった。悪人に捕えられ危機に陥ったところを、主人公(もちろんレオン・カーファイに決まっているにちがいない)に救い出される自分。銃弾に傷ついた主人公を介抱し、やがて恋に落ちるふたり…。空想はとめどなく拡がっていった。わたしはどっぷりと空想の世界に浸ってしまっていた。
誰かに声をかけられて、わたしは空想の世界から現実にひきもどされた。気がつくと、いつの間にかアルフレッド・チョンが目の前に立っている。
「きみ、名前は?」
「莫少玲…、友人はフローラと呼びます」
わたしはドギマギしながら答えた。空想の世界に浸ってボンヤリしていたにちがいない。だが、アルフレッド・チョンは気にもせず、ニッコリと笑うとこう言ったのだ。
「きみ、女優になる気はないかな。こんどの映画のヒロインにイメージがピッタリなんだ。いままで誰を起用しようか悩んでいたんだけれど、きみを見てピンときた。こんどの映画のヒロインはきみしかいないってね」
映画会社のスタッフと住民の代表団とが何度か交渉をおこない、両者の合意が成立するまでさほど時間はかからなかった。映画会社の提示してきた条件はこちらが考えていたものよりも、はるかに良かったからだ。
こうしてわたしたちは九龍城を離れ、新しい生活を始めることとなった。そして、わたしにとっても女優というまったく新しい世界での生活が始まったのだ。
第3章 撮影現場
撮影監督デビッド・チョンは語る
「十秒前!」
アルフレッド・チョンの号令がロケ現場に響き渡った。ついにこの瞬間がやってきたのだ。最初に話しを聞いたときには、そんな撮影が本当に可能だとは思ってもみなかったが、アルフレッドはとうとうやり通してしまったのだ。
私はメインカメラにとりついて、その瞬間を待った。ファインダーの中には九龍城の全景がとらえられていた。そして九龍城の前には九龍城の元の住民たちが不安そうな表情で立ち尽くしていた。その住民たちにも別のカメラが向けられている。カメラは全部で十台用意されていた。
「五秒前!」
スタッフの間に緊張感が走る。私はフィルムを回し始めた。絶対に撮り直しのきかない場面なのだ。
「四、三、二、一」
秒読み以外のすべての音が消えた。世界中が静寂に包まれ、ありとあらゆるものが動きを止めた。一瞬、時が止まったかと思われた。
「ゼロ!」
轟音が響きわたった。静寂は破られ、世界は騒音と風と悲鳴に包まれた。
ファインダーの中の九龍城の一部が炎を吹き上げ、破片を空中に撒き散らした。それが二ヶ所、三ヶ所と増え、みるみるうちに九龍城は炎に包まれていった。大量に仕掛けられた火薬が立て続けに爆発をおこし、腹の底に響く爆音がとどろき、やや遅れて熱風が私たちに襲い掛った。
そして、最大規模の爆発をきっかけに、九龍城は大音響とともにくずれ始めた。アメリカからビルを解体するための専門業者を呼び寄せ、綿密に計算したうえで仕掛けた火薬が、いっせいに九龍城を崩壊させていった。九龍城は断末魔の悲鳴をあげていた。あたかも巨大な生物が死にあらがうかのように、のたうちまわっていた。
カメラをかまえる手が興奮に震えそうになる。それを、必死にこらえた。これほどのシーンを撮影する機会など二度とあるわけがないのだ。それをミスるなど、プロとして絶対に許されないことだ。
私は、レンズの向こうで最後の雄叫びをあげる九龍城をにらみつけ、カメラを回し続けた。
第4章 プレミア・ショー
取材者よしだまさしは語る
ひょんな偶然からアルフレッド・チョン監督の新作『火爆城市』のプレミア上映会に参入できることとなった。『ルパン3世 九龍の財宝』の邦題で日本での公開も決まっている作品だ。なんと、あの『ルパン3世』を実写で映画化してしまったのである。この作品をいち早く香港で見ることができるとは、なんというラッキー。僕は仕事も家族も放り出し、一目散に香港に駆けつけた。許せ、社長よ。許せ、家族よ。映画が僕を呼んでいるのだ。
プレミア上映会は九龍城を取り壊した跡地に建てられた香港電影文化中心の大ホールでおこなわれた。香港映画を文化として残そうというチョウ・ユンファやリー・ハンシャン監督らの努力が実って、政府の手によってようやく建てられたばかりのピッカピカの建て物である。僕はワクワクしながら招待状を受け付けで提示して会場内に入った。
会場内にはすでに招待客がギッシリと入っていた。だが、香港の有名な映画俳優や映画監督などに会えるのではないかというミーハーな期待は、あっさりと裏切られた。そこに集まっていた人のほとんどは、ごく普通の香港の人たちだった。あとで聞いた話だが、九龍城に住んでいた人全員に招待状が送られていたらしい。このプレミア上映会は映画人や文化人を対象とするものではなく、九龍城に住んでいた人を主な対象としたものだったのだ。
やがて開演時間となり、アルフレッド・チョン監督や主演のレオン・カーファイ、新人のフローラ・モクの舞台挨拶があったのだが、残念ながら広東語は全然わからないので、いったい何を言っていたのやら。フローラ・モクが舞台に登場したとき、観客席からいっせいに歓声が湧き上って驚かされたが、あとでフローラ・モクが九龍城出身であると聞かされて納得した。
ともかく、そうこうするうちに映画の上映が始まった。まずはストーリーを紹介することとしよう。なお、オバカサンの僕は、それぞれの俳優の役名をメモするのを忘れてしまったので、オリジナルの「ルパン3世」の名前そのままでストーリー紹介をすることとする。次元大介とか峰不二子の名前はちゃんと中国人の名前になっていたのだけれど、なんという名前だったかわからなくなってしまったのだ。いやはや、申し訳ない。
一九九七年六月。北京。中国人民解放軍特殊部隊本部。
その建て物にルパン3世(レオン・カーファイ)と相棒の次元大介(ティ・ロン)が忍び込む場面から物語りは始まる。建て物の奥深くに秘匿されているはずの、財宝の隠し場所をしるした地図を盗み出すためだ。
ルパンの父(つまりルパン2世)は、その生涯をかけて盗みまくった莫大な量におよぶ財宝をどこかに隠したまま亡くなっていたが、いまだにその財宝は発見されていなかった。実はその財宝の在りかを示す地図は、ルパンの父の隠れ家を急襲した中国人民解放軍特殊部隊の隊長ユン・ワーの手によって奪い去られていたのである。
その財宝の中には、戦争のどさくさに紛れてフィリピンから盗み出した山下将軍の財宝も含まれており、ゆうに一国の国家予算をすら上回るほどの財宝であるはずだった。
「お宝は、正当なる相続人、つまりオレの手に渡らなければならない」
ルパンの理屈によればそういうことになる。
だが、金庫室まで忍び込み、ようやく地図を手に入れたところで、副隊長のディック・ウェイに発見されてしまう。続々と駆けつける特殊部隊の兵士たちに取り囲まれ、ユン・ワーとディック・ウェイにとことん痛めつけられるルパンと次元。さすがのルパンと次元も格闘技ではまるっきり歯がたたなかった。ガックリと肩を落とすルパン。
「しかたがない。使いたくなかったんだが、あれを使うか」
ションボリした声で言うルパンに次元がゲッソリした顔で答える。
「あれかぁ。あれは使いたくないんだがなあ。ま、この際ぜいたくも言ってられないか」
うーん、嬉しくなってしまうではないか。アニメにおけるルパンと次元とのやりとりの雰囲気がきっちりと再現されているのだ。レオン・カーファイのセリフが山田康雄の声で聞こえるような錯覚すら覚えてしまったぞ。
で、ルパンのポケットから秘密兵器がドシャドシャと登場してふたりは無事に逃げ出すことに成功するわけだが、秘密兵器が何かということは見てのお楽しみということにしておこう。いやあ、笑った笑った。
ようやく手に入れた地図に記された宝の隠し場所は九龍城だった。もっとも、ルパンの父が財宝を隠した時点では、九龍城は現在のような巨大な建て物ではなかった。財宝が隠された上に、現在の九龍城が建てられてしまったのである。
顔を見合わせるルパンと次元。
「こりゃあ、九龍城を取り壊さないことには、お宝は取り出せないぞ」
「だから、あいつらも地図を手に入れていながら、今まで手を出せずにいたのさ」
だが、香港の中国返還まであと数日と迫っていた。はからずも、財宝を盗み出すまでのタイムリミットがきられてしまったのである。
その頃、九龍城では取り壊しを強行しようとする政府と、あくまでも立ち退きを拒否する住民との間でのあつれきが高まっていた(ここで登場するのがルパン逮捕に命をかける香港警察の銭形刑事。演じるのはこの作品のプロデュースを担当しているサモ・ハン・キンポー。そして、対する九龍城の住民を演じているのは本当の九龍城の住民たちなのだ)。一九九一年にすでに取り壊しの始まった九龍城ではあるが、意外なほどの住民の抵抗にあって、一九九七年になってもほんの一部を取り壊しただけで作業は中断したままになっていた。
だが、九龍城に潜入したルパンと次元は、住民の抵抗運動の背後に中国人民解放軍特殊部隊の支援が存在することに気がつく。香港の中国返還まで財宝を九龍城の奥深くに隠したままにしておこうと画策したユン・ワーが、住民を騙してあおっていたのである。
かくして、中国特殊部隊、香港警察、九龍城の住民、ルパンと次元、それぞれが入り乱れての虚虚実実の駆け引きが展開されることとなるのだ。
やがて、九龍城の奥深くまで潜入したルパンは、再びディック・ウェイに発見され、格闘の末に傷を負ってしまう。そのルパンを危ういところで救ったのが、住民の中心的人物である長老(ウー・マ)の孫娘、フローラ(フローラ・モク)だった。フローラの部屋に運ばれ、傷の手当を受けるルパン。彼はそこで意外な人物に出会うことになる。別ルートで財宝の存在を知って九龍城に潜入していた峰不二子(ロザムンド・クァン)とユカリ(なんと十三代目石川五エ門のキャラクターを女性に置き換えたうえで峰不二子と組ませ、大島由加里に演じさせているのである)のふたりだった。ふたりから九龍城に住む住民の窮状をことこまかに聞かされたルパンは、ウー・マに真相を打ち明け、財宝の山分けを申し出る。
協力して九龍城に潜入していたユン・ワーの部下を追い出し、地下の財宝の発掘作業を開始するルパンと住民たち。だが時すでに遅く、七月一日。香港の中国返還はなされた。港に停泊している船がいっせいに汽笛を鳴らし、街中の車がいっせいにクラクションを鳴らして、自由を謳歌した日々への別れを告げる。香港はこれから、未知の時代へと足を踏み入れることになるのだ。
汽笛とクラクションを遠く離れた国境地帯。ゴウゴウとキャタピラの音を響かせて、夜の闇の中を戦車の一団が駆け抜ける。午前零時を境に廃止された国境を越えて、特殊部隊に指揮された戦車が九龍を目指して進んでいく。
そして、運命の一夜が明けたとき、ルパンたちが目にしたものは九龍城を取り囲んだ戦車の群れだった。通報を受けて駆けつけた香港警察を無視して、住民への最後通告がなされる。
「正午までに住民は九龍城から退去せよ。悪しき資本主義の象徴である九龍城は正午きっかりに取り壊しを開始する」
抵抗して、戦車の前に座り込む住民たち。住民たちの列に加わる学生たち。香港のごく普通の人たちも続々と集まってきて、戦車の前に座り込む。だが、正午、戦車は住民を無視して九龍城に対する一斉砲撃を開始した…。
ここで、映画を見ている観客席からいっせいに悲鳴があがった。当然だ。僕のまわりで映画を見ている人のほとんどは、つい最近まであの九龍城の中に住んでいたのだ。
画面には燃え上がる九龍城をぼう然と見つめる人々の姿が写し出される。これを演じている人たちもまた、僕のまわりで映画を見ている人たちなのだ。ちなみに、このシーンの撮影は本当の九龍城を爆破して撮影している。香港政府に代わって九龍城の取り壊しを引き受けた映画会社が、取り壊しと映画撮影とを同時におこなってしまったのだ。だから、崩れゆく九龍城を見つめる人々の哀しみの表情は演技などではなく、本当の哀しみの表情なのだ。つまり、この映画はフィクションでありながら、同時にドキュメンタリーの要素をも内包してしまっているのである。
さて、いよいよクライマックスだ。炎に包まれ崩れ落ちる九龍城の中をフローラを抱いて駆け抜けるルパン。銭形と手を組んで対戦車砲で対抗する次元。斬鉄剣を手に戦車に一対一の対決を挑むユカリ。果たして財宝を手に最後に笑う者は誰なのか。轟音をあげて崩れ落ちる九龍城を背景に、ルパン一家対特殊部隊の最後の闘いの幕は切って落とされたのだ。ジャーン!!
イヤッホー!!なのだぞ。行け行けぇ!!なのだ。
そして、最後にはとんでもないどんでん返しがあって…、いやいやそこまで書くわけにはいかない。これはもう、見てのお楽しみというやつなのだ。
映画が終り、最後のクレジットが流れ出すと、場内は拍手に包まれた。涙を流して抱き合っている人たちもいる。それは、感動的な光景だった。ひとつの映画が、これほど観客の心を動かすのを僕は見たことがなかった。もちろん、観客のほとんどが九龍城に住んでいた人たちだからこそ、これほどまでに盛り上がったということは否定できない。だが、この作品が傑作であるということも誰にも否定できないだろう。
娯楽作品として超一級であると同時に、この作品には明確なメッセージがある。天安門事件を決して許してはいけないのだと、この映画は叫んでいるのだ。『彼女はシークレット・エージェント』でも一九九七年の中国返還を見据えた映画を撮っているアルフレッド・チョン監督であるが、『火爆城市』での天安門事件の扱い方はあんな生易しいものではない。九龍城を取り囲んだ戦車の前に住民たちが立ちふさがる場面は、誰がどう見たって天安門以外のなにものでもないのだ。この作品は間違いなく香港でヒットするだろうし、外国でも話題になるだろう。そして、アルフレッド・チョン監督が中国から目をつけられることも間違いのないところだろう。それが分かっていながらこの映画を作った、その映画人魂に心から敬意を表したい。
とにかく、傑作である。たっぷり笑える場面もあるし、ハラハラドキドキする場面も充分に用意されている。香港映画ファンなら、いや、映画ファンならこの映画を見ないという手はない。絶対の自信をもってオススメするので、日本公開の日がやってきたなら、ためらいなく映画館に足を向けてほしい。

プレミア上映会のあとでアルフレッド・チョン監督に話しをうかがう機会があった。その内容は今回の旅行やインタビューをセッティングしてくれたイーグル・カンパニーの発行する映画雑誌「イーグル・プレス」に掲載されることになっているのでそちらを読んでほしいが、ひとつだけ、アルフレッド・チョン監督から日本人へのメッセージがあるので、その要約を記してこの長文の原稿を終えることとしたい。
「私の映画を楽しんでいただければさいわいです。しかし、楽しんだあとで、ぜひとも天安門事件のことをもう一度考えてみてください。私はメッセージ色の強い映画はあまり好きではありませんが、それでも敢えてこの映画を作ったのは、世界中の人にそのことをもう一度考えてもらいたいからです。私たちは一九九七年をさかいに、あの天安門事件を引き起こした政府のもとに返還されます。そのことの意味を考えてみてください。特に日本の人には隣人としてだけではなく、あの天安門事件を真っ先に「なかった」ものとして許した国の国民として考えていただきたい」
僕自身もあまりメッセージ色の強い映画は好きではない。娯楽映画は単純に娯楽映画として楽しみたい。だが、時には目を背けずに、現実を見据えるということも必要なのだ。
【多 謝】
この原稿はアルフレッド・チョン監督、女優のフローラ・モク、カメラマンのデビッド・チョンの各氏のインタビューをもとに再構成したものです。僕のような素人にこころよく話しを聞かせていただいたことを感謝します。また、香港でのプレミア上映会に参加する機会を与えてくれ、なおかつさまざまな取材の便宜をとっていただきましたイーグル・カンパニーのジェームズ・H・鷲尾氏に心より御礼を申し上げます。どうもありがとうございました。イーグル・カンパニー配給によるこの作品が日本でもヒットすることを心より祈っています。
【資 料】
監 督 張堅庭(アルフレッド・チョン)
製 作 鄒文懐(レイモンド・チョウ)
洪金寶(サモ・ハン・キンポー)
脚 本 張堅庭(アルフレッド・チョン)
李碧華(リー・ピクワー)
撮 影 鐘志文(デビッド・チョン)
音 楽 黄霑(ジェイムズ・ウォン)
戴楽民(ロメオ・ディアズ)
主題歌 梅艶芳(アニタ・ムイ)
美 術 奚仲文(ユー・チュンマン)
武術指導 元奎(ユン・ケイ)
出 演 ルパン一家
梁家輝(レオン・カーファイ) ルパン3世
狄龍(ティ・ロン) 次元大介
關之琳(ロザムド・クァン) 峰不二子
大島由加里 ユカリ(十三代目五エ門)
香港警察
洪金寶(サモ・ハン・キンポー)銭形刑事
李修賢(ダニー・リー)
中国人民解放軍特殊部隊
元華(ユン・ワー) 隊長
狄威(ディック・ウェイ) 副隊長
九龍城住民
牛馬(ウー・マ)
莫少玲(フローラ・モク)
林威(ラム・ウェイ)
林正英(ラム・チェンイン)
九龍城住民の皆さん
ゴールデン・ハーベスト/ボーホー・フィルム製作
一九九二年作品(117分)
(初出:「電影風雲1992」1992年)

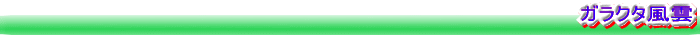
|
