|
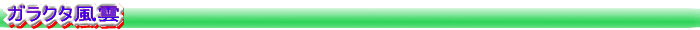
マニラの夜の小さな冒険
M-16をフルオートで撃った時の反動の予想以上の激しさ、S&Wの引き金に指をかけて慎重に狙いを定める時の緊張感、そして自分の撃った弾がターゲットの空ビンをコナゴナに砕いた時の快感、銀翼のダコタが滑走路を離れて大空に舞い上った時の興奮、あれらは本当にあったことなのだろうか。日本に戻り、平凡なサラリーマン生活を送っていると、いささか信じられなくなってくる。僕の今までの日常生活からあまりにもかけ離れた経験であった。あれ以来、僕の中の何かが変わったような気がする。すっかり舞い上ったままなのだ。
さて、あの三泊四日の気違いじみた旅について何の報告をしたらいいのか。おそらくシューティングとダコタについては誰かが書くに違いない。それに、シューティングとダコタは興奮感激の経験ではあったけれども、あくまでも他の人間が準備してくれたレールに乗っかっただけなので、冒険という味付けがちょっとばかり薄かったような気もする(もっとも、ゲリラに囲まれた時にこっそりヴィデオカメラをまわした時は、少なくとも本人は大冒険のつもりだったのではあるけれども)。
そこで、二日目の夜、ホテルの近くのスーパーマーケットまで買い物に行った時のことを書いてみようと思う。少なくとも、これは自分の意志で行動した“冒険”だったのだから。
二日日の夕方、シューティングから命からがらホテルにもどってから食事にでかけるまで、ポッカリと時間があいてしまった。部屋でじっとしているのももったいないので、僕は近くのスーパーマーケットまで買い物に行くことにした。メンバーは他に三人。さっそく「行くべ、行くべ」ということになった。
ホテルで場所を開くと、ホテルの前のマビニストリートをずっと行った所にロビンソンズ・スーパーマーケットという店があると教えられる。さあ、行くべ、行くべ、と外に飛び出すと、空はすでに薄暗くなっている。なかなかいい雰囲気ではないか。
走ってきたジプニーを止め、ロビンソンズ・スーパーマーケットに行くか、と開くと助手席に座っていた男がうなづくので、うしろにまわりこんでドタドタと乗り込む。ジプニーというのは、軍用ジープを改造したものから始まった乗り物で、ギンギラギンに飾りたてられたミニバスのようなものだと思ってもらえばいいと思う。停留所というものはなく、どこでも好きな所でとめて乗り込み、降りたい所で屋根をバンパンと叩いたりしてとめて降りる。ただし、どのジプニーがどこをどう通ってどこに行くのやら、車体に書かれてはいるのだけれど、日本人にはとても分りそうにない。とにかく、勤め帰りの人々で混むジプニーに乗り込んだ我々はエクスキューズ・ミーを連発して席を確保し、運転手に目的地を告げて金を渡した(この料金は脇山女史に出していただいた。ありがとうございました。この場をかりてお礼を申し上げます。いつの日か70センタボ分のお礼は必ずいたします)。
ロビンソンズ・スーパーマーケットは三階建てのなかなか立派なビルだった。他のメンバーと別れて、エスカレーターで三階まで上る。一階が衣料品等、二階が書籍・文具・日用雑貨、三階が家具売り場になっている。三階を一廻りしてから二階でジャック・ヒギンズのペーパーバックを二冊買い、ステーショナリーのコーナーでノートを物色する。文具が好きなので、店員を呼んで「フィリピンで一番オーソドックスなノートはどれか?」とか「マニラの学生が愛用しているのはどのノートか?」などとごたごた聞いていると、突然電気が消えてしまった。停電だ。
この停電という奴がマニラ滞在中、実に頻繁にあった。ホテルのエレベーターは止まるわ、喫茶店のクーラーは止まるわでさんざんな目に会い、なるほど、マニラとはこういう都市なのか、などと思ったりもしたのだが、実はマルコスの政策による停電であるらしい。頻繁に電気を止めることによって、反勢力の力を分散させているとのことなのだが、どうも信憑性に欠けるような気がしてならない。それぐらいのことで効果があるのなら苦労はないと思うのだが。
日本では、停電でデパートがまっ暗になってしまうなどということはちょっと考えられないが、マニラではそれが起こってしまう。うーむ、これはちょっとしたカルチャー・ショックであるな、などとつまらないことを考えていると、部分的にあかりがついた。自家発電の機械をそなえてあるのだろう。そして、そのあかりのとどかない売り場には懐中電灯をもった店員がまわってくる。なかなかいい雰囲気ではないか。
それ以上の買い物をあきらめてレジに並ぶ。これに時間がかかった。なにしろ、停電でレジスターが止まってしまったので、電卓を使って計算し、その上、買った物とその価格を全てレシートに書き込んでいるのだ(後で知ったのだが、他の店でも必ず商品と価格を書き込んだ領収書のようなものをくれた)。おかげで待ち合せの時間はあっという間に過ぎてしまい、しぴれを切らした脇山サンが捜しに来たのだが、まだ時間がかかりそうなのをみてとると、さっさとホテルに帰ってしまった。あとに残された僕ともう一人は延々とレジの前に並んで自分の番を待った。
この時、僕のうしろに学校の制服のようなものを着た若い女性が二人いたので、学生ですか、と聞いてみた。もし学生だったら、ノートのことを聞いてみようと思ったのだ。ただ気になったのは、制服の胸にたらしたネクタイに“大学”という文字がはいっていたことだ。いくらカタカナや漢字のはいったTシ
ャツがたくさん出まわっているからといって、学校の制服にまで漢字がはいるだなんて、とても考えられないではないか(実際に漢字やカタカナのはいったTシャツを着ている若者が多く、一番傑作だったのは“スキャンティ”と書いてあったピンクのTシャツだった)。
学生ですか、と開くとその二人は笑いながら違うと答えた。でも、ここに大学と書いてあるじゃないか、と言うと、なんとこれがカラオケの店の名前なのだという。つまり、彼女たちが着ている、セーラー服にどことなく似ている服はカラオケ“大学”の制服なのだ。きっと、スケベな日本人がゾロゾロと演歌でも歌いに行くのだろう(カラオケについても面白い話があるのだが、長くなってしまうので割愛する。とにかく、日本のカラオケをおいた店がたくさんあるのだ)。
さて、ようやく買い物を済ませて二人で外に出る(この時、停電にもかかわらずエスカレーターだけは動いていた。エスカレーターを動かすくらいなら、レジを動かしてほしいと思うのだけれど、フィリピン人の考えていることはどうもよく分らない)。外はすっかり暗くなっている。なにしろ町中が停電なのだ。ますますもっていい雰囲気ではないか。
またジプニーを止め、アンバサデー・ホテルに行くか、と開くと、またまた助手席に座っていた男がうなづくので、やれ助かったとばかりに乗り込む。すると、まわりの客がアンバサデー・ホテルがどうのこうのと言ってくる。その、どうのこうのという部分がよく分からないのだが、どうやらアンバサダー・ホテルには行かないと言っているらしい。そこで情けない声を出して「アンバサダー・ホテル、オーケー? ノー、オーケー?」と聞くと、またしてもどうののこうのと言ってくる。
あれ、やっぱり行かないのかな、なんて思ったとたんにググーッとジプニーは左の道にまがってしまった。ありゃりゃ、やっぱり行かないのか、なんて悠長にかまえてる場合じゃない、あわててジプニーをとめて飛び降りた。もちろん外はまっ暗。本当にいい雰囲気ではないか。
ジプニーでしばらく走ったのでかなりホテルに近づいた。おそらく歩いても20分くらいのものだろうということにして、二人でトボトボと歩き出した。ダウンタウンのかなり治安の悪い場所だとは聞かされていたが、幸か不幸かまっ暗なのでこちらが日本人だとばれる心配もない。用もなさそうなのに暗い道端でブラブラしている現地の兄ちゃんたちは不気味だけれど、まあ大丈夫だろう、とたかをくくって闇の中を歩き続ける。
さて、だいぶ長い文章になってしまったけれど、そろそろクライマックスである。今しばらくのご辛抱を。
いささか怯えながら歩いていると、突然、空が光った。思わず立ち止まって空を見上げると稲妻がサーッと走った。ところが不気味なことに全くの無音なのである。音のしない稲妻などありそうにもないのだが、これが本当のことなのだ。ピカッ!というような激しさはないが、一条の光がくりかえしくりかえし空を走る。中には下から上に向かって夜空をつっ走るのまである。マニラで、夜で、停電で、たったの二人で、音のしない稲妻が走るなんて、全くもっていい雰囲気ではないか。ハマー・プロだってロジャー・コーマンと手に手をとって逃げだそうという程のしろものではないか。
とにかく、そこに立ち止まって稲妻を眺めていても仕方がないので歩きだす。僕は稲妻よりも人妻の方が好きなのだ、なんてしょうもないことを考えていると、蝋燭の光でやっている店があった。店の名前は“ホビット”。ほう、トールキンの世界ではないか、と思った瞬間、そうまさにその瞬間に、その店の中から突然二人の小人が飛び出して来たのだ!! ウッギャーッ! あやうく迸りそうになる悲鳴を必死におさえ、ヘタヘタとくずれおちそうになる膝を一生懸命につっぱる。な、な、なんだなんだ、なんなんだ。パニックに陥りそうになるのを必死に自制するが、頭の中はすっかりバニック。ただ、あまりにも突然の出来事にドギモを抜かれて体が何の反応も起こせなかったにすぎない。
ところが、突然飛び出して来た二人の小人は何するわけでもなく唐突にまた店の中に戻ってしまった。なんなんだ、一体。お前たちはビックリ箱か。全くもってもう、やけくそにいい雰囲気じゃないか。
マニラというのは実に恐ろしい都市で、たかが買い物に行くだけでこれだけの経験ができてしまうのである。それにしても、あれらは本当にあったことなのだろうか。日本に戻り、平凡なサラリーマン生活を送っていると、いささか信じられなくなってくるのである。僕の今までの日常生活からあまりにもかけはなれた経験ではないか。
またどこかに行きたい、そう思っている今日この頃なのである。

前列一番右が僕で、その隣が内藤陳会長。後列右から4人目が若き日の馳星周(笑)、左端が馬場啓一さん。
(初出:日本冒険小説協会会報「鷲(イーグル)」第3号)

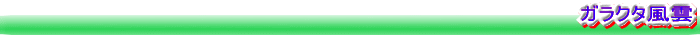
|
